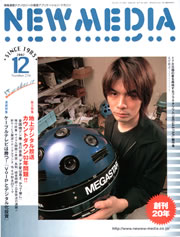| 現在のアナログのテレビ放送では、6MHzの帯域幅を使って1チャンネルの標準テレビ放送(SDTV)を行っているが、地上デジタル放送では、帯域幅約429kHzの「セグメント」を1単位として構成し、最大13個を組み合わせて(帯域幅約5.75MHz)送信される規格となっている。 |
1. デジタル放送技術の基本的な流れ デジタル放送を支える技術として、圧縮符号化、誤り訂正、多重、変調・復調などの各デジタル技術がある。 ・圧縮符号化技術:人間の視聴覚の特性などを利用し、アナログ信号を量子化してデータ量を数分の1から数十分の1へ圧縮する。 ・誤り訂正技術:さまざまな条件下での伝送を可能とする。 ・多重化技術:映像信号、音声信号、データ信号を1つの伝送チャンネルで送ることを可能にしたもので、デジタルならではのサービスを実現する。 ・デジタル変調・復調技術:さまざまな伝送路での送受信の関係を変化させ、誤り訂正技術と合わせることで家庭などで、高品質な受信が可能となる。 2. 地上デジタル放送方式の5大特徴 (1)BSデジタル放送など他のメディアとの整合性 (2)ハイビジョン放送および多チャンネル放送が可能 (3)マルチパス(ゴースト)障害に強い (4)移動体受信が可能 (5)SFN(単一周波数ネットワーク)などで、より周波数の有効利用が可能 3. 「セグメント」の組み合わせ 地上デジタル放送では「セグメント」と呼ぶ単位を、最大13個を組み合わせて送信する。 1セグメントは帯域幅約429kHzのブロック。圧縮方式のMPEG-2システムで規定されたグループに、受信機側で利用するパイロット信号を付加したもので構成される。 4. 変調方式「OFDM」の採用 OFDMは変調方式というよりも、周波数多重の方式という役割で、マルチパス(ゴースト)障害に強いという特徴をもっている。 地上デジタル放送では、セグメントごとにQPSKやQAMなどの変調方式を独立して指定できることから、固定受信向けと移動受信向けの放送を混在して送信できる。 しかも帯域中央部のセグメントでは、1セグメントのみを受信できる受信機に対応する送信ができるようになっている。 5. ゴースト(マルチパス)障害への対応 伝送路に障害物があると、電波に遅延ができ、本来の波とゴーストによる反射波の2つで合成されたものが受信機に入力されるため、アナログ放送では、映像がだぶって映るゴースト障害が発生する場合があった。 地上デジタル放送では、こうした障害を防ぐために伝送時に「ガードインターバル」と呼ぶクッション部を設け、余計な成分が混在する期間を省いて復調できることで、ゴースト障害を防いでいる。 6. アナログ放送との最大の相違は「移動受信」 自動車などで移動しながら受信する場合、送信所からの直接波と大地や建物からの反射波の合成波として受信されることと、移動する時間の経過でも受信電波のレベルなどが大きく変化する。そのためにアナログ放送ではゴースト画面や乱れが起こり、安定した受信ができなかった。 地上デジタル放送では、移動受信に伴う受信波の急激なレベル変動などを考慮した伝送方式を採用し、安定した映像や音声、データの受信を可能にしている。 採用した伝送方式は以下の通り。 (1)変調方式としてDQPSKを採用 (2)時間的にデータを分散させて伝送する時間インターリーブを採用 (3)ガードインターバルによる反射波の除去 7. 電波の有効利用を可能にする「SFN」 アナログ放送では隣接した中継局が同じ周波数を使用して放送すると、電波の到達時間の差と電波の強さの差が画面上にゴーストとして現れる。 地上デジタル放送のOFDM方式では、単一周波数中継(SFN)によるゴースト妨害を軽減できる。このため、周波数を少しずつずらしていた隣接の中継局からの電波を、同じ周波数で送信できるため、周波数の有効利用ができる。 |