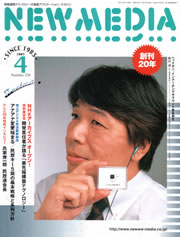2003年2月1日、テレビ放送開始50年を機に、東京・愛宕山にあるNHK放送博物館がリニューアルオープンした。既存の2Fの展示室に、新たに3・4Fを増設し、日本の放送の始まりであるラジオの時代から現在のハイビジョン放送まで、まさに日本の放送の歩みと歴史を、当時の貴重な放送機器や資料・映像で見て、聞いて、感じることができる国内唯一の場となっている。今回の増設では、NHKアーカイブス(埼玉県川口市)とネットワークで結ばれた番組公開ライブラリーのコーナーが新たに設けられ、来館者が番組に直接触れる楽しみも増えた。 世界の放送界のなかでも、放送開始直後より関連資料の保存の重要性を認識し、博物館を並存させてきた放送局はNHKだけという。 2月1日には、約50年前にわが国独自の設計で作られたTKO-3型イメージオルシコンカメラ(1955年、和久井孝太郎・工学博士、設計)により、テレビ50年記念番組が実際に撮影・放送され、テレビ放送50年の歴史と2003年の現在がシンクロする時間を体験できる貴重な1日となった。 愛宕山地区再開発で、標高26メートルの山を上下するエレベータが完成し、高齢者や車いすの方も訪れやすくなったNHK放送博物館。その成り立ちとリニューアルされた館内の様子を、フォトレポートを交えてお届けする。 (桐山佳代子=月刊ニューメディア編集部) 日本の放送の歴史とともに歩んだ 愛宕山の地 愛宕山はまさに日本の放送のふるさとである。大正14(1925)年3月22日、東京芝浦にあった東京放送局の仮放送所から日本のラジオの第一声が流され、その約4カ月後の7月12日、当時は緑豊かな山だったという愛宕山から本放送が始まった。 その後、敗戦により愛宕山の局舎は一時期GHQにより接収されたが、昭和28(1953)年2月1日のNHKテレビ本放送開始(内幸町の新局舎より放送)にあわせて、NHKへと返還された。 その日本の放送のシンボルともいえる愛宕山の地を、放送の役割や大切さを知ってもらうために活用できないかと、ラジオ放送開始30年目の記念事業として昭和31(1956)年に誕生したのが、世界でも貴重な存在であるNHK放送博物館だ。当時の準備委員会の呼びかけで、各方面から寄せられたさまざまな放送機器や資料が展示され、その後昭和43(1968)年には現在の建物に建て替えられ、展示内容も拡充されていった。 さらに、平成8(1996)年には放送開始70年を記念して、展示室を全面改装。ラジオの第1回からハイビジョンに至る放送の歴史と技術の発達を系統立てた、よりわかりやすい展示内容となった。収蔵品は放送機器、文献、図書、その他さまざまな資料類を合わせて3万955点。そのうち約500点(うち放送機器267点)が現在展示されている。 説明ボランティアの熱意溢れる話に 涙する来館者 入館者数は、平成11(1999)年9月23日に300万人を突破。改装のために閉館した平成14(2002)年9月までに、約331万人が訪れている。 海老沢勝二・NHK会長は今回のリニューアルオープンの挨拶のなかで「現在、年間約10万人の来館者があるが、今後はその3倍、30万人が目標。テレビ放送開始50年という節目の現在、国内の景気は低迷しているが、日本人には受け継いできた確固たる技術力がある。その技術を基に、視聴者みんなが元気になれる質の高い番組をつくり、送り出していきたい。それが我々放送人の使命だと考えている」と語った。 また、中川志郎・日本博物館協会会長がリニューアルオープンの式典で「生涯学習という新しい教育体制により、社会教育の核として博物館の役割が大きくなっている。日本の博物館約3,500のほとんどが戦後にできたもので、戦前からのものはこのNHK放送博物館をはじめほんの数パーセント。まさに、博物館の歴史そのものでもある。また、博物館にはコレクション機能とサービス機能が大切。そういった点からも、NHK放送博物館の今後の展開に期待したい」と述べたように、博物館のさらなる充実が望まれる社会状況のなかで、NHK放送博物館にはまさにNHKならではの力強いサービス機能がある。それは、NHKのOBのボランティアによる館内説明だ。現在、10名の説明ボランティアの方々が、1日2〜3名の交替制で館内に張り付き、来館者にマンツーマンのように丁寧な説明をしてくれる。どなたも、かつてはNHKの現場で活躍されてきた方々だけに、エピソードを交えた解説内容はまるで“生きる放送歴史書”のように詳しく、そして熱心だ。説明員の方の話に、当時を懐かしんで思わず涙ぐむ来館者もいるという。日本の放送の一端を担ってきた方々の熱意と自負があってこそできる、生きた視聴者サービスである。「今後は、状況に応じて説明ボランティアの増員も考えている」と、中田薫・館長はいう。 「放送」という性質上、 動態保存・展示にこそ意義がある また、中田館長は「我々は、機器類の動態保存・展示に特に力を入れている。当時の状況を実際に体感していただきながら、さらに後世に残していくのが我々の役目。TKO-3型イメージオルシコンカメラの動作復元などもその一環。また、これからますます増大していく収集品の、何を残し、何を廃棄していくのか。系統立った収集・保存の視点が必要であり、その手法を確立していきたい。さらに今後は、館内のどこかで、いつでも何かをやっている、例えばイベントやセミナーや視聴会、コンサートなど、来館者が参加して楽しめる博物館にしていきたい」と、次代へ向けた抱負を語った。 4階に新設された番組公開ライブラリーは、まさに参加して楽しめるコーナー。デジタル時代の技術を基盤に、新たな視聴者サービスが実現されている。また、3階の「テレビ放送の50年」のコーナーでは、技術の進歩と番組表現の進化を関連付けながら見ることができる。大河ドラマや紅白歌合戦の衣装なども間近に見られ、来館者は時間を忘れて、放送の世界に浸ってしまうに違いない。 |