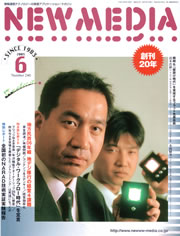自動車や家庭用などの分野でPEFC(固体高分子形燃料電池)が注目を集めているが、ここにきてSOFC(固体酸化物形燃料電池)の開発、実用化準備が盛んになってきた。これまで実用化の障害になっていた技術的課題を新材料やシステムの開発で克服。各種の燃料電池の中で最も高い発電効率や、高温の排熱を有効活用できるといった特徴(図1)を生かし、PEFCが対応できない市場を開拓する動きである。日本市場での独走体制を狙い先行スタートを切った住友商事、急増する通信事業関連のCO2排出量の大幅削減を目指してSOFC導入を計画するNTTグループの取り組みや、注目の先端技術開発の最前線をレポートする。 (渡辺 元=月刊ニューメディア編集部) 2005年に市場投入する住友商事 米国のSOFCメーカー、アキュメントリックス社の日本総代理店である住友商事は、日本におけるSOFC事業のトップランナーである。2005年に日本仕様の製品を本格的に市場投入する計画だ。 住友商事は燃料電池分野で、燃料から各種燃料電池システムまで手広く展開している。例えば2002年、世界最大のメタノール製造会社の加メタネックス社に出資し、民生用商品の日本総代理店になっている。国内の携帯電子端末用DMFC(ダイレクトメタノール形)の燃料カートリッジを含めたインフラ市場を抑えるための有力な布石である。PEFCでは2000年、米プロトンエナジーシステムズ社に出資している。その他、ケミカルハイドライドなど新技術を含む各種燃料、電池材料、燃料電池車用高圧タンクなど、燃料電池分野全般で各分野の企業と協力関係を築いている。住友グループに重工メーカー、重電メーカーがないことが、かえって燃料電池事業の“手札”を増やす好結果になっているとも言える。 高温型燃料電池に関しては、SOFCに注力。日立製作所などが撤退したMCFC(溶融炭酸塩形)については、電解質が液体で制御が難しいといった技術的問題があり、実用は困難と見ている。低温型はPEFCとDMFC、高温型はSOFCに集中投資する考えである。 アキュメントリックス社は今夏、燃料電池のシリコンバレーを目指して企業誘致を進めるコネチカット州に、月産200台の能力を持つ世界初の量産工場を稼働開始する。今年7月に10kWシステム、今年末に100kWシステムの出荷を米国で始める予定である。同社は住友商事の他、米国の電力会社、ガス会社、石油会社、軍需企業の4社も出資し、経営陣を送り込んでいる。 住友商事は国内での2005年の市販開始に向けて、2004年からアキュメントリックス社製品を国内仕様に開発した製品を十数カ所でフィールド試験し、より良い製品に改善する。北海道から沖縄まで、全国のさまざまな気候、使用環境下で運転。耐久性・限界性能試験などを通して、燃料にする日本の都市ガス成分への対応、遠隔操作、補機、部品、デザインなどについて検討する。 コンビニ、ファミレスに狙い アキュメントリックス社のSOFCは、現在世界標準と目されている米シーメンス・ウェスチングハウスパワーコーポレーション社(SWPC)製品の仕組みとは異なる。アキュメントリックス社の燃料電池開発統括技術者は、SWPCの技術の長所、短所を熟知している同社の元幹部である。アキュメントリックス社製品には、SWPCとは全く違う手法で、小・中規模分散発電システムに適した技術が取り入れられている。 SWPC製品は水素が満たされた加圧空間に精密に作られた円筒形スタックを配置し、スタック内部に空気を供給する仕組みである。起動に約20時間かかるため、デイリー・スタート・アンド・ストップは不可能。連続運転を前提にした小型プラントの概念で設計されている。 それに対して、アキュメントリックス社製品の仕組みは、“SWPC製品の逆”である。マイクロチューブ型スタックの内側が燃料極で、メタンなどの燃料を直接供給し、スタック内部で部分酸化改質を行う。SOFCの上部に熱交換機を設置し、熱自立運転できる。熱自立を実現したSOFCメーカーは、世界でも数少ない。 同社のマイクロチューブ型スタックは、外側から一気にバーナーで温めることができるため、室温状態からでもわずか30分で起動可能である。住友商事は日本市場にはデイリー・スタート・アンド・ストップが可能なアキュメントリックス社製品が適していると考えている。構造上小型化できるのも特徴。今年末米国で発売予定の100kWシステムは、SWPC製品のおよそ1/5程の大きさになりそうだ。省スペース、メンテナンスの容易さなどの利点は大きい。 住友商事は日本市場では当初、10kWと100kWのラインアップで展開する。まず2004年に10kWシステム10台程度をフィールド試験として、そして2005年から数十台を市販製品として、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、スーパーマーケットなどで運転する。100kWシステムも同年にフィールド試験を行う。 10kWシステムの実用機は、吸収式冷凍機とSOFCを組み合わせたユニットとして販売する予定である。SOFCから冷凍機に冷熱を供給し、環境対策だけでなく、チルド温度で冷やせるという付加価値を訴求する。100kWの実用機は電話会社の基地局、携帯電話中継局、データセンター、地域冷暖房、集合住宅、災害対策車などでの利用を狙う。すでに大規模な地域冷暖房用として、100kWシステムを複数台並べる引き合いもあるという。さらにSOFCはCOも燃料にできるため、製鉄工場、化学工場、石油精製所などから出るCOを含んだ副生水素を活用したシステムでの利用にも期待する。 本格的な市場展開のためにも、住友商事は国内メーカー数社との共同事業体(JV)設立も視野に入れている模様。日本全国でメンテナンス可能な体制を作り、2〜3年で国内のSOFC市場での独走態勢を築くことが目標だ。 NTTのCO2排出量を1割削減 通信関連のエネルギー需要が大幅に増加し続けている。それに対してNTTは、グループ各社の通信施設にSOFCを導入することによって、通信関連の電力消費によるCO2排出量の削減を目指している。NTT環境エネルギー研究所で新型SOFCシステムと材料の開発が進められており、すでに大きな研究成果を生んでいる。 通信の光化が進むことで、通信設備でのトラフィック量当たりのエネルギー消費量は、今後減少していくだろう。しかしそれを織り込んでも、トラフィック量の急増によって、NTTグループの2010年における電力消費量は、1990年の約3倍に上ると予想されている(図2)。そのためNTTグループは、低消費電力化と共にクリーンエネルギーの導入によるCO2排出量削減を図っている。その一環として、通信施設へのSOFCの導入を検討している。SOFCの他にクリーンな夜間電力の利用なども含めると、2010年のCO2排出量を約10%削減するという大きな効果が期待できるという。 NTTグループの通信施設では、エネルギー消費のほとんどを電気で賄う。その多くは通信設備と空調の電源である。空調は高信頼性で低コストの電気空調を多用しているため、空調の電力消費量が全電力消費量の約20%に達している。 クリーンエネルギーの内、太陽光発電や風力発電などは供給量が不安定であるため、高い信頼性が要求される通信施設のメイン電源には使えない。そこで通信施設の規模に対応でき、燃料電池では発電効率が最も高いSOFCを選択した。 新システムと新材料を独自開発 通信施設の建物はスペースに制約があるため、NTT環境エネルギー研究所は発電効率の向上と小型化に向けた材料やセル、システムに焦点を絞り込んで開発を進めている。その結果、現在最も有望な技術として、(1)改質器とSOFC本体による二重発電、(2)新材料による高出力密度の電解質膜と電極材料、(3)ゾルゲル法による超微粒子触媒の導入−−を開発した。これらの組み合わせで、ガスタービンなどを用いなくても60%の高発電効率が可能と見ている。 改質器とSOFC本体による二重発電は、部分酸化改質型SOFC(POSOFC)を使用する。POSOFCでは燃料の都市ガスを改質しながら発電も行う。そして作り出した燃料を使ってSOFCでも発電する。POSOFCで燃料改質する際の吸熱反応には、SOFCの排熱を有効利用する(図3)。POSOFCとSOFCで二重発電する方式の開発は、他社ではまだ実用化レベルには達していない模様である。 POSOFCで最大の問題は、都市ガスの分解による炭素の析出だ。炭素析出を抑制する技術が、POSOFCを実用化させるためのポイントになっている。同研究所ではこれを電極触媒の高活性化によって解決しようとしている。 第1に、従来のSOFCの空気極材料に使われるランタンストロンチウムマンガン酸化物((La,Sr)MnO3)より酸素還元触媒特性が優れた、ランタン鉄ニッケル酸化物(LaNi(Fe)O3=LNF)を開発した。 電解質膜についても新素材を開発した。従来のSOFCに使われているイットリア安定化ジルコニアよりイオン導電特性が優れた電解質材料、アルミナ添加スカンジア安定化ジルコニア(SASZ)である。イットリアの代わりにスカンジアを使うことで、イオン伝導性が高くなる。しかし、スカンジア安定化ジルコニアは約600℃で相変化し、急激に伝導性が低下する。アルミナを約1mol%添加することで相変化が起こらず、高伝導性を維持できる。またSASZは薄膜化できるという特徴がある。薄膜化によって抵抗が下がり、イオン導電特性がさらに向上する。 第2に、ゾルゲル法で超微粒子触媒を電極の表面にコーティングする技術を開発した。超微粒子は直径100nm以下(写真1)。電極触媒の表面積が増える上、低温でも高活性で、電極反応を促進する。POSOFCにおける炭化水素の分解による炭素析出反応と電気化学反応とは、競争反応であるため、電気化学反応の効率を向上させれば、炭素析出が抑制されると考えている。ゾルゲル法を用いれば、セル作製工程を大きく変更しなくても、電極特性の向上が可能となる。 今後、燃料極にゾルゲル法で高活性の超微粒子触媒を導入し、炭素析出の抑制を図る研究を行う。 SOFCだけで発電効率60%が目標 この空気極材料のLNFと電解質材料のSASZ薄膜の組み合わせで、直径約3cmのセルを作製した。セルの出力密度は、0.7V・800℃で1.3W/cm2、0.7V・750℃で0.85W/cm2と、世界トップレベルを記録。長期的な耐久性は実験中だが、今のところ少なくとも数週間レベルの耐久性は問題ないという。従来のSOFCでは、起動・停止を繰り返している内に電極触媒と電解質膜との熱膨張率差によって、電極触媒が剥離してしまうのが課題になっている。同研究所が開発した空気極材料のLNFと電解質材料のSASZは、熱膨張率が非常に近いため、耐久性と長期的安定性が期待できる。今後セルの大面積化、スタック作製、システム化を進める。 POSOFCとSOFCを組み合わせたシステムには、排熱を利用したガスタービンなどは連携しない。ガスタービンを使う加圧方式にすると、大型で高価にもなる。頻繁にSOFCを停止して、ガスタービンのメンテナンスを行う必要も生じる。そのため、ガスタービンを使わずにPOSOFCとSOFCだけで60%の高発電効率を狙う。かなり高い目標だが、計算上は可能だという。 2004年に1kWのモジュールを試作し、検証を行い、2007年から100〜200kWを中心に実用化する予定である。全国のNTTグループの通信施設への導入を目指す。同研究所では、CO2排出量だけでなく電力コストも削減できると期待する。 ナノテクで高耐久・高性能化 このところSOFCの材料開発が活発になっている。その中でも、NEDOのナノコーティング技術プロジェクトにおいて(財)ファインセラミックスセンター(JFCC)が日本特殊陶業(株)と共同で開発に成功した、高温の動作温度でも耐久性のある電極は、注目すべき技術の一つである。今回開発したのは、空気極のランタンストロンチウムマンガン酸化物の電極を柱状晶構造で電解質にコーティングした電極膜。JFCCの電子ビーム物理気相成長装置によるEB-PVD法で、ジルコニア系の電解質に蒸着させた。 電極の柱状晶は長さ約4μm、太さ約0.3μmで、一本一本が独立して電解質上に立っている(写真2)。この構造が耐久性をもたらす。触媒の粒子を電解質の表面で焼成する従来の電極は、電解質との熱膨張率差によって、剥離しやすい。柱状晶は基材の電解質の伸縮に合わせて自由に移動できるため、剥離しにくい。 この電極膜の特徴は耐久性だけではない。電極は柱状晶の側面がさらに羽毛状になっているため、表面積が非常に大きく、電極反応が高効率で行われる。さらに、電極を従来の焼成温度の1,100〜1,200℃より低い約1,000℃で蒸着することによって、ランタンジルコネート(La2Zr2O7)が生成される界面反応を防いでいる。ランタンジルコネートは酸素イオン伝導抵抗が高く、従来の空気極ではイオン伝導性低下の一因になっている。 JFCCと日本特殊陶業では、成膜条件を変更して柱状晶の構造を制御する研究を進めている。すでに柱状晶の長さ、太さを変えたり、蛇行させることに成功している。EB-PVD法の低コスト化も検討中である。JFCCでは今回の開発とは別に、低温作動SOFC用の材料開発も進行中だ。 各企業、研究機関、大学のSOFC開発は、市場展開を視野に入れた本格競争に突入した。 |