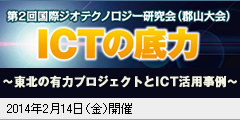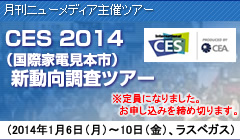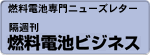月刊ニューメディア 2011年2月号掲載
連載 メディア関係者のための国際情勢
ジョセフ・ナイ・ハーバード大教授が論じる日米同盟の対中戦略(後編)
〜日経・米戦略国際問題研究所(CSIS)共催シンポジウム報告〜
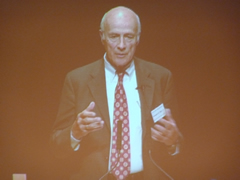 基調講演を行うジョセフ・ナイ・ハーバード大教授
基調講演を行うジョセフ・ナイ・ハーバード大教授 第7回日経・CSIS共催シンポジウム「安保改定50周年、どうなる日米関係」が2010年10月19日に東京で開催され、弊誌はその模様を取材した。同シンポジウムは日本経済新聞社と米戦略国際問題研究所(CSIS)の共催。前原誠司外務大臣など日米の安全保障担当者や研究者が講演やパネルディスカッションを行った。この中で、クリントン政権の国防次官補(国際安全保障問題担当)などの要職を歴任したジョセフ・ナイ・ハーバード大教授が基調講演を行い、日米同盟の対中戦略について見解を語った。中国の台頭に日本の世論が翻弄されている中、米国の外交政策に強い影響力を持つナイ教授はどう現状を分析し、対策を示したのか。レポート後編の今回は、パワーの均衡と経済の統合を合わせた対中政策と日米同盟の在り方に関する議論をまとめた。
(渡辺 元・本誌編集部)
クリントン政権の対中政策
ナイ教授は米中間の経済力、軍事力の格差、中国が抱える経済的、政治的な課題の深刻さから、「中国と米国が今世紀に戦争を行う必然性はない、というのが私の見方だ」としながらも、東アジアにおける米中紛争の可能性も否定しない。
「何らかの事件が台湾で起こる危険は常にある。中国は追い詰められたならば、あるいは追い詰められたと感じたならば、攻撃をするというリスクを選ぶ可能性もある。1950年の朝鮮戦争のときがそうだった。台湾がその可能性は少ないと思うが独立を宣言したならば、中国はおそらく軍事力を行使するだろう。そして米国は軍事力でそれに応えるだろう。中国がその戦争に負けたとしても、その地域、関係国にとって非常に大きな悲劇となる。中国から生まれるこの紛争についても、事前にいろいろなシナリオを検討すべきだ」
中国の台頭に対応した日米の長期的戦略のモデルとしてナイ教授は、クリントン政権で国防次官補(国際安全保障問題担当)として検討した対中政策を挙げた。当時、政権内のタカ派は中国に対する封じ込め政策を提案したが、ナイ次官補(当時)はそれは適切ではないと考えた。外交的な支持が得られないことと、中国が確実に敵対すると考えたためだ。
「そこで我々が採択した政策は、リアリズムとリベラリズムを合わせたものだ。つまりパワーの均衡と経済の統合を盛り込んだ。日米の安全保障同盟を強化することによって、中国が日米の間に楔を打ち込むことができないようにすると同時に、WTOへの加盟など国際制度に参加するように中国に働き掛けたのだ。我々の中国に対する経済的な対応は、冷戦時のソ連に対する封じ込め政策とは全く違う。冷戦時には、我々はソ連とはほとんど経済関係がなかった。一方、我々の中国に対する政策は、取り込むけれどもヘッジもするというものだった」
経済的相互依存と国際的課題での協力
ナイ教授は日米が現在採用すべき対中政策として、同様にリアリズムとリベラリズムを合わせた政策を提案した。その内のリベラリズム政策の有効性については、自らが提唱する相互依存論に基づいて論じた。
「経済的相互依存の状況では(両国間に)対称性がある。ロバート・コヘイン氏と私は約30年前に『Power and Interdependence(権力と相互依存)』(1977年)を著した。同書では、非対称性がある場合にはパワーが発生し、対称性がある場合にはパワーは発生しないということを論じた。我々がとった中国を統合化する政策によってリスクが生じたとは考えない。したがって(現在の)日米両国にとって、経済的な統合と不確実性に対するヘッジは重要な政策となる。このようにして、ロバート・ゼーリック氏の言葉を使えば、責任あるステークホルダーになるように中国に働き掛けるべきだ」
さらに日米と中国の経済的相互依存だけでなく、日米中が共通して直面している国際的課題への対応における協力関係を構築することを提案した。
「日米中とも国境を越えるいろいろな問題に直面している。そしてその問題には我々の死活的な利益がかかっている。日米中は3カ国間の協力、あるいは地域的な協力を進めていくべきだ」
日米中が直面している国境を越える問題とは、パンデミック、テロ、破綻国家の影響、気候変動などだ。特にCO2排出への対策では日本は進んでおり、強みを活かせる領域だとナイ教授は指摘した。
グローバルな公共財としての日米同盟
一方のリアリズム政策については、日米同盟の維持とアジアの友好国による圧力が重要だと述べた。
「今後数十年間繁栄し、安定した東アジアをつくっていくためには、日米が二つのことを維持することが重要だ。一つは自信、それから同盟関係の維持だ。また、もし中国が好戦的になった場合は、インド、オーストラリア、ベトナムなどアジア諸国の力を得て封じ込め政策ができる。ただし、現状では封じ込め政策に動くべきではない」
ナイ教授は日米同盟の維持だけでなく、同盟の対等化も進めるべきだと述べた。対等化の領域としては、安全保障ではなく、国境を越える諸問題への対応での日本の貢献に期待した。
「日本の友人は、日米同盟は対等ではないということを指摘する。安全保障の領域では、日本が自らに課した制限によってそれが生まれている。しかし新しい領域においては、日本はより対等なパートナーだ。日本のODAはアフリカからアフガニスタンまで広く行われている。医療のプロジェクトにも参加している。国連に対する支援、海賊取り締まり作戦に対する関与、省エネルギーの研究開発といったことは、国境を越える問題に対する対策として非常に重要だ。オバマ政権もこれらをとても重要視している。日本は非常に大きな潜在力を持っており、地域内だけでなくグローバルなシビリアンパワーとして、これらの活動に貢献できる」
最後にナイ教授は、日米同盟の安定と、同盟をグローバルな公共財にすることが、日米中の良好な関係にとって必要であると主張し、基調講演を結んだ。
「日米はもう一度、我々の同盟をこの安保改定50周年に再確認する必要がある。もちろん様々な問題はあるが、それらはあまり大きな問題ではない。日米共通の国益は非常に大きい。日米同盟を均等なパートナーシップにすること、そしてグローバルな公共財とすることは、日米中にとっても、世界全体にとっても良いことだ。日中、日米、米中のそれぞれの3辺が良好な関係を持った三角形は、日米同盟が安定していなければ成り立たないということを強調したい」