(2005年以降の号)
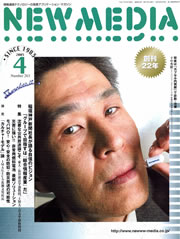
●特集 沈着な公共放送論こそ
嵩に回る論調がNHKを包囲している。「NHKの体質が問題」とか「独裁で風通しが悪い」などサンドバッグ状態のNHKである。真偽定かではない政治家の圧力という問題が助長する。専門誌たる弊誌は、一時の感情的な議論に与することなく、沈着な検討を加えたい。
・橋本新会長が解決すべき“宿題”(音 好宏)
・法学者から求めたい論点と方向性(長谷部恭男)
・公共財としてのメディアを考える
●地域と地上デジタル放送(2回連載特集 第1回)
・サンテレビ+松下電器+兵庫県 データ放送の強制割込型「緊急防災情報提供システム」を開発
・28道県が地デジ普及で検討会発足 「山間僻地にしわ寄せはゴメン!」
・神戸新聞社社長に地域「総合情報産業」展望を聞く(稲垣嗣夫・清水信一)
・<地デジ×知事インタビュー「試される地デジのビジョン」(第5回)>沖縄県 稲嶺惠一知事−−国は民放局のデジタル負担に対し、税制優遇ではなく直接支援策が必要だ
●モバイル端末向け衛星デジタル・マルチメディア放送(DMB)「モバHO!」の災害時アプリケーションの可能性(山口慶剛)
●<連続大論究 「デジタル放送時代のカルチャーモデル」論(第12回)>長瀬文男・(株)IMAGICA代表取締役社長×重延 浩・(株)テレビマンユニオン代表取締役会長・CEO−−世界最先端の技術は常に、最初にIMAGICAが手掛ける
●特集 災害に強い!! 非常用燃料電池
自動車用や家庭用の市場投入が大きな話題になっている燃料電池だが、防災用の非常用燃料電池が発売され、ディーゼルエンジン式など従来型にはない利点があることは、あまり知られていない。普及が大いに期待される非常用燃料電池の特長と市場の反応をまとめた。
・エネルギー政策の転換と災害対策の両面で、分散型電源への期待が高まっている(柏木孝夫)
・経営レベルの観点でエネルギーシステムのリスクを診断する「エネルギードック」(小笠原政教)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・<プロジェクト「地上デジタル放送全国行脚」(最終回)>「北の大地」が抱えるいくつかの課題(高瀬徹朗)
・多品種変量生産の拠点 ソニーが「湖西テック」工場を公開
・大判プリンターNO.1を目指してキヤノンから大判インクジェットプリンター新機種発売
・乗降客30万人以上の地下鉄「京都駅」で携帯電話を使った避難誘導実験を行う(曽崎重之)
・インテルがノートPC用モバイル・テクノロジーを強化
・松下電器 双方向サービスの新ソリューション
・厚労省テレパソロジー研究班第2回班会議開催
・「中曽根憲法改正試案」に「知財」条文明記 時代錯誤だと一蹴してはならない時代センス
・障害を持つミュージシャンのためのオーディション「ゴールドコンサート」第2回開催
●NHKデータオンラインの「各地のニュース」始まる(宮崎経生・斎藤 聡)
●<デジタル・パブリッシング提案(第35回)>携帯電話を学習ツールに!(佐藤 渉)
●『全国デジタル放送化動向調査2005』 走破した!「デジタル全国行脚」
●<地デジ放送電波の問題(第11回)>サイマル放送期間 デジタル放送用「テレビ中継回線」はどうなる
●21世紀の放送経営と所有規制 世界の最新動向(隈部紀生)
●地域づくりとしての「日本型ネットデイ」(和崎 宏)
●松下電器 放送局設備のSI新会社を設立(片倉達夫・小林政夫)
●<カーネギーメロン大学(CMU)情報大学院日本校(第3回)>地域経営ビジョン「“減災”の思想」具体化の一環として絶対に成功させる(長棟健二)
●CTY開局15周年 学校インターネット、IP電話無料化(森 紀元)
●JWAY開局 日立市民のケーブルテレビの始まりだ!(杉本 弘・吉田 要・宇佐美得眞・小川 清・藪下憲一・野村昌雄)
●DCAjデジタルコンテンツグランプリ セルシスが2年連続受賞の快挙(川上陽介・野崎愼也・濱野保樹)
●<飛躍するBB遠隔医療(第1回)>遠隔医療における映像・ブロードバンドの活用状況(東福寺幾夫)
■連載
●<今月の表紙>「カプセル内視鏡」の技術開発へ挑む−−下中秀樹・オリンパスメディカルシステムズ(株)医療研究開発本部CP-プロジェクトリーダ、穂満政敏・CP-プロジェクト開発グループ課長代理、本多武道・CP-プロジェクト開発グループ課長代理、原 雅直・オリンパスシステムズ(株)ソフトウェア開発1部係長
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<編集後記「BETWEEN」>

●エプソン、富士通ゼネラル、日立、松下、三洋、ソニー「3LCDグループ」を結成!
・液晶パネルD5シリーズで「フルHD」を実現(麻倉怜士・岩野英明・下斗米信行・古畑睦弥)
●渦中の海老沢勝二NHK会長に直撃90分インタビュー 不祥事の経営責任、会長職、海老沢独裁批判などすべてを話す
7月20日に不祥事があったことを発表してから、海老沢会長の肉声は12月19日放送の『NHKに言いたい』や謝罪メッセージであったものの、会見の発言になると、その一部がセンセーショナルに伝えられるだけになった。そこで、海老沢会長にズバリ、会長としての責任の取り方、包囲するジャーナリズムへの反論、公共放送NHK再生の確信など、90分にわたって本音を聞いた。2004年12月24日、NHKにて。
・会長として「NHK再生の道筋」にこだわり、取り組むべきだ
●今年4月、個人情報保護法全面施行 顧客情報漏洩を監視カメラで防ぐ!?
大手企業から、中小企業、学校、自治体まで、相変わらず顧客情報漏洩が頻発する中、個人情報保護法が今年4月、全面施行される。顧客情報を保有する企業は、徹底した安全対策を迫られている。情報漏洩防止策には様々なものがあるが、監視カメラには、どのような効果、そして課題があるのか、取材した。
・顧客情報漏洩の抑止効果は認めるが、映像が新たな個人情報保有リスクに(関本 貢)
●<連続大論究
「デジタル放送時代のカルチャーモデル」論(第11回)>岡 康道・TUGBOAT代表×重延 浩・(株)テレビマンユニオン代表取締役会長・CEO−−海外でこてんぱんにやられても、国際的レベルに達してみたい
●<連載 メディアの学校(第12回)>団体経営のメディアの学校(浜野保樹・森川喜和)
・親睦会レベルから脱却して人材育成重視へ傾斜(内田真理子)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・<プロジェクト「地上デジタル放送全国行脚」>デジタル放送時代、災害に油断禁物(高瀬徹朗)
・日立の地上デジタルローカル局 タイアップ販売促進施策(設楽雄二)
・インテルのデジタルホーム構想
・日本ビクター 世界初、BD-DVDコンビネーションROMディスク技術を開発
・総務省の新情報通信政策「u-Japan政策」 2010年の活性化した日本実現のための目標と行程表を提示
・リンクシェア・ジャパンが三井物産から分社独立 3年以内の上場を目指す
・DCAj「第19回デジタルコンテンツグランプリ」の受賞作品決定
・全日遊連が諮問機関「未来型パチンコ産業創生会議」を設置
・研究者に会える2泊3日! 先進的科学技術体験合宿「スプリング・サイエンス キャンプ」参加者募集
・「AES東京コンベンション2005」技術発表募集
●NTT Comが画期的なサービスを提案 望まれていたデジタルハイビジョン“非”圧縮伝送
●<デジタル・パブリッシング提案(第34回)>デジタルパブリッシングデータをそのままインターネットで活用(小林 真)
●<カーネギーメロン大学(CMU)情報大学院日本校(第2回)>アジア全域から学生を集めるために神戸へ打って出るCMUの経営戦略
●地デジ「2011年問題」研究会報告 県域デジタル放送局のショールーム−−NHK水戸放送局
●3回目のデジタル紅白歌合戦 本番直前から密着取材 最終得票数(6万9,037)は前回横ばい
●T-COM CATV業界初のケーブルIP網利用VODサービス サービス開始1カ月間で新規IP加入者の10%をゲット(藤原智哉)
●<新聞・テレビの株名義「虚偽記載」問題(下)>放送法55年目にマス排問題を間接から直接の規制へ転換すべき
●CESレポート 時代のキーワードは「ブロード」だ! “キャスト”と“バンド”が「ブロード」でマリッジする(麻倉怜士・吉井 勇)
●<シリーズ「今さらだけど、知りたい!」>韓国の画づくり(安達武志)
●ソニー 無人カメラからIP伝送で生中継 低コストの新システムに放送局やCATV局が注目(田中 誠)
●イトーキ マルチ画面用プレゼンテーションソフト「リアルマルチ」シリーズ 1台のPCでパワポ、エクセルをマルチ画面表示
●日本SGIが開発 世界最小・最軽量のユビキタス・モニタリング・サーバ「ViewRanger」
●高臨場感映像 広がるアプリケーション、一大市場形成へ(原 啓起)
■連載
●<今月の表紙>1ミリ角の「T」の文字を読み取る−−桜井貴康・東京大学国際・産学共同研究センター生産技術研究所第3部教授・工学博士、染谷隆夫・東京大学工学系研究科量子相エレクトロニクス研究センター助教授・博士(工学)
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<編集後記「BETWEEN」>
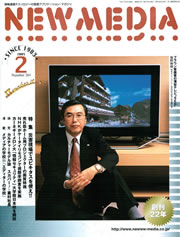
●スペックでは語れないホーム用プロジェクター 売れ筋3モデルにみる画質の特徴(麻倉怜士)
・エプソン「EMP-TW200H」 明るい室内でも変わらぬ色調(倉内新次郎・坂井健一)
・サンヨー「LP-Z3」 最上位のスケーラーを搭載(桝田悟史・渡辺昌彦・橋爪繁幸・桶谷和伸)
・日立「PJ-TX100J」 高解像力を実現(青島亜津志・板倉梨沙)
●特集 災害現場でユビキタスを使え!!
新潟・福島豪雨、福井豪雨、三重県集中豪雨、新潟県中越地震−−。2004年、日本列島は自然災害に立て続けに襲われた。被災地では交通、物流、情報通信などのインフラが寸断した。被災地で孤立状態に陥った地域社会や個人を再びつなぎ合わせる技術として、ユビキタスにできることは何か?
・災害時におけるユビキタスの活用 ユビキタスで地滑りを事前に察知できる(大石久和)
・災害時に役立つITSに向けた私案 カギを握るのは地上デジタル放送とのリンク(川嶋弘尚)
・災害時の安否情報サービス NTT「171」が活躍、平常時の利用体験がカギに
・新潟県中越地震で明らかになった、停電時の電力確保の課題 バックアップ電源の落とし穴と対策
●<カーネギーメロン大学(CMU)情報大学院日本校(第1回)>世界最高・最強の情報セキュリティ大学院
●NHKが実施 ケータイリモコンで視聴率調査
●<連続大論究
「デジタル放送時代のカルチャーモデル」論(第10回)>重村 一・(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズ代表取締役社長×重延 浩・(株)テレビマンユニオン代表取締役会長・CEO−−「マーケットの論理」で日本の放送は変質した
●<連載 メディアの学校(第11回)>エディターの学校(浜野保樹・稲庭恒夫・福田 収)
・「エディターの学校資料」 専門分野別コースが人気(久保友香)
・上海市松江区の「大学城」に2大コンテンツ制作拠点
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・<プロジェクト「地上デジタル放送全国行脚」>交通事情は放送事情!?(高瀬徹朗)
・富山増力、フルパワーに 北日本放送とNHK富山
・びわ湖放送「MJ」(モバイル・ジャーナリスト)組織化
・ケータイ1セグ放送の受信装置が次々と提案
・総務省発表 県庁所在地「開局ロードマップ」
・日本テレビビデオが新スタジオと新HD中継車を公開
・ビギナーでも楽しく使えるRSSリーダー 放送番組との連動企画も検討中
・「京都デジタル疎水ネットワーク」 KBS、NHK京都が生中継利用
・“FOMAメソッド”で災害報道の新しい可能性に挑戦 テレビ電話機能付き携帯電話で被災者のメッセージ映像を放送(智片通博)
・「ひまわりネットワーク防犯パトロール隊」発足 警察と提携した東海4県初の試み
・電通総研編集のデータブック『情報メディア白書2005』発刊
●<デジタル・パブリッシング提案(第33回)>旅行プラン作成サービス(松山憲和)
●<連続特集 メディア大年2005(第2回)>
・2010年の日本とメディアの変貌 ユビキタス+ユニバーサル+ユニーク(吉崎正弘)
・フルHD時代に突入 大画面薄型テレビ シナリオを握るパッケージメディア(林 秀介)
・“動き”が伝わるNTT「ワープビジョン」 病理医は必ず使いたくなる(澤井高志・安藤清和・村尾成隆・熊谷一広・出口秀一・長谷川達彦・海野 大)
●<シリーズ「今さらだけど、知りたい!」>次世代デジタルインターフェース規格「HDMI」(長谷川教通)
●特集 VRの最前線
・第二世代のVR「HoloStage」 中国・韓国で爆発的進化の予感(廣瀬通孝)
・これがクリスティの「HoloStage」の迫力だ(半澤 衛・関内 進)
・ソリッドレイ研究所 床がゼニを生む! インタラクティブ・グランドスクリーン「タップトーク」(神部勝之)
●ゾクゾクと地上デジタル放送開始 兵庫、神奈川で12月1日スタート NHK神戸、サンテレビ、テレビ神奈川(松沢成文・伊達木昂訓)
●東海テレビ サイマル放送ハイブリッド方式のリアルタイム双方向クイズ番組(田島 誠・林 佳典・新垣好二)
●<地デジ×知事インタビュー「試される地デジのビジョン」(第4回)>茨城県 橋本 昌知事−−2009年までに地デジ全県下普及 ケーブルテレビに強い期待
●上智大・音 好宏助教授が聞く“前倒し組”の決意と戦略
・京都放送 メキシコ「テレビサ」との提携は海外への番組展開の足掛かり(加藤哲夫)
・岐阜放送 「宝物の上に座ったまま」ではいけない(杉山幹夫)
●<地デジ放送電波の問題(第10回)>このままではチャンネルが足りなくなる
●<新聞・テレビの株名義「虚偽記載」問題(上)>新聞社、キー局の出資実態は「マス排原則」などどこ吹く風!
●<Webアクセシビリティ提案(上)>「アクセシビリティにするとダサくなる」に反論(濱田英雄)
■連載
●<今月の表紙>ブラウン管より約100倍の電界に耐える技術−−福間和則・(株)東芝 ディスプレイ・部品材料統括統括責任者
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<編集後記「BETWEEN」>

●特集 2006年春デビュー! 地デジ・1セグ放送 テレビとケータイの究極タッグ
地上デジタル放送の「1セグメント放送」が2006年春開始というスケジュールが確定してきた。1セグメント放送は、「ケータイ電話やケータイ端末による移動受信」と「1セグ・データ放送」と合わせ、通信との連携が考えられている。急速に関心が高まってきた。
・1セグ放送の規格と準備状況(黒田 徹)
・戦略インタビュー NHK−−データ放送の独自展開と通信系サービスの連動で公共放送としての役割をさらに担う(土屋 円・山内雄敦・加藤久仁)
・戦略インタビュー 日テレ−−広告メディア価値は「思わず行動してしまう」リーセンシー効果にあり(佐野 徹)
・戦略インタビュー 電通−−1セグ放送の視聴約30分 広告メディアとして有望(二瓶浩一)
・戦略インタビュー NTTドコモ−−番組のダイジェストを視聴できる「OnQ」(上原 宏・副島義貴・高間亮行)
・戦略インタビュー KDDI−−他業界と組んだビジネスモデルの成功体験を活かす(酒井清一郎・神山 隆・石橋義徳)
・受信端末の課題 ディスプレイ−−4〜6インチ液晶ディスプレイでHD表示 新サービスの登場は技術をさらに進化させる(松島 聡)
・受信端末の課題 電源−−ケータイ本体を大型化させずに連続視聴時間を伸ばすという難題
・東海テレビ 地上デジタル放送と連動した次世代型会員カード「Yappass(ヤッパス)」を発行(加賀敬章)
・現行アナログ放送で双方向番組 JNN系東北5局がケータイ、PCからリアルタイム参加 双方向クイズ番組を生放送
・NTT東日本 視聴者のネット参加番組を現行アナログ放送から実現する「クロスメディアプラットフォーム」(高木誠一・山根 聡・林 佳典)
・インデックス 現在のアナログ放送からケータイ双方向サービスを先行 ローカル局の収入源となるケータイサイト運営を提供(金本成生・吉田 直・野川明良)
●<連載 メディアの学校(第10回)>声優・アナウンサーの学校(浜野保樹・神谷 明・有賀さつき)
・「声優・アナウンサーの学校」資料 人気絶頂の部門だけに授業料も高いのだ(日塔 史)
●<連続特集 メディア大年2005(第1回)>
・総務省 地デジ開始1年 奇跡的なほど順調なアナ変作業、勢いあるデジタル受信機普及だが、課題は「2011年アナログ停波」の国民への告知(南 俊行)
・CEATECとWPC Expoに見るデジタルホームネットワークの未来(姉歯 康)
・ポスト・ブラウン管の覇権 決め手は“新画質”
・FPD International展示レポート ゴング鳴った 液晶同士の激闘!?
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・<プロジェクト「地上デジタル放送全国行脚」>情報格差=デジタルデバイド?(高瀬徹朗)
・電動車椅子サッカー大会でモバイルライブ中継実施
・「CEATEC JAPAN 2004」に登場したユビキタス村(久保田直美)
・NTTがリアルタイム処理できるスケーラブル映像CODEC開発
・地上デジタル移動体受信 名古屋で公開デモ
・KBS、世界最大級のテレビ局Televisaと提携し、テレノベラ『ゲーム オブ ライフ』放送開始(久津間愛味子)
・<貝谷嘉洋の視点>第38回東京モーターショー「働くくるまと福祉車両」ここに注目!
・ホームシアターのハイエンドモデル「フルハイビジョン液晶プロジェクター」富士通ゼネラルから発売
・村瀬孝矢・日本画質学会副会長が画質の見方を教授する本『画質の世紀』を発刊
・「第14回サーティファイグランプリ2005」作品募集中
●ユビキタス情報化社会の風にのるモーター王・白木学の中国知財戦略
●モバイル放送がスタート NHKからもニュースや人気番組を提供(浜崎浩丈・岡本樹一郎)
●世界初 移動体向け衛星デジタルマルチメディア放送「モバHO!」登場(溝口哲也・末永雅士)
●<デジタル・パブリッシング提案(第32回)>eラーニングシステム「MST」シリーズ(國富郷太郎)
●<シリーズ「今さらだけど、知りたい!」>SXRDデバイスの応答速度は、なぜ速い?(橋本俊一)
●<地デジ×知事インタビュー「試される地デジのビジョン」(第3回)>兵庫県 井戸敏三知事−−災害時の緊急放送としてケータイのテレビ受信(1セグ放送)は期待が大きい
●<連続大論究 「デジタル放送時代のカルチャーモデル」論(第9回)>「カルチャーモデル」論には、これを毒と知りながら飲み込んでしまう度胸がある(渡辺 誠)
●JWAY 日本一安い価格で最高のサービス提供ができるインフラ構築を目指す(杉本 弘・吉田 要・中村康次・村田富哉・今橋徹也)
●松下電器 ローカル民放局の地上デジタル放送開始に向けてスピード、ローコスト、多重回収 この3つが提案コンセプト(片倉達夫・小野淳哉)
●電気通信自由化20年 世界で一番テレコムビジネスを知っている男にこれからのメディアの行く末を聞く(林 紘一郎)
●「第9回地域安全環境研究会」東京大会 竹花豊・東京都副知事の“貴重”講演(澤田麻記子)
●国際共同制作を促進するAFCNet(アジア・フィルムコミッション・ネットワーク)発足(前澤哲爾)
●<Webアクセシビリティ提案(上)>Webアクセシビリティの基本の考えとデザイン問題(濱田英雄)
■連載
●<今月の表紙>“指トン”動作の周波数を検出する「UbiChip」を開発−−福本雅朗・(株)NTTドコモ マルチメディア研究所・生体信号処理研究室室長、工学博士
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<編集後記「BETWEEN」>