バックナンバー紹介
(2004年の号)
(2004年の号)
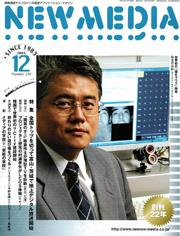
2004年12月号(2004年11月1日発売)
●全国トップを切って茨城、富山で地上デジタル放送スタート
昨年12月1日に始まった三大広域圏を除く全国のトップを切って、茨城県と富山県の2県で地上デジタル放送が始まった。県域テレビ放送局がない茨城県ではNHK水戸放送局が開始し、富山県では北日本放送とNHK富山放送局の2局が同時にスタートした。
・茨城県 NHK水戸放送局−−“最後で最初”の開局
・富山県 NHK富山放送局、北日本放送−−地デジ先進県・富山へ意欲
・北日本放送−−ローカル民放のトップを切って地上デジタル放送開始
・地上デジタル放送に向けた設備の設計と概要(佐伯則男)
・朋栄が北日本放送地上デジタル放送のテロップシステム全般を担当
●<連続大論究 「デジタル放送時代のカルチャーモデル」論(第8回)>平野友康・(株)デジタルステージ代表取締役×重延 浩・(株)テレビマンユニオン代表取締役会長・CEO−−終わりのない遊び場をつくる
●最新映像機器を画質体験・評価
・日立のハイビジョン“Wooo”7000シリーズ−−画質の「奥ゆきの美学」を提案(麻倉怜士・長谷川 敬・岡 尚弥・島上和人・川村知之・鈴木宏幸)
・サンヨー「CAPUJO」−−デザインコンセプト「つるるん」がいい!!(麻倉怜士・河合晃弘・岡本敏一・川本 準・清水正人)
・キヤノンのLCOSを使ったデータプロジェクター「SX50」−−これだけ高性能で、こんなにコンパクト!(村瀬孝矢)
●韓国で世界初の本格的なu-City建設開始 ICT分野のリーダー、キム・ヨンボク・NETfam社長
●<連載 メディアの学校(第9回)>芸能の学校(浜野保樹・竹中 功・三坂知絵子・清水宏一)
・「芸能の学校」資料(久保友香)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・<プロジェクト「地上デジタル放送全国行脚」>これでいいのだテレビ新潟! これでいいのか「しなやか県政」?(高瀬徹朗)
・すべてのチャンネルが無料視聴可能という“違法チューナー”に対しては厳正対処の方針(山本 学)
・CEATEC JAPAN 2004レポート−−ストレージメディア、ディスプレイ、燃料電池
・「場所が話しかける」インフラづくり 神戸でプレ実証実験開始
・「第4回中小企業のためのHPコンテスト京都2004」 年々向上するコンテンツ
●<デジタル・パブリッシング提案(第31回)>電子メディア対応の出版ソリューション(槇本英治)
●「商店街監視カメラの運用実態調査」報告 商店街監視カメラの違憲性(第2回)
●<地デジ×知事インタビュー「試される地デジのビジョン」(第2回)>宮城県 浅野史郎知事−−情報入手のスタイルが変わる今、テレビの役割も変わる
●上智大・音好宏助教授が聞く“前倒し組”の決意と戦略
・サンテレビ−−ホップ・ステップ・“ドボン”だってあるが失敗を恐れていては何も始まらない(清水信一)
・テレビ神奈川−−新社屋「第二の開局」、新コンセプト「ヨコハマ開放区」 デジタル化でさらに打って出る(牧内良平)
●追悼 主協電波委員長・大竹和博氏、本誌主催の研究会での最後の発言から
●JWAYに「有線テレビジョン放送施設設置許可状」交付 2005年春開局を目指す(吉田 要・野村昌雄・嶋岡利明)
●CSデジタル放送「スーパーチャンネル」ドラマ系初の500万世帯(宮川裕皓・額田大介)
●タイムビジネスとGPS
・“時刻配信”や“時刻認証”サービスなど推定1,500億円規模の「タイムビジネス」(竹内芳明)
・QZSS(準天頂衛星システム)−−ユビキタス時代の日本独自の新衛星インフラを構築しよう(飯沼健雄)
・GPS−−進化するITSやケータイの大インフラ 欧州の「Galileo」と協力関係へ(西口 浩)
・日本標準時はアジアの時間HUB 電波時計の販売台数は1,500万超(栗原則幸)
●企業サイトのアクセシビリティを語る(渡辺春樹・林 哲夫・望野和美・関根千佳・濱田英雄)
・日本のWebをアクセシブルに! 「アックゼロヨン」スタート
■連載
●<今月の表紙>瞳孔でカーソル移動、クリック、ドラッグ操作を実現−−海老澤嘉伸・国立大学法人静岡大学工学部システム工学科教授、工学博士
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<編集後記「BETWEEN」>
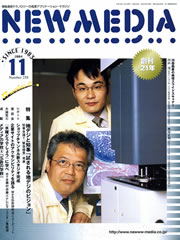
2004年11月号(2004年10月1日発売)
●全国知事会議で「緊急提言」発表 地デジと知事「試される地デジのビジョン」
知事会が地上デジタル放送への動きを強めている。8月18日、19日に開催された全国知事会議では、『地上デジタル放送に関する緊急提言』を梶原拓・全国知事会長が発表した。
・<知事インタビュー>栃木県 福田昭夫知事
・<知事インタビュー>高知県 橋本大二郎知事
●ショップチャンネル 完全24時間生放送の拠点 新スタジオビル完成(川上 正・ビル・コンセロ)
ショップチャンネルは新スタジオビル「プロダクション・ファクトリー」を拠点に、年商500億円を目指す。新スタジオビル建設責任者に対するインタビュー、レポート。
●商店街監視カメラの運用実態調査」報告 商店街監視カメラの違憲性(第1回)
●<連続大論究 「デジタル放送時代のカルチャーモデル」論(第7回)>藤村忠寿・北海道テレビ放送(株)コンテンツ本部報道制作センター制作グループ×重延 浩・(株)テレビマンユニオン代表取締役会長・CEO−−『水曜どうでしょう』に学べ
●Web広告研究会×ユーディット 企業サイトのアクセシビリティを語る(林 哲夫・関根千佳・濱田英雄)
●<連載 メディアの学校(第8回)>広告の学校(浜野保樹・中島信也・中島浩二郎)
・「広告の学校」資料(久保友香)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・<地デジ行脚レポート(第1回)>「見られればいい」では済まないのが放送(高瀬徹朗)
・松下、デジタル家電のプラットフォームを開発(蓮 憶人)
・地デジ放送施設整備の資金に「ふるさと融資制度」運用
・ソニー独自開発SXRDのリアプロジェクションテレビ発表
・朋栄「佐倉研究開発(R&D)センター」メディア見学会実施
・日本テレパソロジー研究会が遠隔医療研究会と岩手で同時開催
・松下電器がDVDレコーダー新5機種を発売、シェア4割以上を狙う
・松下電器が世界最大65V型PDP「VIERA」を発売、新プロモーションも開始
・「ITS国際会議愛知・名古屋2004」を契機に飛躍するITS関連ビジネス
●<デジタル・パブリッシング提案(第30回)>次世代ブロードバンドDMソリューション(金子抄恵子)
●「最新監視カメラ」製品提案 朋栄の高精細ネットワークカメラ「IHC-600」 600万画素監視&デジタルレコーダ一体型カメラ
●10月1日地上デジタル放送開始のNHKローカルテレビ2局、水戸放送局、富山放送局2局長に聞く(平 逞仁・塚田博通)
●民放連・地上デジタル放送特別委員長に聞く(中村啓治)
●地上デジタル放送「2011年問題」研究会報告 第1回開催「ローカル民放の『地デジ』トップランナー 北日本放送(富山・KNB)」
●アテネオリンピックで予想以上の評価と熱い関心を集めたパナソニック「DVCPRO P2」
●日立市のJWAYにケーブル関係者が70名集結! 10月1日開始の県域地デジもフォローの風
●世界最小モータなど知財で東証マザーズに上場(白木 学)
●フィルムコミッションはコンテンツ創造の重要な基盤(前澤哲爾)
●NICTのスケーラブル・バーチャル・リアリティ・プロジェクト(SVR)実証実験(廣瀬通孝・山下 淳・西岡貞一・竹内芳明・竹村崇裕)
●世界初「高画質2004」を開催(麻倉怜士・村瀬孝矢・秋山雅和)
●プロジェクターの人間工学的評価(鵜飼一彦)
■連載
●<今月の表紙>今月の表紙>3分間ほどで約36億画素をスキャンできる高速化技術−−内山 茂・浜松ホトニクス(株)システム事業部第1設計部第14部門専任部員、奥河正利・浜松ホトニクス(株)システム事業部第1設計部第14部門
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<編集後記「BETWEEN」>
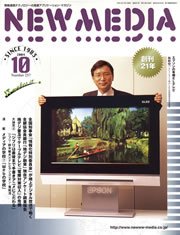
2004年10月号(2004年9月1日発売)
●本誌独自調査報告 34銀行が示すローカル民放「地デジ投資」に対する融資判断
全国銀行協会の会員であり、信託銀行除く119行の頭取(または社長)宛に、「地上デジタル放送に伴うローカル民放局の投資負担に関する金融機関の意識調査」を行った。
●<連載 メディアの学校(第7回)>Webの学校(浜野保樹・宮崎光弘・濱田英雄)
今や、作るだけなら、誰でも作れるWebデザイン。しかし、プロを養成する教育となると、未発展だ。それぞれ異なる視点からWebデザインを見つめる宮崎光弘氏と濱田英雄氏をゲストに、現場に求められる人材と「Webの学校」についてお話いただいた。
・「Webの学校」資料(日塔 史)
●全国知事会「情報化推進対策特別委員会」レポート 地元民放「いきなりの支援要請」は、あまりにも志がなさすぎないか!!
●<地デジ半年の経験でわかったこと(第2回)>地デジ普及でケーブルテレビ「電障対策収入」の危機(穴見徹正)
●<連続大論究 「デジタル放送時代のカルチャーモデル」論(第6回)>鈴木敏夫・(株)徳間書店常務取締役スタジオジブリ事業本部本部長×重延 浩・(株)テレビマンユニオン代表取締役会長・CEO−−ジブリは最後まで手書きアニメにこだわる
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・わかりやすい地デジ放送エリア D-PAがホームページを強化
・「ケーブルフェスタ2004」を東海支部が開催 一般客9万4,000人にケーブルの魅力をアピール
・「奥行き感」を重視した画づくり 日立「WOOO」7000シリーズ
・三洋がデザイン重視のプラズマ、液晶TV「CAPUJO」シリーズを発表
・ハリウッド映画の特撮技術を搭載したプロジェクター用デバイス「iSkia」
・キヤノンから最上位デジタルビデオカメラ「XL2」
・Web広告研究会が「Webプロデューサー育成講座」
・BBジャパンが「光ライフビジョン」ニーズ調査を実施
・会合の通知、返信の集計に便利なアプリケーション『連絡だよ、回答集合!』をブロードネットマックスが提供
・「水素と燃料電池会議・展示会2004」をカナダ・トロントで9月25日から開催
・ラスベガスのモノレール、やっと7月15日に開通
●NHKが展開した参議院選挙開票速報体制とデータ放送(川上啓輔・炭谷健司)
●<デジタル・パブリッシング提案(第29回)>個人情報保護とプライバシーマーク制度(内桶孝雄)
●地上デジタル放送トライアル
・DXアンテナが新方式の光ケーブルテレビを実用化
・メーテレの「データ放送による地図配信サービス」(服部清幸)
●放送経営シミュレーション・エッセイ「結局、この方法しかなかったのか……」
●京阪神ケーブルジョン(KCV)のデジタル放送センター竣工(藪下憲一・田辺千秋・鈴木一美)
●「監視カメラで何が悪い」−−監視カメラ問題の一社会科学的考察(下)(青柳武彦)
●次世代ケーブルテレビJWAY、来春開局 市民はケーブルテレビを待っている(杉本 弘・嶋岡利明・山本直人・藪下憲一・今橋徹也)
●それでも進む「開かれた学校」のセキュリティ対策
●「ITS世界会議愛知・名古屋2004」初めての市民参加型で全国50万人参加が目標
●「浮かび上がる映像」エプソンの新提案「プロジェクターサインスタンド」(成瀬文章・町田壮人・赤岩昇一・村上 実)
●<シリーズ「今さらだけど、知りたい!」>画質を決める応答速度(杉沼浩司)
●液晶では不可能といわれた黒を沈めたセイコーエプソンの次世代液晶パネル「D5」シリーズが登場(麻倉怜士・内山貞住・山崎康二・青木 透・後藤貴文)
■連載
●<今月の表紙>開発目標は「2007年製品化」−−飯野聖一・セイコーエプソン(株)OLED技術開発本部本部長
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<編集後記「BETWEEN」>
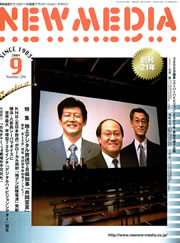
2004年9月号(2004年8月1日発売)
●特集 地上デジタル放送で8県知事「共同宣言」
6月17日、8県の知事が地上デジタル放送について共同宣言を出した。これは岩手県が総務省、日本民間放送連盟に出向いて主旨を伝えている。共同宣言の全文と、8県知事参加の第5回「地域からIT戦略を考える会」をレポートする。
・共同宣言「地上デジタル放送の活用と普及を取巻く諸課題」
・地方自治体にとって「地上デジタル放送」とは何か
・増田寛也・岩手県知事インタビュー
●地デジ最新レポート KNB(北日本放送)がローカル局初「地デジ試験電波」発射
6月30日深夜から7月1日早朝にかけて行われたマスター切り替えを取材した。試験電波の発射、デジタルマスターへの切り替えと、地上デジタル放送の形が見えてきたためか、KNB社員の“デジタル士気”もドーンと高くなった。
●横浜・八景島シーパラダイスに世界最大、半球型720インチ「デジタルハイビジョンシアター」誕生(海老沢勝二・板谷駿一・布留川信行・中村 宏)
●<連続大論究 「デジタル放送時代のカルチャーモデル」論(第5回)>山口裕美・アートプロデューサー、現代美術ジャーナリスト×重延 浩・(株)テレビマンユニオン代表取締役会長・CEO カルチャーには戦略が不可欠だ
●緊急特集 地上デジタル放送の雷害リスクを防げ!!
・地上デジタル放送の雷害リスクの実態と対策(生岩量久・池辺裕昭)
・放送が雷害を被るのは「実は恥ずかしいこと」(妹尾堅一郎)
・地上デジタル放送局の雷害対策「7大ポイント」(佐藤秀隆)
・NTTファシリティーズの総合的な雷害対策サービス「エネルギードック」(村尾哲郎)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・NHKの水戸・富山局、北日本放送に予備免許交付
・松下電器が同軸ケーブルで100Mbps実現など、次世代ケーブルテレビ技術を公開
・松下電器がDLP1チップ方式で5000ANSI lmのプロジェクターを開発
・デジハリが、今度は英語×IT×クリエイティブの4年制大学設置申請へ
・松下電器がセキュリティ事業の強化戦略を発表
・<貝谷嘉洋の視点>電動車いすでの長距離移動で見えてくる環境整備と技術課題
・栗本鐵工所が燃料電池車いすを出品
・障害者と性の問題を考える本『セックスボランティア』(貝谷嘉洋)
・IBC岩手放送と富士通FIPが「IPポータルバー」で共同事業へ
●動き出した国交省「自律的移動支援プロジェクト」 「ユビキタス」×「ユニバーサル」のまち案内(坂村 健・竹中ナミ・大石久和)
●<デジタル・パブリッシング提案(第28回)>カラーマネージメントシステムツール(中込浩之)
●見えてきた「サーバー型放送」サービス(児野昭彦)
●アテネ五輪のもう一つの挑戦−−「2波出し」を視聴者はどう選ぶか(高瀬徹朗)
●<ローカル局のデジタル化支援>松下電器−−ローカル局の細かな要望に応える「運用しやすさ」を提案(小野淳哉・堀田 勝)
●<ローカル局のデジタル化支援>ソニー−−ハイビジョンシフトを最強の「システム+オンラインサポート」で支援(花谷慎二・宮島和雄)
●最強のケーブルアライアンス、TDNのデジタル放送センターが竣工(淀 敬・森本仁郎・藪下憲一)
●手ごたえあったSCHOOL SECURITY
●「えらいこっちゃ、ケーブルテレビ」−−地デジ半年の経験でわかったこと(穴見徹正)
●日本初、開局時からフルデジタルのケーブルテレビ局「JWAY」
●日立国際電気などが警備至難立地の幼稚園のセキュリティ計画を立案
●ネットワークカメラサーバー「R-150A」をベンチャーの琉テクが独自開発
●「監視カメラで何が悪い」−−監視カメラ問題の一社会科学的考察(上)(青柳武彦)
●<業務効率化システム新時代(第6回)>ビジネスツールからVODまで客室端末で提供するサンルートホテルチェーン(姉歯 康)
●「LCD vs. PDP」いよいよ選択の規準は画質へ!(蓮 憶人)
●セルシスの急速に進化する携帯電話へのマンガ配信サービス
■連載
●<今月の表紙>600インチ超大画面「半年間・朝9時から夜9時まで休みなく」を仕上げる−−金澤 勝・NHK放送技術研究所(テレビ方式)主任研究員・工学博士、三谷公二・NHK放送技術研究所(テレビ方式)主任研究員・工学博士、濱崎公男・NHK放送技術研究所(音響情報)主任研究員
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<編集後記「BETWEEN」>
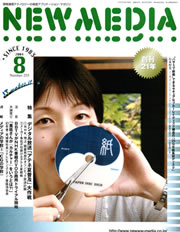
2004年8月号(2004年7月1日発売)
アテネ夏商戦で、薄型テレビがどこまで「自己新」を続けていけるのか。商戦に弾みをつけるNHKと民放のオリンピック放送計画に、目玉となるデジタル放送の新しさはあるのか。
・NHKのアテネ五輪放送計画
・地上民放、BS民放のアテネ五輪放送計画(高瀬徹朗)
・メーカー各社が仕掛けるアテネ夏商戦
●注目 BBTVがNHK番組のVOD商用トライアル開始(橋本太郎・楜澤 悟)
●<連載 メディアの学校(第6回)>CGの学校(浜野保樹・河口洋一朗・杉山知之)
・「CGの学校」資料(久保友香)
●<連続大論究 「デジタル放送時代のカルチャーモデル」論(第4回)>見城 徹・(株)幻冬舎代表取締役社長×重延 浩・(株)テレビマンユニオン代表取締役会長・CEO 良いものが売れるとは限らないが、売れたものは全部良いものだと考えない限り、表現を会社組織でやっているところは成立しない
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・第58回NHK技研公開 来場約2万8,000人
・危機感に包まれて策定されたJCTAの「業界ビジョンと戦略」
・インテル、家庭での活用をアピール 車載端末などPC以外への製品搭載にも注力
・オリンパスがより実用化された「800万画素の高精細デジタル動画システム」を開発
・液晶テレビ市場に参入する三菱電機
・超薄型リアプロジェクションTV技術を同時発表
・走る地下鉄の窓に100インチの動くCM 日本初、サブメディア方式の大型トンネル内CM
・セイコーエプソンが世界初、40型フルカラー有機ELディスプレイの試作機を開発
・ソニーが「4K SXRD」デジタルシネマプロジェクターを商品化
・2003年度JASRAC事業報告&2004年JASRAC賞発表
●日本SGIの世界最小・最軽量の監視用マイクロサーバ「SGI ViewRanger」
●<デジタル・パブリッシング提案(第27回)>クロスメディア企画制作(和泉広彦)
●エプソン、テレビ市場に名乗り 第3の薄型テレビ、大画面液晶プロジェクションテレビ「LIVINGSTATION」(麻倉怜士・永嶋伸一・古畑睦弥・下斗米信行)
●<NHK受信技術、デジタル放送普及へ走る!(第2回)>ケーブルテレビのデジタル放送普及 アテネオリンピックのチャンスを生かせ!
●<NAB2004要諦レポート(下)>HD画質、H.264/MPEG-4 AVCの「2つの潮流」は放送局をどこへ導くか
●NHKがBBTV、KDDI光プラス、J-COMのVOD商用トライアルに番組を提供
●ケーブルテレビ2004出展、松下電器のコスト1/10のPPVシステムに注目
●情報告知番組制作ツール「InfoCaster」の威力はCATV局の番組制作でも証明された
●考え抜かれた杉並区の防犯カメラ条例
●遠隔医療の現状と課題 皆「必要だ」と認めるが、事業化に至らないのは……(澤井高志・白川英俊・原田 豊)
■連載
●<今月の表紙>3つの“出会い”が生んだペーパーディスク 山本眞伸・ソニー(株)ホームエレクトロニクスネットワークカンパニー・ホームエレクトロニクス開発本部オプティカルシステム開発部門部門長
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<Web Usability & Accessibility(第39回)>(社)地上デジタル放送推進協会(D-pa)サイト 公共の福祉増進のためにも、サイトの技術効果を検証すべき(濱田英雄・小川祥子)
●<編集後記「BETWEEN」>

2004年7月号(2004年6月1日発売)
CSデジタル、BSデジタル、さらに地デジの直接受信サービスのトリプル攻勢で、ケーブルテレビ事業は守勢を強いられている。広域連携、サービス連携の現状など、急速に進行しているケーブル事業者の「連携戦略」の成果と課題をまとめた。
・“少年法時代”から脱却しなければ「地デジ」や「役務法」に棄て去られる
・近畿のケーブルテレビ「地デジ再送信」 経営問題に発展(田島 俊)
・松下電器のデジタルケーブル「End to End」ソリューション(片倉達夫・福田 親)
・ケーブル大連携時代の次世代光伝送装置「PrismaIP」(大瀧英士)
・最新デジタルケーブル機器&ソリューション(シンクレイヤ/パイオニア/フジクラ/マスプロ電工)
・CATVとCCTVの相性はメチャメチャいい 「地域安全創出サービス」はキラーコンテンツ(山口正裕)
・杉並区防犯カメラ条例のインパクト(本橋正敏)
・広島県警の防犯専門家がケーブルの有用性を実証(世戸慎吾)
・「安全で安心な街づくり」に貢献する「ジェイコム東京 防犯パトロール隊」(高橋 直)
●特集 NAB2004要諦レポート(上)
全米放送事業者大会「NAB」が4月17日〜22日、ラスベガスで開催された。今年のテーマは「Next Level is Here!(at NAB)」。大きく舵を切った大会となった。入場者は9万7,500人余り。次号にわたってレポートを掲載する。
・目を見張るコーデック技術の進化(佐藤和俊)
・NAB2004にみる米DTVの展望(隈部紀生)
・標準となったHDTV(為ケ谷秀一)
●<連続大論究 「デジタル放送時代のカルチャーモデル」論(第3回)>川勝平太×重延 浩 「力の文明」から「美の文明」へ 「経済のための文化」から「文化のための経済」へ)
●<連載 メディアの学校(第5回)>ゲームの学校(浜野保樹・鈴木 裕・馬場 章)
・「ゲームの学校」資料(日塔 史)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・日本画質学会フル回転 少人数で中身の濃い研究会を実施
・ユビキタスの尖兵集うPervasive 2004(杉沼浩司)
・地上デジタルのデータ放送からネットにリンク 人気コンテンツを揃えた「NHKデータオンライン」開始
・NECがNABで説明「次期放送用グラフィックシステム」
・プレゼン便利グッズ「リモートポインター“ナビゲーター2.4”」 インターリンクから発売
・GW恒例のNHKデジタル放送イベント開催
・NPOでより一層の活動活性化を目指す「JAVCOMの第二世代発進」(八巻 磐)
●お帰りなさい NHK南極プロジェクト(下野戸憲義・佐々木 元)
●<デジタル・パブリッシング提案(第26回)>デジタルコンテンツナビゲーションツール(森田和義)
●日立のハイビジョンプロジェクター Wooo「PJ-TX 100J」遂に完成!(麻倉怜士・アバック)
●<論戦 中期経営計画『NHKビジョン』をどう読む!(番外編)>NHKエンタープライズ21「3か年中期経営計画」を聞く(板谷駿一)
●<地デジ放送電波の問題(第9回)>地デジ電波が引き起こす「ブースター障害」とは何か
■連載
●<今月の表紙>最長10mも離れた場所から利用できる「パ写ワープ」 青木大輔・NTT東日本(株)法人営業本部ブロードバンドビジネス部、金子麻衣・NTT東日本(株)法人営業本部ブロードバンドビジネス部
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<貝谷嘉洋の視点(第15回)>「技術と障害をもつ者」--インターナショナル・カンファレンス報告
●<編集後記「BETWEEN」>

2004年6月号(2004年5月1日発売)
3大広域圏での地上デジタル放送開始から5カ月。全国各地は2006年に始まるが、前倒し局や技術特性を活かした新放送モデルへのチャレンジも登場してきた。最新動向をレポート。
・10月1日ローカル民放全国初「地デジ」開局の北日本放送(横山哲夫)
・「地デジの行政サービス提供」セミナー(岐阜県主催、本誌共催)報告
・東海テレビ放送の地デジ挑戦「マルチ編成とデータ放送」
・果敢に挑む名古屋テレビ放送独自の「番組評価指針」(有川 俊)
●<連続大論究 「デジタル放送時代のカルチャーモデル」論(第2回)>放送局からプロダクションへの利益分配方法を改善すべし(重延 浩・久保雅一)
放送局、プロダクション、スタッフは運命共同体だ。一気にデジタル化が進む中、3者が質の高い仕事を維持していくためには、放送番組の新たな収益分配方法が求められている。
●<連載 メディアの学校(第4回)>ジャーナリズムの学校(浜野保樹・徳山喜雄・音 好宏)
・「ジャーナリズムの学校」資料(久保友香)
・京都精華大学マンガ学科第1期生の進路(牧野圭一))
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・ソニーと松下電器が新製品を発表、市販カーナビ分野の強化を表明
・スカパー!がスター・チャンネルBSのプラットフォーム業務を受託
・地上デジタル放送推進協会が第3回総会を開催
・ソニー新体制、HD技術でB2B市場ソリューション提案
・4月5日開始のコピー制御信号で受信トラブル
・日本デジタル配信のフルデジタル放送サービス、計10局に拡大
・広色域LEDバックライト液晶モニターを三菱が開発
・「京都デジタルアーカイブ研究センター」解散、第3ステージへ
・コンテンツ振興法、全会一致で成立へ
・夢の乗物、セグウェイで世界初の書類送検体験記(後編)(神田敏晶)
・CeBIT報告番外編 ジャーマンの車窓から--ドイツ原色美女図鑑編(杉沼浩司)
●インターネット経由で地上デジタルデータ放送を補完する「NHKデータオンライン」(宮崎経生)
●<デジタル・パブリッシング提案(第25回)>ブロードバンド時代のデジタル・パブリッシング(中所義忠)
●<地デジ放送電波の問題(第8回)>1セグ放送の符号化特許料交渉が一転、放送事業者有利に合意
●<新連載 NHK受信技術、デジタル放送普及へ走る!(第1回)>420万戸以上もあるマンションに対するデジタル放送対応化の啓蒙活動で協力強化
●<論戦 中期経営計画『NHKビジョン』をどう読む!(第2回)>「24時間ニュースチャンネル」について
・メディア・サービス全体でのNHKの位置づけが必要(音 好宏)
・視聴者の利便性は増すと確信する(荻野祥三)
・デジタルメディア時代には意外に本命か(千田利史)
●テレビ朝日の放送設備リース方式のスキーム浮上
●改正「下請法」はコンテンツ業界の悪しき慣例を打破できるか(岸本周平)
●ヤマハがこだわるホームシアターの画づくり(鴨志田憲一郎)
●セイコーエプソンのプロジェクタ事業、価格戦略で堅調な市場づくりを強化(内田健治)
●<業務効率化システム新時代(第5回)>VODで学外へも情報発信する九州大学(姉歯 康)
●CeBIT 2004に登場したモバイル端末用燃料電池
●ネットワークカメラとセキュリティサービスはCATV事業者の有力新事業モデル(世戸慎吾)
●ケーブル業界の名門企業、キャディックスがネクストキャディックスとして再生(上垣 潔・石垣国典・小林美勝)
●さまざまなシーンで活躍・効果が期待されるネットワーク型カメラシステム(荊尾健二)
●シンクレイヤ+となみ衛星通信テレビのFTTH実証実験
●長野県中南信のケーブルテレビ7局がネットワークを構築
●「ハルウララ」生中継配信で威力を発揮した「東四国CATV光連係ネットワーク」(川崎源右衛門)
●CeBIT 2004レポート 凪のPC、構えるHDTV、携帯に急進展の予感(杉沼浩司)
●<The Challengedとメディアサポート(第77回)>加速しはじめた「ユニバーサル社会」形成への動き(中和正彦)
■連載
●<今月の表紙>表面、裏面に異なる映像を同時に表示--結城昭正・三菱電機(株)先端技術総合研究所・TFT-LCD開発プロジェクトグループ・デバイス応用グループマネージャー・工学博士
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<貝谷嘉洋の視点(第15回)>「技術と障害をもつ者」--インターナショナル・カンファレンス報告
●<Web Usability & Accessibility(第38回)>ソフトバンクBBサイト--見栄え優先のデザイン、文字色やALT属性を再考せよ(濱田英雄・小川祥子)
●<編集後記「BETWEEN」>

2004年5月号(2004年4月1日発売)
NHKは1月に平成16〜18年度の事業計画をまとめた『NHKビジョン』を発表。『NHKビジョン』が示すデジタル放送時代の公共放送の在り方などについて、関係者が論じる。
・『NHKビジョン』が示す平成16〜18年度の事業展開
・民放連見解 二元体制の維持を前提に、NHKの分割も含め議論すべき(広瀬道貞)
・スコラ的な議論ではなく、役割論から議論すべきではないか(長谷部恭男)
・受信料制度と新サービス意欲が突きつける課題(神余 心)
●重延テレビマンユニオン会長提唱「デジタル放送時代のカルチャーモデル」論(連続大論究第1回)(重延 浩・竹内宏彰)
「カルチャーモデル」−−類まれな嗅覚を持つテレビマンユニオンの重延浩会長は、デジタル放送時代を迎え、一つの挑発を仕掛けてきた。ゲストとの大論究を連続で重ねていく。
●効率的な資金調達を「みずほ3人衆」直言!--地デジ・地方民放経営問題(香村佐斗史・佐藤勇一・森谷竜太郎)
●広告会社の地デジ普及戦略--電通、博報堂DYメディアパートナーズ(新山迪雄・松下 康・吉川和良・西川 孝)
●連載<メディアの学校(第3回)>マンガの学校(浜野保樹・モンキー・パンチ・小野耕世)
・「マンガの学校」資料(日塔 史)
・デジタル化するマンガ+アニメの制作現場に対応した人材育成(川上陽介)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・日立エンジニアリングの交通流シミュレーションシステム「TRAFFICSS」が実写に近い3DCG動画で都市景観を再現可能に
・テレビ朝日、デジタルマスターに完全移行
・モバイル放送、地下鉄駅構内の受信実験
・衛星・デジタル放送普及に寄与したCATV17社にNHKが感謝状贈呈
・ますます加速するHDD内蔵DVDレコーダー
・燃料電池の工作キットを開発・販売、基礎技術の提供で開発促進に貢献する西野田電工
・前代未聞! 自民党本部で『イノセンス』勉強会
・東大も今秋からプロデューサー、技術開発者の育成に乗り出す
・セルシスがマンガビューア「ComicSurfin」発売
・夢の乗物、セグウェイで世界初の書類送検体験記(前編)(神田敏晶)
●「セリフやナレーションも聞き取りやすい」放送に(沢口真生)
●<デジタル・パブリッシング提案(第24回)>中国進出企業ITビジネスサポート(松田浩行)
●アナ変間近、山陰の受信対策(金田英郎・高橋孝之)
●<地デジ放送電波の問題(第7回)>4月5日から「コピー制御」放送の時代が始まる
●北米では未だ大画面の主役、Projection TV(高相 緑)
●特集「ネット化+ケータイ連動」進化形の映像ADディスプレイ(原 啓起)
・信頼感ある定番媒体化目指し、交通機関、公共施設など活用が拡大する「映像AD」
・第二の頭脳、ケータイへ広告を送り顧客を誘導する「モバイル連動映像AD」
●人の動きで変化する大型映像、ヨコハマに登場!!--NTT「パブリックメディア」(小島慎二・小川克彦・高橋 実・篠原章夫)
●図説 モバイル用燃料電池は今年から来年が天王山!!
●設立10年で「デジタルハリウッド大学院」(杉山知之・浜野保樹・中島信也)
●第2回地域安全環境研究会で反響あったCATV-HSサービスの事例報告(世戸慎吾)
●IP防犯カメラシステム大規模・大量導入時代の構成要素と考慮すべき点(伊藤光裕)
●三重県だから実現したCATVインターネット網利用のホームセキュリティサービス(伊藤秀明・森下 育)
●愛・地球博は21世紀初の「知財博」(中村利雄)
●筑波科学博覧会から20年、愛・地球博はやっぱり超弩級映像博だ(善方 隆)
●<テレヴィジョン“温故知新”--70年前の挿絵が語るテレビ新生活への展望(第2回)>知力を競うスポーツ、アメフット テレビ「観戦」から「参戦」へ
●<The Challengedとメディアサポート(第76回)>e-FORUM 2004/三重県からチャレンジド在宅ワーク実践報告(中和正彦)
■連載
●<今月の表紙>7月末までの実用化実験にトライ中--小川克彦・NTTサイバーコミュニケーション総合研究所主席研究員・工学博士
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<Web Usability & Accessibility(第37回)>国民生活センターサイト--テキスト主体ですっきりした印象も、文字サイズやページの統一感に難(濱田英雄・小川祥子)
●<編集後記「BETWEEN」>

2004年4月号(2004年3月1日発売)
「テレビ×ケータイ」はケータイをテレビ受信だけで終わらせるのではなく、ネントサイトへの連動を紡ぐ提案である。ニッポンならではの「TVライフ維新」が仕掛けられた。
・アナログ放送に対応したケータイ連動サービスを実現するインデックスの「ナビチャン」(山本ひろし)
・データ放送波を使ったケータイ連動双方向サービスを実現するサイバードの「ワンプッシュ」(大森洋三)
・広告主がテレビ×ケータイの双方向型広告に求める「プラスα」の引き出し(真野英明・天野敦夫・吉田洋一・岩井陽介・岸 徹・大森洋三)
・広告会社は「テレビのマス性からケータイのニッチさ」の連続性に期待(二瓶浩一)
●報告「地域安全環境研究会」近畿大会
警察庁による基調報告、ネットワークカメラの設置事例、高度顔認識システムなどについての発表や、CATV局、自治体、一般企業からの参加者による熱心な意見交換が行われた。
・防犯環境設計で犯罪抑止力を創出せよ(首藤祐司)
・地域社会からCATVにもっとも求められているサービス(上田秋次・中川 章)
・テロ防御のための画期的映像解析技術(五島 敦)
・絶対に必要なケーブルインターネットのWebフィルタリングサービス(小澤政弘)
●地方民放の資金調達に新提案--民放デジタル経営課題にズバッと提案
・本誌編集部提案「中継局建設資金プール型スキーム」
・みずほ証券・みずほコーポ銀提案「設備共同運用会社スキーム」(森谷竜太郎・佐藤勇一)
●連載<メディアの学校(第2回)>アニメの学校(浜野保樹・原 恵・山口康男)
・「アニメの学校」資料(藤井光治)
・アニメは杉並区の地場産業!(山田 宏)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・レスキュー支援総合情報システム、視覚障害者の安否確認で試験運用
・トレソーラ、民放3局共同のBB配信イベント2弾
・松下電器が高画質・高感度・機動性が特長の多機能ミニDVカメラレコーダーを3月に発売
・松下、双方向サービス対応の三波共用デジタルSTBを発売
・ナナオが家電参入、液晶テレビ第一弾「FORIS.TV」をネット販売
・シャープが亀山工場の生産第1弾「AQUOS」6機種発売
・富士通日立プラズマディスプレイがe-ALIS方式を新開発、55V型プラズマテレビ“新WOOO”に搭載
・大井競馬場が欲したディスプレイ三菱電機のリアプロジェクションパネル24面を採用
・人の動きを感知する映像AD「みらいチューブ」実験開始
・テレパソロジー研究班第2回班会議開催
・雷害リスク低減コンソーシアムのシンポジウムに400名、ユビキタス社会における雷害対策の新課題を提示
・創立10年を迎えた日本映像事業共同組合
・SKIPシティが3月5日(金)、デジタルシネマでシンポジウム
・デジタルAV、白物販売好調、PCは魅力ある製品望む
・プレゼントのお知らせ
●情報社会の羅針盤としてのNHKの使命と役割(野島直樹)
●<デジタル・パブリッシング提案(第23回)>アナログ、デジタルの良いとこ取り情報提供システム「PNトランジット」(中西元男)
●<地デジ放送電波の問題(第6回)>アナ変最大の難所、対象チャンネル数380以上の九州・有明地域が動き出す
●地デジ放送による行政サービス、岐阜市モニター150世帯で実証実験を開始
●どうする? 平成大合併×地デジ時代のCATV事業(加藤晴彦)
●経営トップの引責辞任に追い込まれたBBC(簑葉信弘)
●今年のJAVCOM「NABツアー」はここが違う!!(勝田正仁・近藤 潔・久松 隆・森澤克彦・金丸幹夫・八巻 磐)
●米国家電ショーCESの“サプライズ”報告(麻倉怜士)
●ネットワークによる知の総合力経営「暗黙知こそが競争力になる」
●エプソンのHTPSパネル技術が世界のプロジェクター市場を支える(麻倉怜士・有賀修二・内山貞住・鹿川祐一)
●まず7社がつながった! 「東四国CATV光連係ネットワーク」運用開始、東京接続も射程距離(大瀧英士)
●新聞社系CATVであることの優位性と課題(鈴木裕之)
●徹底図説 携帯端末用燃料電池は技術課題が山積、各メーカーの対応技術競争が激化
●新連載<テレヴィジョン“温故知新”--70年前の挿絵が語るテレビ新生活への展望(第1回)>薄型テレビを予見した『コドモのテキスト』の先見性
●2年連続でDCAjグランプリ「金の翼賞」受賞、デジタルハリウッドのクリエイター養成パワーが炸裂(真島理一郎・宮谷 大・清水由希・山口義仁)
●3Gケータイ将来論(松本徹三)
●<The Challengedとメディアサポート(第75回)>晴眼者が視覚障害者と点字の世界を共有してみれば--ITと点字が開く新しい世界(金子秀明・竹中ナミ)
■連載
●<今月の表紙>独自の真空技術が切り開くFED--田中 満・双葉電子工業(株)商品開発センター・プロダクトグループ・ユニットリーダー
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<貝谷嘉洋の視点(第14回)>ジョイスティック車という常識(第7回)--フジオートがジョイスティック運転補助装置を新開発
●<Web Usability & Accessibility(第36回)>防衛庁・自衛隊サイト--前回評価からあまり進化せず、基本的な部分にまず配慮すべき(濱田英雄・小川祥子)
●<編集後記「BETWEEN」>
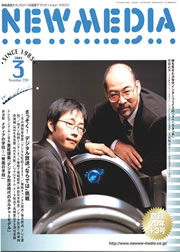
2004年3月号(2004年2月1日発売)
地上デジタル放送が始まった。1つのチャンネルで複数チャンネルを放送する複数チャンネル・まだら編成サービスや、データ放送を活用した地域独自サービスが動き出した。
・「デジタル紅白」最終投票に総数6万9,858票--NHK
・ショッピング番組で好評分を同時再放送--毎日放送(長井展光)
・二つの海外ニュースを同時放送--テレビ愛知(大矢明人)
・番組と連動したインターネット経由で地図情報をテレビに配信--中部日本放送
・「安心・安全」を基本にしたワン・ストップサービス--NHK名古屋放送局(兄部純一)
・ゲーム感覚で心豊かに西国めぐり「西国巡礼倶楽部」--NHK大阪放送局(東原成和)
・リアルタイム・データ伝送方式による高精度GPS測位実験--LSIジャパン・北陸地上デジタル放送推進協議会(田中 隆)
●連載<メディアの学校(第1回)>映画の学校(浜野保樹・掛須秀一・石井聰亙・藤井光治)
知的財産権創出と人材育成を目的に、「メディアの学校」の連載を開始する。第1回は「映画の学校」。映画の作り手たちを養成する学校が日本でもようやく増え出した。
●デジタル放送時代のカルチャーモデル--テレビマンユニオン・重延 浩会長提案
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・ソニー、新規格「Hi-MD」の狙いと課題
・年末番組『踊る大捜査線』で、字幕が消えた!!
・NHKスタジオパークに「デジタル放送体感コーナー」開設
・600m級の放送新タワー、在京6社が本格検討へ
・「国際ユニヴァーサルデザイン協議会」発足に思う(松森果林)
・白もの家電のネット接続、技術仕様を4社共同開発
・日本SGI、スパコン並パフォーマンスのLinuxサーバ発売
・松下電器、04年度経営方針中期計画「躍進21計画」発表
・セミナー開催予告「e-Learningのコンテンツビジネスの新たな拡がり」
・大阪・東京で本格的ケーブルショウ
●地デジスタート「送信技術者にとっても、楽しい時代が訪れた」(砂川 清)
●<デジタル・パブリッシング提案(第22回)>情報の集積基地「DATA CITY構想」(山口高弘)
●ファンド形式による「地デジ放送設備共同運用会社」の設立を提案(森谷竜太郎
●提起 デジタル放送の「民放経営ビジョン」を可及的速やかに
●メディア融合時代の放送局の世界的課題「経営強化と多様性の確保」(隈部紀生)
●ケーブルラボ運用仕様の地デジ対応機器勢揃い、春からSTB投入で地デジ再送信に拍車(佐藤和俊)
●ヘッドエンドからSTBまで、川上から川下まで出揃った(大河内勝彦)
●「スターキャットは大丈夫」(奥村見治)
●ネット音楽のキープレイヤーを探せ
●<日テレ視聴率買収事件を考える(続)>「『率』じゃダメだから『質』で」という短絡思考では問題は解決しない!!(藤平芳紀)
●<地デジ放送電波の問題(第5回)>同時刻に同じ番組を楽しめるのは「テレビ中継回線網」のお蔭
・地デジ対応のPC受信機が登場
●「県紙空白県」滋賀県で「(株)みんなで作る新聞社」が2005年春新県紙を創刊(築地達郎)
●全国縦断14回開催「プロバイダ責任制限法研究会」、ケーブル局延べ400局参加し、成功裏に終了
●ネットワークカメラ報告 2004年は百数十カ所に防犯灯設置予定(京地利行)
●2004年は脅威のウイルス、フラッシュ(閃光)型出現か(森 豊)
●NEC、日立製作所、東芝が独自の方式で技術課題克服に鎬を削る、携帯端末用燃料電池
●<The Challengedとメディアサポート(第74回)>新資格「福祉情報技術コーディネータ」はチャレンジドのIT環境を変えるか(中和正彦)
●ISO14001取得のNTTドコモ九州で活躍、三菱電機「ペーパー会議システム」(西坂輝一・田代義浩・河原敏成)
●シェア9割以上の画期的アニメ制作支援ツール、セルシスの「RETAS!」シリーズ(浜野保樹・川上陽介・野崎慎也)
■連載
●<今月の表紙>未来のインターフェイスは直感操作--齋藤武邦・トヨタ自動車(株)デザイン本部グローバルデザイン統括部主担当員、土屋裕志・(株)デンソー 技術管理部デザイン室
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<Web Usability & Accessibility(第35回)>社会保険庁サイト--シンプルなデザインには好感、ナビゲーションはさらなる工夫を(濱田英雄・小川祥子)
●<編集後記「BETWEEN」>

2004年2月号(2004年1月1日発売)
東名阪で一斉にスタートした地上デジタル放送。歴史を刻む「12月1日」という一日をNHK会長の海老沢勝二氏に密着取材した。メディア史にとって、濃密な24時間であった。
・歴史的な一日を海老沢勝二NHK会長に密着取材
・地デジは電子政府に貢献せよ!(梶原 拓)
・地デジを活用した行政サービス提供についての実証実験概要(坂口裕信)
・BSデジタル大賞グランプリは『世界遺産』と『MLB』
・これがアナ変作業だ 前線基地から最新レポート
● ケーブル事業者必読! ケーブルセキュリティのガイドライン(中村正孝・竹中俊二・白須洋史)
ケーブルテレビ連盟はケーブルセキュリティのガイドラインを作成、2004年1月に発表する。その全文(案)を掲載する。また、ガイドラインの内容、今後の予定について伺った。
● チャレンジド(障害者)がITテレワーク就労--NTTネオメイト「デジタル地図バーチャルファクトリ」(西村憲一・潮谷義子・竹中ナミ・平野明子・杉原輝美・神崎淳一・勝岡千佳子・宮本圭子・中和正彦)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・電通が本社ビルで地デジスタートのビル絵文字
・デジタル放送時代の新テレビCM 視聴者の誕生日にあわせてメッセージ
・軍事用技術が歯科診療に--インテリジェント画像診療装置の開発
・遂に来た?! ホームシアタープロジェクター好景気時代(鈴木新次郎)
・「第18回デジタルコンテンツグランプリ」決定、経済産業大臣賞に『東京ゴッドファーザーズ』と「RETAS! シリーズ」
・NEC、Windows Media配信専用OS搭載のストリーミング専用サーバーを業界初製品化
・日本画質学会の村瀬孝矢副会長が「放送技術80年のドラマ」を共著
・日本テクトロニクス、新社長就任・本社移転を発表
●「教育フェア」と「日本賞」--放送は技術を活用した文化を体現する教育番組(原田隆司)
●<デジタル・パブリッシング提案(第21回)>「rosetteStar Proof」を利用したCTPサービスのビジネス展開(金子栄一)
●<編集部提案「地デジ中継局建設プール型スキーム」への意見・反響(第3回)>
・募集「地元力を生かしたデジタル化投資支援策」提案
・「地域ごとの特例措置」を考えてはどうか(音 好宏)
・匿名座談会「これがローカル局経営幹部の本音だ」
●3大都市圏ケーブルでの地デジ視聴可能世帯は710万(茅野徹男・前川秀樹)
●さよなら「Western Show」(原 隆司)
●<地デジ放送電波の問題(第4回)>地デジのコピー制御、あなたの録画機器ではこうなる
●ホームシアター2003開催、「こんなイベントを待っていた!」(為ケ谷秀一・秋山雅和・麻倉怜士・村瀬孝矢)
●日本初「ビジネス著作権検定」をサーティファイが創設
●地域安全環境研究会スタート、2004年のテーマは「治安」ではなく「地安」(亀田正博)
●進化するネットワーク社会! サイバースペース破壊から物理的破壊への予感(井上陽一)
●2007年度までに300万加入を目指す、IP電話・ネット接続・テレビ放送の「KDDI光プラス」
●NHKアーカイブスの構築技術の点検と運用実績(大井康祐・小森隆夫・桝井修平・菅原 仁・竹松 昇)
●<The Challengedとメディアサポート(第73回)>福島 智 vs 竹中ナミ(第2回)--「日本自体がチャレンジド」の時代、すべての人が試されている
●日本画質学会報告、フルデジタル時代における画質の「同一性保持」は可能か(峯川 卓・瓜生 修)
■連載
●<今月の表紙>目指せ、皮膚感覚を持つ等身大ロボット--桜井貴康・東京大学国際・産学共同研究センター教授・工学博士、染谷隆夫・東京大学工学系研究科量子相エレクトロニクス研究センター助教授・博士(工学)
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<Web Usability & Accessibility(第34回)>日本郵政公社サイト--サイトデザインに難あり、さらなる構造改革が必要か?(濱田英雄・小川祥子)
●<貝谷嘉洋の視点(第13回)>ジョイスティック車という常識(第6回)
●<編集後記「BETWEEN」>
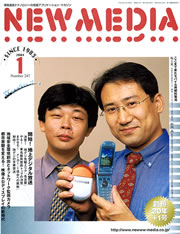
2004年1月号(2003年12月1日発売)
12月1日午前11時、アナログの最大で最後のメディアであった地上波テレビ放送がデジタル化へ動き出す。地上デジタル放送の移行には壁があるが、歴史の幕は上がったのである。
・決意! 地デジ先駆エリア「名古屋」
・NEBA会長、「名古屋が地上デジタルの起爆剤になる」宣言(岡嶋昇一)
・NHK名古屋放送局長、「地上デジタル放送普及の先頭に立つ!」(川上 淳)
・やる! 東名阪民放局トップの決意--日本テレビ/テレビ朝日/東京放送/テレビ東京/フジテレビ/MXTV/東海テレビ/中京テレビ/中部日本放送/名古屋テレビ/テレビ愛知/毎日放送/朝日放送/テレビ大阪(間部耕苹・広瀬道貞・井上 弘・菅谷定彦・村上光一・後藤 亘・石黒大山・徳光彰二・夏目和良・桑島久男・佐藤富男・山本雅弘・西村嘉郎・富澤秀機)
・やる! D-paトップの決意(芳賀 讓)
・まかせろ! メーカー「1億台以上への挑戦」--三洋電機/シャープ/ソニー/日本アンテナ/日本ビクター/パイオニア/日立国際電気/日立製作所/マスプロ電工/松下電器(前田 健・寺川雅嗣・浪越善一郎・伊藤隆継・藤崎陽一・五月女 勝・秋山孝男・井本義之・端山佳誠・藤田正明・田口利三)
・期待! 地デジの字幕放送
・デジタル放送で字幕放送はユニバーサルなサービスになる(清原慶子)
・字幕放送ユーザーから
・「いつでも、どこでも、誰にでも、ちゃんとわかる」、こんな状況が当たり前になるといい(小椋知子)
・聴覚に障害のある私たちは、地上デジタル放送のここに期待する!(小川光彦)
・字幕放送最前線レポート--NHK、民放キー5局の取り組みの現状と地デジによる新たな展望
・字幕放送を双方向のトリガーにする「TVeCM」提案(田中 隆)
・メーカー提案
・ナレーション音声をそのまま使い、放送用字幕制作の効率アップ--ダイキン工業
・増大する字幕付与ニーズに対応、“使いやすさ”と“分業・分散”を実現--IBE
・生放送番組に字幕をリアルタイムに付けるシステムをNHKと共同開発--松下電器
● 地域安全環境創出とネットワーク監視カメラ
本誌はニューメディアを人間生活の向上のために役立てる方策を精力的にお伝えしてきた。しかし、世の中、性善説だけで回ってはいない。日本は犯罪社会に変貌してしまった。
・「石原知事と議論する会」防犯首都を目指して東京の治安を再生
・ネットワーク監視カメラの最先端技術とその必要性(宮城直樹)
・証明された犯罪抑止力と解決力(亀田正博)
・2004年度は「地域安全環境創出とIT」で研究会展開(世戸慎吾)
● 映像ADディスプレイの新時代
本誌はニューメディアを人間生活の向上のために役立てる方策を精力的にお伝えしてきた。しかし、世の中、性善説だけで回ってはいない。日本は犯罪社会に変貌してしまった。
・ここまで来た! 東京都の屋外広告規制緩和(原 啓起)
・パリ発「ストリートファニチャー」が日本を席捲する日(大山 昇・原 啓起)
・世界一早く共同電を発信する「汐留メディアタワー」(原 啓起)
・大型LEDディスプレイのリーダー企業、赤見電機
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・日本ケーブルテレビ連盟東海支部の地デジ対応(奥村見治)
・緊急メッセージ 日テレ視聴率買収事件を考える
・広告主の立場から(大竹和博)
・視聴リサーチのプロから(藤平芳紀)
・オプティキャストの役務法ビジネス戦略(仁藤雅夫)
・第5回デジタルアーカイブ・アウォード受賞者決まる
・デジタルコンテンツの中国進出は上海でなく北京にオフィスを(古株 均)
●<デジタル・パブリッシング提案(第20回)>XMLをデータフォーマットとして採用することで広がるビジネスの可能性(植野 博)
●<地デジ放送電波の問題(第3回)>地上デジタル放送における「B-CASの採用」とは(佐藤和俊)
●「10億7,000万色の表現力」をエプソンdreamioで満喫(麻倉怜士・村瀬孝矢・宮下 聖・河崎麦雄)
●「故宮文化資産デジタル化応用研究所」開所
●<上智大・音先生が地方民放トップに聞く(第2回)>関西テレビ、中部日本放送、名古屋テレビの地デジ戦略(出馬迪男・夏目和良・桑島久男)
●<業務効率化システム新時代(第4回)>最先端のVODで「授業メディア空間」を構築した名古屋大学(姉歯 康)
●<The Challengedとメディアサポート(第72回)>福島 智 vs 竹中ナミ(第1回)--コミュニケーション技術が道を拓いた
■連載
●<今月の表紙>坂上英一・(株)東芝 研究開発センター機械・システムラボラトリー研究主務、山内 尚・(株)東芝 研究開発センター給電材料・デバイスラボラトリー研究主務・工学博士--「希釈循環システム」方式を採用した東芝
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<貝谷嘉洋の視点(第12回)>ジョイスティック車という常識(第5回)
●<Web Accessibility(第33回)>在京テレビ局「地上デジタル放送紹介」サイト--万人に情報が伝わるような配慮を(濱田英雄)
●<編集後記「BETWEEN」>
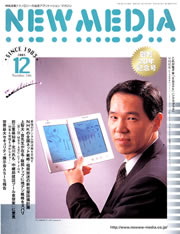
2003年12月号(2003年11月1日発売)
これまで50年をかけて作り上げてきたアナログ放送のための放送局から、地上デジタル放送のための放送局への変身をいかに遂げるか。各社の事例と提案を掲載する。
・2005年3月放送開始の福岡放送新社屋にみる「最強」のコンテンツ制作工場づくり
・TS伝送方式の採用で回線の低コスト化と地域局の設備負担を軽減するNHK
・IBC2003、ユーロ各局で動き出してきたHD制作
・池上通信機、ソニー、松下電器の「わが社のシステム提案」
●世界最大の総合セキュリティー展示&セミナー「ASIS International 2003」報告(桑山良一)
世界は不安に満ちている。9・11テロ以来、世界はおびえている。日本も例外ではない。こんな時代、活況を呈しているのがセキュリティー産業だ。ASISの概略を報告する。
●<上智大・音先生が地方民放トップに聞く(第1回)>--毎日放送、朝日放送、中京テレビ、東海テレビ放送の地デジ戦略(音 好宏)
●<編集部提案「地デジ中継局建設プール型スキーム」への意見・反響(第2回)>放送業界もデジタル化の「マニフェスト」を出すべきだ(北川正恭)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・北米大停電は電力自由化反対論の論拠となり得るのか
・麻倉怜士が見た! 今年の「CEATEC」
・地デジ放送元年、テレビ主役も待たれるケータイ受信
・松下がネット家電戦略強化表明、テーマは「easy networking ideas」
・デジタルラジオをPCなどで聴取可能に、3セグ放送対応受信機開発進む
・マイクロソフトがお茶の間に進出、リモコン操作のPC登場
・こんなデザインのホームシアタープロジェクターが東芝から出た!
・日本ビクターが地デジ対応ハイビジョンテレビなど、8モデル発表
・不適当なADSL広告表示などの自主基準案(桑子博行)
●日本中の約1億台以上のテレビ受信をデジタル放送に対応させる(金田英郎)
●<デジタル・パブリッシング提案(第19回)>顧客へ向けた「DTPターボサーバー+ec-Being」によるWebサービス提案(星名康雄)
●業務効率化システム新時代(第3回)>MPEG-2アーカイブシステムで放送業務効率化を目指す北海道放送(姉歯 康
●パイオニアのRemoteCast BB、広告媒体の電子メディア化を強力サポート
●ネットワンシステムズが最先端ソリューションを提示
●テレビ放送50周年記念フォーラム(海老沢勝二・佐藤和俊)
●<地デジ放送電波の問題(第2回)>「アナ変」の天王山、20万世帯対象の多摩エリアが作業開始
●新聞社系CATV連携ネット会議(井上 仁)
●日商エレクトロニクス「BBAS」戦略の中核製品、TORRENT OSA(榎本瑞樹)
●The Challengedとメディアサポート(第71回)>チャレンジド・テレワーク本格普及へのモデルとなるか(西村憲一・竹中ナミ)
●日立プラズマテレビ&液晶テレビ「見るWOOO」を麻倉怜士が体験
■連載
●<今月の表紙>早川佳宏・松下電器産業(株)パナソニックシステムソリューションズ社eソリューション本部eシステム開発グループ・グループマネージャー--記憶型液晶の採用で省エネの読書用端末
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<貝谷嘉洋の視点(第11回)>ジョイスティック車という常識(第4回)
●<Web Usability & Accessibility(第32回)>「安部晋三」サイト--人柄や信頼感をサイトに反映しているかは「?」(濱田英雄・石田直子)
●<編集後記「BETWEEN」>>

2003年11月号(2003年10月1日発売)
「10月改編」は、12月1日に始まる地上デジタル放送にとって初めての番組編成でもある。民放キー各局の編成担当に「地上デジタル番組編成方針」について聞いた。
・日本テレビ/TBS/フジテレビ/テレビ朝日/テレビ東京
●台頭するデジタル@ネット家電「新“価”論」
ブロードバンド網の急速な普及に加え、地デジ開始が目前に迫り、「デジタル@ネット家電」の動向が注目を集めている。その付加価値戦略の意義をさまざまな視点から検分。
・経産省の情報家電普及戦略
・オープンOSの責任所在
・設計ガイドライン策定
・「家電王」が語る必須条件
・東芝「FEMINITY」シリーズ
・アナログ停波の広報が重要
・デジタル家電フォーラム2003
・ソニーの新家電GUI「エアタクト」
・薄型テレビ続々登場
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・地デジ普及のスローガン制定
・日本初、雷害リスクマネジメントの本格的ビジネス書(妹尾堅一郎)
・Webクリエーション・アウォード贈賞
・電子書籍ビジネスコンソーシアム設立
・ネイビス、監視カメラ施行作業を簡便に
・NECの18GHz帯高速無線アクセスシステム
・日本テレパソロジー研究会に韓国ゲストも
・ハイビジョンを超えるJVCのD-ILA新デバイス
・エプソンの新ホームプロジェクター
・スクリーンのオーエス、50周年イベント
・松下電器のD-snap新製品
・IPマルチキャスト監視カメラネットワークで協業
・NTT Comのインターネット新検定資格
●デジタルテレビ新時代は生放送、ハイビジョン、データ放送で生活により密着した情報を提供(出田幸彦)
●<デジタル・パブリッシング提案(第18回)>どうなる! ドキュメント制作にとってのXML(平田憲行)
●編集部提案「地デジ中継局建設プール型スキーム」意見・反響の第一弾
●<地デジ放送電波の問題(第1回)>実際に発射してみないと問題はわからない
●<業務効率化のカギを握るテレビ会議システム新時代(第2回)>コジマ全250店舗を結び情報戦に備え万全、コストも大幅削減(姉歯 康)
●画質のオニ・麻倉怜士が三洋電機のプラズマテレビ「VIZON」を画質体験
●<The Challengedとメディアサポート(第70回)>千葉からユニバーサルの風を!(中和正彦)
●日本最強のCATVブランドを目指すTDN
●情報BOX利用で四国CATV大連係の可能性
●次世代光伝送装置「PrismaIP」が東四国7局を結ぶ(井上良孝)
●「役務法」を戦略的に捉える愛媛CATVの事業展開(神山充雅)
●高画質モニタリング・長時間記録は時代の要請
●カーネギーメロン大日本校、阪大などの情報セキュリティ新講座(塩路忠彦)
●「低ビットレートでもきれい」と定評、JVCのMPEG-4ネットワークコーデック
●三大都市再開発で注目度アップ! 映像ADディスプレイ
・丸ビル・六本木ヒルズ・汐留シオサイトの映像ディスプレイ戦略(渡辺晴俊)
・着実に進化してきた「店舗立地型」と「交通広告型」(原 啓起)
・交通広告の電子メディア化をリードするアイティ・ニュースの戦略(唐川 敬)
●政府主導で「100館デジタルシネマ計画」を進める中国(坂井常雄)
■連載
●<今月の表紙>竹中ナミ・社会福祉法人プロップステーション理事長、楠田喜宏・IT車椅子を推進する会代表--GPSと道路センサー情報による地図づくりを提案
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<Web Usability & Accessibility(第31回)>「IPAセキュリティセンター」サイト--ユーザーに理解できる情報提供を(濱田英雄・石田直子)
●<貝谷嘉洋の視点(第10回)>ジョイスティック車という常識(第3回)
●<編集後記「BETWEEN」>

2003年10月号(2003年9月1日発売)
今年7月、NHK会長に3選、「デジタルテレビ新時代」ともいえる重要な時期に公共放送の舵取り役を三たび担うことになった海老沢勝二氏に、抱負や課題などをうかがった。
●本誌編集部提案「地上デジタル中継局建設資金プール型スキーム」
地上デジタル化の最難関である「地形で左右される中継局建設コスト問題」に対し、公平な資金負担を実現する「中継局建設資金プール型スキーム」を提案する。
●受講者10万人、世界有数、日本最大の大学「放送大学」(麻生 誠・岩永雅也)
2003年10月から「放送大学学園法」が改正・施行され、放送大学は自主裁量権が拡大する。国公立大学の独立法人化に連動して「攻め」に出る新学園体制の展望を聞いた。
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・地上デジタル放送のCM画角・画質デモ
・受信普及の重責を担う(社)地上デジタル放送推進協会(D-PA)設立
・日本ケーブルラボが事務所移転、石橋運営委員長が地デジ対応の決意表明
・朋栄がフィルムストリームカメラ「VIPER」の発売開始
・松下電器、212時間録画可能なHDD内蔵型を発売、DVDビデオレコーダーの上位機種を拡充
・モバイルキャスト、テレマティクスサービスで新提案
・トヨタ自動車、「G-BOOK」の対応車種とサービスを拡大、年内に50車種で利用可能に
・ペンタックス,レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ「PENTAX *istD」発売
・人工内耳と無線LAN(宮下あけみ)
・アビッドジャパンが新製品「Nitris(ナイトリス)」発表会
・中小企業テクノフェア2003、東京・大阪で開催
・DXアンテナが創業50周年記念キャンペーン実施
・ロボットベンチャー企業の入居施設「THINK未来工房」開設
●<デジタル・パブリッシング提案(第17回)>クロスメディア企画制作(和泉広彦)
●地上デジタル放送試験電波を発射
●日本初の地上デジタルラジオ放送、10月10日実用化試験放送開始!(東海林 通)
●「買ってよかった! BSデジタル」キャンペーンの成果と展開(生井俊重)
●新サービス「モバイル放送」、ケータイなどで受信、2004年上旬開始へ(溝口哲也)
●レオパレス21のBBネット配信サービス「LEO-NET」で快走するVOD
●<業務効率化のカギを握るテレビ会議システム新時代(第1回)>移動時間の削減と技術開発のリサーチ活動を同時に実現--シャープの事例(姉歯 康)
●救速発信、ITで人命を救え!!--内閣府防災担当官に聞く「組織横断的な情報共有は、効果的な防災対策の基盤になる」
・災害時救助支援への新提案、レスキューロボ出動待機中(松野文俊)
・耐災害性の高い衛星監視システム、ネイビス「さおみ〜る」
●「役務法」組第1号、BBケーブルの課題(橋本太郎)
●100万世帯接続可能な首都圏最強のケーブルアライアンス、TDNの出資会社が12社に増加(淀 敬)
●過半数の道府県が「地域デジタルアーカイブ協議会」に結集(清水宏一)
●六本木ヒルズは「デジタルポスター」のテーマパークだ(菅原淳之)
●カーネギーメロン大が神戸にやってくる(塩路忠彦)
●ノーテルネットワークスのIPマルチキャスト「監視システム」(平松敏之・伊吹仁志・亀田正博)
●安全・安心のマチづくりのためにケーブルテレビの役割は大きい--テレビ岸和田(片山智信・北野洋一・阪口勇一・亀田正博・楠本雅洋)
●ネットワンシステムズの日本最高のIP技術者教育ソリューション「ネットワークアカデミー」(田中 稔・秋丸秀信・北川順市・加藤晴彦・齋藤征雄・中川一也・沖 千里・石川 忠)
●NECビューテクノロジーとDP社の最強2Kフルスペック新DLPシネマプロジェクタ「cS25」(麻倉怜士・押切隆世・井口 洋・渡辺政則・Mike Blackburn)
●<The Challengedとメディアサポート(第69回)>日本のチャレンジドももっと大学へ!〜IT時代の高等教育就学支援策(広瀬洋子・竹中ナミ)
■連載
●<今月の表紙>伊藤順司・独立行政法人産業技術総合研究所エレクトロニクス研究部門長・理学博士、外岡和彦・独立行政法人産業技術総合研究所エレクトロニクス研究部門主任研究員・学術博士--“透明”にこだわった太陽電池
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<Web Usability & Accessibility(第30回)>内閣府「防災情報のページ」--必要性の高いサイトだからこそ、より高い意識をもって運営を(濱田英雄・石田直子)
●<貝谷嘉洋の視点(第9回)>ジョイスティック車という常識(第2回)
●<編集後記「BETWEEN」>
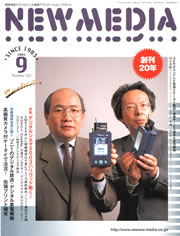
2003年9月号(2003年8月1日発売)
ジョージ・ルーカス監督が火を付けたデジタルシネマの現状はどうか。ハリウッドはどう動いているのか。アメリカの規格動向から、日本で進む事業への挑戦動向をまとめた。
・デジタルシネマ大国ニッポンを目指せ!!
・アメリカ最新動向「気がつけば“深く”“静か”に前進」(蓮 憶人)
・ティ・ジョイはデジタルシネマの第2フェーズを確実に歩んでいる(井口 洋)
・NHKのハイビジョン・プログレッシブ制作(飛地 茂)
・ソニー「HDCAM-SR」採用の24P新製品群登場(倉田 梓・岡田修司・岩崎研一・亀山和生)
・「コダックデジタルシネマシステム」欧州で販売開始(久保添倫成)
・地域における非常設型上映会の振興を目指す(須藤智明)
・マイクロソフト「WM9」でシネマ公開の裾野が広がる(御代茂樹・河野万邦)
・「神の視点への挑戦」ブロードバンドシアターの取り組み(滝内 泉)
●安藤国威・ソニー社長特別インタビュー「ソニーがリーダーシップをとってAVとITの相互接続性を実現させる」
世界の代表的な家電・コンピュータメーカーなどで構成された団体、DHWGが設立された。リーダーシップをとっているソニーのデジタル放送・デジタル家電戦略を聞いた。
●高画質カメラ付きケータイで活況!、“写真維新”街頭プリント端末の新事情
デジタル画像の出力手段として、街頭設置型のセルフプリント端末が注目を集めている。業界関係者へのレポートとともに、メーカー、ラボ各社の機器・サービスを紹介する。
・遊ぶか、残すか、ケータイ写真の活用は?(曽崎重之)
・メーカー、ラボ各社の機器・サービス--オムロン/55ステーション/富士写真フイルム/三菱電機/NECモバイリング/ソニーマーケティング
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・地デジ「アナ変作業」の今後を占う八王子エリアで7割の「申請」返信率
・Web広告研究会がCMのインターネット配信で小冊子発行
・障害者高等教育支援の第3回「交流・研究・研修」会開催
・ベンチャーラボグループが専門家集団、技術評価やVC業務を活かしたMOT開始
・全商連が41回総会、福田会長体制6期目
・日本初のオンライン・メンタルヘルスサービス「MTOP」、新会社設立へ
・三菱ショールーム&カフェ「DCROSS」オープン
・デジタルde<みんなのムービー>に第一通信社が新作で参加
・松下電器、周辺機器との接続を中心に考えた業務用PDP、3連装ファンクションスロットを搭載
・NEC、地デジ放送受信機能を想定した携帯電話試作機を発表
・日本SGIと電気通信大学、ヘビ型レスキューロボットを開発
・ITSの進化で車社会の新たな飛躍
・2003年ネット人口予測は6,000万超、『インターネット白書2003』発売
●「デジタルテレビ新時代」のNHKの広報活動(三浦 元)
●<デジタル・パブリッシング提案(第16回)>データ資産を活用し、意思決定をより早く的確に行うビジネス・インテリジェンス(星野雅博)
●各分野で高い評価を受ける三洋液晶プロジェクター活用事例--札幌シネマフロンティア/大島アイランドホテル長崎/五藤光学研究所(佐藤信一・井川 透・山路善也・吉田健治・黒沼佳一)
●infoComm 2003レポート(稲葉視朗)
●「ユビキタス放送」の展望とその予兆(藤原 洋)
●香川県を基点に「東四国CATV光連係ネットワーク」12月スタート
●アメリカのメディア所有規制緩和と日本の放送(隈部紀生)
●LRTは本当に不採算事業なのか?
●日立エンジニアリングが交通流シミュレーションシステムの最新版を発売(大沼康明)
●商品170万点を手中にできる「ケータイ版楽天市場(牛山典子)
●<連載レポート 燃料電池実用化の最新事情(第2回)>独自のシステム開発路線で他社に先行する東芝のモバイル電子機器用DMFC
●インターネットから整いはじめたCMの権利処理と、対応する業界体制(峯川 卓)
●<The Challengedとメディアサポート(第68回)>「第9回チャレンジド・ジャパン・フォーラム2003国際会議inちば」米国からのユニバーサルな風(中和正彦)
●中核都市・松山の将来展望を踏まえた5Gbpsのリングネットワーク構築(中村時広・神山充雅)
●松山は「ユビキタス仕事場」、愛媛CATVが松山市と一体となって産業振興(竹村奉文・沖廣善久・大野栄一・神山充雅・白石成人・柴田祐輔・平松敏之・亀田正博・野尻康弘)
●「Under500MHz施設」のバージョンアップなくして「地デジ」なし--東京ケーブルビジョン編(石黒 公・紙谷行文・榊原盛吉・飯島真人・石川 忠・木村英治・奥山清雄)
●エプソン「EMP-7850」「EMP-7800」この明るさ、このビデオ高画質、この使いやすさ
■連載
●<今月の表紙>国分秀樹・NHK放送技術研究所 マルチメディアサービス主任研究員、小池 淳・(株)KDDI研究所 画像通信グループ・グループリーダー・博士(情報学)--“放送・通信連携”の新サービス検証に活用
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<Web Usability & Accessibility(第29回)>東京電力サイト--Webでの情報開示によって見透かされる企業の危機管理能力(濱田英雄・石田直子)
●<編集後記「BETWEEN」>
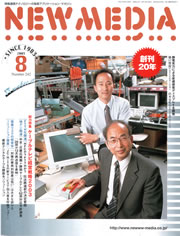
2003年8月号(2003年7月1日発売)
ケーブルテレビ事業は今、膨張するADSLやNTT・電力系のFTTH攻勢にさらされている。そして急務は、地上デジタル放送への対応。過去の公式は通用しない。デジタル時代の「成長継続」のためには、何を選択すべきなのか。多角的な視点で特集する。
・ケーブルテレビ事業振興の総務省「国策」(小暮純也)
・HFC vs FTTH伝送路“線”争論(奥村見治)
・世界と日本のFTTHビジネスモデル(小林直行)
・手応え上々、上越FTTH実証実験
・ケーブルテレビ各社の地上デジタル対応方針調査「26局が12月再送信表明」
・業界関係者必読! 基本解説「地上デジタル放送とケーブルテレビ対応」(角 弘樹)
・ケーブルテレビ経営を直撃する「地上デジタル再送信」問題
・雷害リスクの経営学「雷害対策の費用対効果をどう考えるか?」
・ケーブル業界の切り札になることを期待したいVOD(猪股英紀)
・SCTEショー報告「米国はデータ伝送の高速化に夢中になった」(山口正裕)
・デジタル・ケーブル時代の映像コンテンツ流通革新JC-HITS(藪下憲一)
・ZTVが現在の10倍規模のデータセンター構築へ(吉田 要・川村芳生・寺家通浩・平松敏之・及川満広・亀田正博)
・三重県行政WANとCATV(永田利康・瀧上昭憲・和田義美・保井伸之・矢田雅近・岸本 明・川村芳生・及川満広・亀田正博)
・都市電障問題の解決なくしてデジタル放送なし(上田秋次・中川 章・石川 忠・塩見 力・奥山清雄・伴 泰次)
・世界初の広域ADSLケーブルテレビ、BBケーブルTV
・最新デジタルケーブル機器&ソリューション--伊藤忠ケーブルシステム/NEC/NECマグナスコミュニケーションズ/NTTファシリティーズ/音羽電機工業/シンクレイヤ/パイオニア/フジクラ/マスプロ電工/松下電器産業
●地上デジタル直前! BSデジタル?!
地上デジタル放送がスタートする12月に、BSデジタル放送は開始3周年を迎える。BSデジタル放送局8社に登場してもらい、「地上デジタル開始とBSデジタル」を語ってもらった。
・BS民放5社座談会「今だからこそBSデジタル」と訴えたい!(石塚浩人・上霜亮太・植村祐嗣・磯見敦彦・遠藤登久雄)
・NHK理事に聞く「BSと地上波の共通のキーワード『デジタル』が動き始めた」(和崎信哉)
・主協・電波委員長に聞く「広告主にとって今後3年のBSデジタル経験の違いが“決定的な差”となる」(大竹和博)
・WOWOW新社長に聞く「ホームシアター視聴の広がりはWOWOWのチャンス」(廣瀬敏雄)
・スター・チャンネル経営戦略担当者に聞く「ブランドを打ち立てる絶好のチャンス到来」(デビッド・シン)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・「地上デジタル推進全国会議」5月23日発足
・デジタルテレビは「白モノの発想」で--松下電器
・DMDの映像信頼性を実証すべく競合技術と比較実験を実施--日本TI
・日本初のWindows搭載液晶テレビ、病院・医療機関専用端末「MediClient」
・音声、データ、映像を融合したブロードバンド事業--NECマグナスコミュニケーションズ
・フィルムからデジタルシネマまで基本が学べるセミナー開催--日本映画テレビ技術協会
・デジタルシネマ・マスタリング・フォーマット決まる!?
・QuickTimeの3GPP規格対応でケータイ動画は第2ラウンドに突入?(姉歯 康)
●NHK技研公開、今年の目玉はハイビジョンの移動体受信デモ
●日本初、ビジネススクール主催「デジタル放送のあり方」提言セミナー(佐藤 勉)
●<デジタル・パブリッシング提案(第15回)>モノなら「なんでも追跡システム」(酒田義矢)
●キリンのネットを活用したデジタルキャンペーン「ネットでFIRE」の成果(松枝勇治)
●日枝 久・民放連新会長に聞く「地上デジタルによってテレビを中心に放送と通信が『アコモデーション』する」
●成功のために地上デジタル放送計画を大胆に見直せ(平井卓也)
・平井卓也・衆議院議員の提言「地上波デジタルを再考せよ」
●民間企業のMOTプログラムには、大学院にないメリットがある
●<The Challengedとメディアサポート(第67回)>「福祉就労の場を本当の働く場に!」 神戸で産官民連携のプロジェクトが始動(中和正彦)
●青学が三菱電機の「リアプロジェクションパネル」34面を採用(濱中正邦・麻倉怜士・寺本浩平)
■連載
●<今月の表紙>樋口俊郎・東京大学教授・工学博士、山本晃生・東京大学講師・博士(工学)--ミクロン単位でザラツキ感を再現
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<Web Usability & Accessibility(第27回)>(第28回)>「日本のCATV」サイト--HP作成ソフトでの安易なWebサイトには問題点多し(濱田英雄・石田直子)
●<編集後記「BETWEEN」>
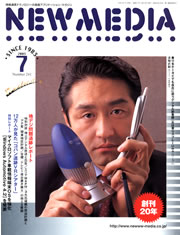
2003年7月号(2003年6月1日発売)
4月18日、総務省は関東・中京・近畿三大広域圏の16社に対して、地上デジタルテレビ放送の予備免許を交付した。12月1日から始まる地上デジタル放送の諸問題を追跡する。
・Web広告のリーダーと電通テレビ局部長が説く「12月放送開始を前に、今必要なこと」(真野英明・田中 剛)
・関東・中京・近畿三大広域圏の放送エリア計画
・地上アナログ放送の停止までに1億台の普及、果たして「目標」をクリアできるのか
・アメリカDTV計画「2006年アナログ停波」、パウエルFCC委員長の「本音」と「次の一手」(隈部紀生)
●「神秘の王朝−マヤ文明展」において「コパン遺跡VRシアター」を展開--「スケーラブル・バーチャル・リアリティー・コンテンツ生成・共有技術の研究開発(SVR)」プロジェクト(廣瀬通孝・田中正樹)
放送・通信機構(TAO)のSVRプロジェクトは、東京・国立科学博物館で開催された「神秘の王朝−マヤ文明展」に、世界最大規模のVRシアターを設置し、研究成果を発表した。
●マイクロソフトが車載情報端末OSを強化--Windows Automotive 4.2を発表
次世代カーライフをターゲットとする野心あふれるマイクロソフト・テレマティクスのプロジェクトが加速。強化された車載情報端末向けOS、Windows Automotive 4.2が登場した。
・マイクロソフト「テレマティクス」事業への確信を聞く(ボブ・マッケンジー・平野元幹)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・Windows Media9でライブ観賞を 5.1Ch対応の高精細動画配信実験実施
・デジタルテレビ情報化研究会、10月に仕様発表予定
・大画面高精細ディスプレイ対応自動画像補正装置「Vision Plex」開発・販売--オリンパス光学工業
・高精細でド迫力! 次世代型デジタルドームシアターを開発--五藤光学研究所
・立ち上がり6秒で映像が見えるプロジェクター「EMP-S1」エプソンから発売
・ビー・エイチ・エー社、「高圧縮コーデック“XVD”」を発表、ライセンス事業を全世界に推進(姉歯 康)
・日本最大のケーブル会社「J-COM Broadband」の新総帥、果たして3つ目の会社の黒字化も果たせるか(森泉知行)
・流通大再編期を迎える中、NEBA定時総会開催
・第1回ゴールドコンサートオーディション「探せ!21世紀のスティービーワンダー」総合グランプリ決定!(貝谷嘉洋)
・滋賀・長野両県に新営業所開設--シンクレイヤ
●<デジタル・パブリッシング提案(第14回)>ワン・トゥ・ワンDM戦略を提案(高下士良)
●「プロバイダ責任制限法」研究会に大阪90局・福岡40局が参加
●ケーブルテレビ網セキュリティ強化のポイントはここだ(矢野 篤)
●ノーテルネットワークスの新しいケーブルテレビ市場創造戦略(平松敏之・伊吹仁志・及川満広・亀田正博)
●総視聴可能世帯数が1,000万に迫るQVCジャパンの急成長の鍵を聞く(佐々木 迅)
●放送&モバイル機器の記録媒体の本命は? “メディア”サバイバル最前線
・高画質カメラ付き携帯の動向に注目せよ(曽崎重之)
・各記録媒体活用のメリット--松下電器産業/TDK/サンディスク/太陽誘電/スタート・ラボ
●民間企業のMOTプログラムには、大学院にないメリットがある
●日本初のメンタルヘルス対策ワンストップサービス「MTOP」(石上 裕)
●Windows MediaとQuickTime、エンコード画像の客観的な品質評価提案(Arman Aygen)
●<連載レポート 燃料電池実用化の最新事情(第1回)>世界初の大規模な定置型フィールドテスト実施、製品開発・政策展開に有益なデータを収集(芝池成人)
●バルコがマヤ文明展「コパン遺跡VRシアター」に世界初の映像システムを提供(福里清信)
●NHKは地域放送の思いきった改革を実行する(諸星 衛)
●業界初、WM9をプロジェクターに搭載したエプソン「EMP-8350」(御代茂樹・岡田 隆・赤岩昇一・野溝朋弘)
●<The Challengedとメディアサポート(第66回)>千葉からユニバーサルの風を!(堂本暁子・竹中ナミ)
■連載
●<今月の表紙>漆畑直樹・(株)ピクセン代表取締役--肥満抑制効果のある香りも開発中
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<Web Usability & Accessibility(第27回)>帝都高速度交通営団サイト--安易に視覚的技法を用いないように(濱田英雄・石田直子)
●<編集後記「BETWEEN」>
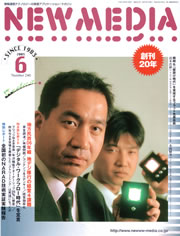
2003年6月号(2003年5月1日発売)
●地上民放06年組、地上デジタル移行の経営4課題--見えぬ未来図、消えぬ危機感、示す進路は?(音 好宏・香村佐斗史・佐藤勇一・佐藤 勉)
地方民放テレビ経営者アンケート(本誌5月号掲載)の調査結果を基に、スペシャリストの協力を得て、地上デジタル移行における経営戦略、経営者の潜在意識を鋭く分析した。
・NHK文研シンポで海老沢NHK会長が特別講演
・アナ変作業開始から2カ月、3月末までに20地区中17地区で完了
●NAB 2003特別レポート「デジタル・ワークフロー時代」を宣言
イラク戦争真っ只中の4月7日から11日、ラスベガスでNAB(全米放送業年次大会)が開催され、次世代の放送機器システムが展示された。一つの転機を示した大会となった。
・「国民の安全を支えるのは放送だ」フリッツ会長が年次報告(蓮 憶人)
・昨年会場を席巻した「ストリーミング」はもはや死語?(姉歯 康)
●NARADのOver100Mbps技術実証実験、確かに100Mbpsは出た!!(大野公稔・松浦賢司・山下伸一郎・鈴木仁志・信田剛希・黒岩孝史)
怒濤のごとく取り囲むADSLとFTTH陣営に対抗するため、CATVはHFCをもっと活用できないか。それに応える技術が、NARAD NetworksやAurora Networksの「Over100Mbps」技術だ。
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・スイッチャーやレコーダなど新製品3機種をNAB 2003で初公開--朋栄
・公共放送でITベースの効率的な放送システムを構築--SGI、MCSi
・有料番組等の情報料をメールで架空請求するトラブルが急増中
・CeBIT2003レポート、欧州にもiモード(蓮 憶人)
・ドイツ産業見本市日本代表部のCeBIT2003結果報告
・ディズニー初の本格ブロードバンドサービス開始--NTT東西、ウォルト・ディズニー・ジャパン、ディーワンダーランド
・パワー・マート&トレード・エキスポ2003開催、電力自由化に伴う新ビジネスモデルを提示、国内最大規模の排出権取引シミュレーションも実施
・電力自由化でESCO、ESP、PPS、CO2排出権取引など新ビジネスモデルの市場が本格的に拡大する(柏木孝夫)
・小売店として、共遊玩具の啓発と推進に力を入れる--日本トイザらス
・ナノ・バイオ・インフォマティクスがこれからのキーワード
・障害者と健常者が一緒に楽しめる興行初のバリアフリー上映実施
●<デジタル・パブリッシング提案(第13回)>XML自動レイアウト処理の到達点(平田憲行)
●<プラズマテレビ「画質実測テスト」(第1回)>富士通ゼネラル「P42HHS10JS」(横澤美紀・井上 俊・芳賀 稔・堀口 信)
●「いざ」というとき役立つ地上デジタル放送を目指すために(岡嶋 守・川上 淳)
●ビデオ監視・防災システム最新動向「今そこにある危機」を回避せよ!!
・現場の状況をいち早くキャッチ、モバイル活用の遠隔監視システム(曽崎重之)
・MPEG-4映像+音声双方向を低コストで実現、低遅延・高品質の監視・防災システム--沖電気工業
●NTTがSOFC型燃料電池を開発、CO2排出量の大幅削減目指す
●国立科学博物館で開催中「マヤ文明展」の世界最大規模のVRシアター(廣瀬通孝・葛岡英明・高橋文武・田中正樹・西岡貞一・工藤尚美)
●水と社会に関する精神文化育成を求める斬新な芸術表現(山本圭吾)
●国立劇場・伝統芸能情報館の「文化デジタルライブラリー」(織田紘二・吉田 敦・金田光範・平山廣和・長谷部憲次・武邑光裕)
●森タワー49〜50階「六本木アカデミーヒルズ」のBB&映像システム(坂本和也・黒部 進)
●能力認定試験の最大手「サーティファイ」の新たな取り組み(国山広一)
●<The Challengedとメディアサポート(第65回)>匂いで聴覚障害者を守る!--IT時代の警報システム実現に向けて(漆畑直樹・河関大祐・田村裕之・竹中ナミ)
■連載
●<今月の表紙>清本浩伸・オムロン(株)技術本部先端デバイス研究所マイクロフォトニクスグループ担当係長主査/本間健次・オムロン(株)技術本部先端デバイス研究所マイクロフォトニクスグループ--光の3原色を内部で混色してフルカラー光源にも
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<誤用に御用だ!(第6回)>「スペクトラム(Spectrum)」の誤用(青柳武彦)
●<Web Usability & Accessibility(第26回)>共同通信社サイト--テキスト中心のサイトでは読みやすい構成力と配慮が不可欠(濱田英雄・石田直子)
●<貝谷嘉洋の視点(第8回)>アクセシビリティ配慮マークの付いた商品を増やしたい
●<編集後記「BETWEEN」>

2003年5月号(2003年4月1日発売)
●地方民放地上デジタル06年組、これが“本音”と作戦だ
2006年に地上デジタル放送開始を予定する全国地方民放局の経営者にアンケート調査を実施。衝撃的な回答を得た。また、機器メーカー等25社を訪ね、各社の意欲的な提案を聞いた。
・NHK名古屋放送局で注目のフォーラム開催、災害での地上デジタル放送の可能性を議論
・全国地上デジタル放送推進協議会PR部会長に聞く(堀 鐵藏)
・サブチャンネルで地元ローカル番組を交換しあう「勝手ネットワーク」を提唱--毎日放送(田島 俊)
・なぜ2004年5月に地上デジタル放送開始を断行するのか--北日本放送(横山哲夫)
・調査「地方民放経営者に聞く地上デジタル放送への対応」--111局中76局回答の分析レポート「総務省殿、我々は2011年停波を楽観視していません」(佐藤 勉+本誌編集部)
・放送設備機器メーカー等25社の「サポート宣言」--「わが社の地方民放局への提案」
・送信・送出系分野--アストロデザイン/アンリツ/池上通信機/NEC/NTTファシリティーズ/コンドーブロードキャスト/東芝/日本テクトロニクス/日本ビクター/日立国際電気/日立電線/三菱電機(三原 勉・小林康雄・河内毅彦・齋藤 徹・岩崎有平・森 一弘・坂口宏昌・今井 誠・野村春紀・近藤信幸・貝嶋 誠・室岡利吉・苗木英明・林 至・船本真吾・今井 誠・広谷 光・天野 滋・高松俊一郎・貝沼保信)
・編集・制作系分野--アップルコンピュータ/アビッドジャパン/イメージワン/加賀電子/キヤノン販売/クォンテル/住友商事/ソニーマーケティング/ダイキン工業/東京エレクトロン/フォトロン/朋栄/松下電器産業(古村秀幸・室松智人・小澤伸夫・安岡政則・柴田孝司・ジョン・オニール・瀬戸一文・磯貝 純・毛塚善文・中嶋 清・原田雅博・大本 大・伊藤政貴・清原克明・野牧幸雄)
●緊急提言「プロバイダ責任制限法」とケーブルテレビ
ネット上での誹謗、中傷、差別、著作権侵害などに対するプロバイダの損害賠償責任の制限などを定めた「プロバイダ責任制限法」をケーブルテレビ事業者向けに解説する。
・プロバイダ責任制限法とガイドライン(桑子博行)
・なぜケーブルオペレーターはこの法律を理解しなければならないのか(野口満夫)
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・世界初、固体素子で「量子絡み合い」に成功、量子コンピュータ実現に大きく前進--理研、NEC
・最新セキュリティ機器/システム展示会「SECURITY SHOW 2003」に17万人来場
・第3次日・EU貿易促進キャンペーン開始、欧州中小企業からの新技術導入に期待--欧州委員会
・レンズを使わないプロジェクタが登場、驚異の投写距離“25cm!”--NECビューテクノロジー
・「第50回ISSCC」半導体の微細化に暗雲、一方で多彩な応用(蓮 憶人)
・MPEG-LAが国内で初めてMPEG-4ライセンスの説明会(姉歯 康)
・「映像コンテンツ学会(仮称)」6月に設立予定
・「第一回Web Creation Award<Web人発見!>」の公募開始--日本広告主協会Web広告研究会
・レスキュー支援総合情報システムを共同開発--日本SGI、ゼンリン・グループ、レスキューナウ
・最大200ch放送可能な「光放送サービス」実証実験開始--京阪ケーブルテレビジョン、ケイ・オプティコム、関西電力
・「デジタル映像最前線ワークショップ」プロジェクター3機種比較投写会で成果--DCAj(宮崎和信)
●<デジタル・パブリッシング提案(第12回)>情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の有効性(柴崎正道)
●NHKアーカイブス稼働1カ月(桝井修平)
●日テレのデジタルアーカイブス「日本テレビライブラリ」8月から本格稼働(黒崎忠男・小倉 徹)
●サムスン電子飛躍の解剖(麻倉怜士)
●デジタル時代の放送局はIT、IPがキーワード(橋本元一)
●ストリーミング映像をリビングで見せるマイクロソフトのWM9(麻倉怜士・御代茂樹)
●JVCの世界初の家庭用デジタルハイビジョンビデオカメラ「GR-HD1」(並木康臣)
●日本初のケーブルテレビ連携VoIP商用化サービス「けーぶるふぉん富山」開始(中村正孝・岡部一輝・燒田賢一・村上仁己・菅 俊直・青山繁行・石原裕久)
●ケーブルテレビ事業者の落とし穴、「ファリシティリスク」再点検の7大ポイント
●@NetHomeのCATVブロードバンドサービス戦略(渡辺康生・橋本澄彦・荒木 勤)
●<The Challengedとメディアサポート(第64回)>聴力を失ってもキャリアは失われない。働きたい人を支える制度作りを!(小椋知子・竹中ナミ)
■連載
●<今月の表紙>橋本俊一・ソニー(株)ホームネットワークカンパニー・プロジェクター&ディスプレイシステムカンパニー・プロジェクターエンジン部統括部長・工学博士--フルHDTVの反射型液晶デバイス「SXRD」
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<誤用に御用だ!(第5回)>「ユニバーサル・サービス」の誤用(青柳武彦)
●<貝谷嘉洋の視点(第7回)>第1回ゴールドコンサート「探せ! 21世紀のスティービーワンダー」開催
●<Web Usability & Accessibility(第25回)>「カウントダウン! 地上デジタル放送」サイト--魅力乏しく、効果に疑問(濱田英雄・石田直子)
●<編集後記「BETWEEN」>
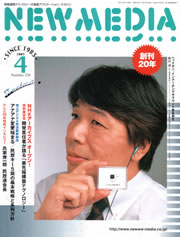
2003年4月号(2003年3月1日発売)
●NHKアーカイブスの最先端構築テクノロジー(森 明已・桝井修平・根岸弘明・金子 隆・竹松 昇・井上晴夫・北村 徹・高木一彰・森口幹也・長坂 篤)
保存可能映像ソフト約180万本という、世界最大の収容能力を誇る映像拠点「NHKアーカイブス」がオープンした。その開発・構築関係者が一堂に会し、テクノロジーを語った。
・フォトレポート、世界最大級の放送番組アーカイブがオープン
・NHKアーカイブスを支える技術・システム--NEC/日本SGI/IBE/松下電器産業/金剛/沖電気工
●民放キー局「免許申請」直後に聞く、これが地上デジタル放送の基本戦略と系列方針だ--日本テレビ/TBS/フジテレビ/テレビ東京(高田真治・城所賢一郎・石川順一・奥川 元)
2002年12月18日、NHKと在京民放キー5局は地上デジタル放送の免許申請を行った。デジタル放送移行へ舵を切った民放キー5局に、基本戦略と系列方針をインタビューした。
・「アナアナ変更」作業始まる(松本正春・岡嶋昇一)
・受信システム業界から「地上デジタル放送への期待」--マスプロ電工/日本アンテナ/DXアンテナ/日立国際電気(端山佳誠・伊藤隆継・芝田 収・小林 明)
●テレビ50年特別インタビュー、氏家齊一郎・民放連会長--地上デジタル放送移行は「国策」で進める以上、まず「負担」責任を明確にすべきだ
テレビ放送開始50年。半世紀にわたりテレビ放送事業を間近で見てきた氏家齊一郎・民放連会長に、地上デジタル放送移行問題をはじめ、日本のテレビ放送の行方と課題を聞いた。
■一般記事
●<今月の注目ニュース「New Media FRONT」>
・雷害リスク低減コンソーシアムが設立、今年は「ネットワーク雷害対策」元年に
・コンソーシアム座長に聞く「日本の雷害対策には3つの大きな課題がある」(妹尾堅一郎)
・音楽ファイル交換サービスに司法判断、仲介業者も著作権侵害に
・日本SGIが業界初、1ノード最大64CPU構成のLinuxサーバー国内出荷開始
・企業向けIP電話システム事業でNECと沖電気が業務提携
・100Mbpsの双方向通信が可能なCATVネットワーク伝送実験開始
・Windows Media 9、満を持して登場、高まる「デジタルメディア・ビジネス」への期待(姉歯 康)
・LPG改質型燃料電池の実用機を新日本石油が世界初の開発
・水素エネルギーの安全対策を実験映像で紹介する米加日共同制作ビデオを発売
・松下電器が新組織体制発足、放送用フルデジタルミキサー発売
・松下電器が新シリーズDVDビデオレコーダー「DIGA」5機種発売
・J-VIGのヤング映像クリエーターを励ます賞
・59型で奥行26cmのDLPリアを三菱電機が開発
・エプソンの新プロジェクター「ELP-735」、PCカードスロット搭載で、活用領域を大幅に拡大
・ハイデルベルグ・ジャパンが新社屋にてカラーデジタル印刷機「NexPress 2100」を日本初公開
●<デジタル・パブリッシング提案(第11回)>「WebNative」による最先端DTPワークフロー(関 郷)
●世界初のデジタルシネマ「学習」「制作」「発表」拠点、SKIP City(柳 修逸・洪 恒夫・堀内秀治)
●<激変するメディアパワー(3回連続テーマ特集・第3回)>デジタル放送時代の「受信端末」--ソニー/NEC(辻野晃一郎・高塚 栄)
●番供各社のBB配信進出状況調査、48%がすでに配信事業に参加
●注目株の新たな無線通信技術「UWB」(山本雅史)
●“テレビの復権”宣言、CES2003で見えたこと(麻倉怜士)
●今年のNAB視察ツアーはここが見所(近藤 潔・久松 隆・山内信治・金丸幹夫・八巻 磐)
●動態保存・展示に力を入れるNHK放送博物館、リニューアルオープン!
●プロジェクタートップメーカーに聞く、2003年度わが社の販売戦略--エプソン/NECビューテクノロジー/三洋電機/日立製作所(新井勝一・高木清英・岩中俊博・長林 保)
●「プロバイダ責任制限法」を中心に、ケーブルセキュリティ講演会開催
●CATVインターネットセキュリティ向上のための、4つのセキュリティポイント(矢野 篤)
●<The Challengedとメディアサポート(第63回)>「チャレンジドを納税者に」をシーティング技術が底上げする!?(山崎泰広・竹中ナミ)
●NECビューテクノロジーのDLPシネマプロジェクタ「DPC 10i」を観る、語る。(麻倉怜士・秋山雅和・井口 洋・渡辺政則・黒田 敦)
●活用シーンに合わせたPDPの情報発信をパイオニアが提案(法月利彦・内藤一彦・丸山 透・服部正和・山崎浩司)
■連載
●<今月の表紙>飯田一博・松下電器産業(株)ネットワークソリューション開発センター・音響処理開発グループ・グループマネージャー・工学博士--外耳道の音響伝播特性のデジタル補正を実現
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<誤用に御用だ!(第4回)>「コモディティ」の誤用(青柳武彦)
●<貝谷嘉洋の視点(第6回)>ジョイスティック車という常識)
●<Web Usability & Accessibility(第24回)>NHKサイト--情報整理と新技術の導入を図るべき(濱田英雄・石田直子)
●<編集後記「BETWEEN」>
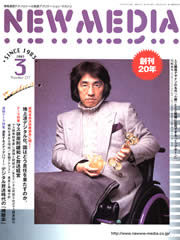
2003年3月号(2003年2月1日発売)
●総務省放送政策課長に聞く「地上波デジタル化、国はどう責任を果たすのか」(田中栄一)
地上波デジタル化は国策である以上、国の責任による体制・施策の整備が必要だ。支援策の策定などに責任を負う総務省放送政策課長(取材当時)に、一問一答で聞いた。
●マス排原則緩和と放送経営
地上デジタル放送によって放送局の経営が変わる。そのカギは、キー局の資本がローカル局へ対応できるのかにある。マスメディア集中排除原則の規制緩和として議論が進む。
・マスメディア集中排除原則見直し論議に内在するいくつかの問題点(音 好宏)
・BSデジタル民放5社がマスメディア集中排除原則の緩和を求める理由(金光 修)
・金融アナリスト直言「再編は必至だが、総務省の緩和策では地盤沈下は必至だ」(佐藤勇一)
●<激変するメディアパワー(3回連続テーマ特集・第2回)>デジタル放送時代の「視聴率」
ビデオリサーチ社が展望するデジタル時代のテレビ放送「視聴率」の考え方をインタビュー。視聴率測定機の技術開発や「シングルソース・データ」の新提案を寄稿したもらった。
・ビデオリサーチが考える「デジタル放送と視聴率」(尾関光司)
・デジタル放送の「視聴率測定機」技術提案(田中 博)
・TBS、博報堂、松下電器3社が地デジ「ケータイ放送」デモ調査
・個人型シングルソース・データ「VR Personal Scan System」の提案(塚原新一)
●HD24P制作プロセス全研究
ビデオリサーチ社が展望するデジタル時代のテレビ放送「視聴率」の考え方をインタビュー。視聴率測定機の技術開発や「シングルソース・データ」の新提案を寄稿したもらった。
・映画『ピンポン』から制作の実際と課題(曽利文彦)
・HDW-F900フィルムγおよびHDシネレンズテスト撮影について(池田修康)
・HD24Pビデオ映像からのフィルムレコーディング(柴田祐男)
・HD24P音響製作の概要と課題--映画『模倣犯』から(多良政司)
・世界で活躍するHDCAM24P「シネアルタ」に新機能搭載モデル登場(岡田修司)
・デジタルシネマへのわが社のレンズ提案(キヤノン/富士写真光機/ナックイメージテクノロジー)
・デジタルシネマ成功のカギは、デジタルシステムの正しい理解から(秋山雅和)。
■一般記事
●<New Media FRONT>
・地上デジタル、東名阪17社が免許申請
・SPOT、ついに姿を現す--International CES 2003速報(蓮 憶人)
・防災フォーラム開催「地上デジタル放送と災害報道」
・日本映画撮影監督協会「三浦賞」該当作品なし
・基本性能とコストパフォーマンスを追及したプロジェクター新機種発売
・日本ケーブルテレビ連盟に「セキュリティ調査会」が発足(野口満夫・壱岐浩康・野尻康弘・瀧澤 淳)
・雷害リスク低減コンソーシアムが準備フォーラム開催
・「電子ホワイトボード」の近況(針生文樹)
●NHK専務理事・技師長に聞く、2003年地上デジタル放送開始への取り組み(吉野武彦)
●『NHK紅白歌合戦』で初の双方向機能活用、“お茶の間審査員”4万5,336票!!
●<デジタル・パブリッシング提案(第10回)>印刷会社を取り巻く全領域がソリューションの対象、解決策を顧客より先に提示(和泉広彦)
●ブロードバンド時代の「NHKアーカイブス」、NHKテレビ放送開始50年の2月1日スタート(大井康祐)
●<Video ITソリューション(第6回)>放送映像を即編集・即配信するオンエア同録編集トランスコードシステム--毎日放送(MBS)の活用事例(姉歯 康)
●<使いたくなるケイタイ論(第3回=最終回)>ビジネス活用はココまで進んでいる、爆発的普及のカメラ付きケイタイ(曽崎重之)
●VoIPサービスも視野に入れ、大分県域のケーブルテレビ事業者が連結(佐藤英生)
●<The Challengedとメディアサポート(第62回)>
・チャレンジド社長、機会均等と自立のIT大国に学ぶ(谷井 亨・ダーナ・アン・ウェルトン・竹中ナミ)
・インターナショナル・ビジター・プログラムでアメリカを視察して(谷井 亨)
●日本のデジタルアーカイブのレベルの高さを実証(壱岐 徹)
●全国10電力会社が最高レベルのBBコンテンツ配信サービス「BBit-Japan」をスタート(有吉 猛・土山仁司・茅野智弘・山方信雄)
●<シリーズEPSON EXCELLENCE(第23回)>無線LAN対応プロジェクター「ELP-735」(赤岩昇一・久保田真司)
■連載
●<今月の表紙>川崎和男・名古屋市立大学大学院教授・大阪大学大学院特任教授・医学博士・デザインディレクター--NHK『ようこそ先輩』では、視聴モニターの評価が「珍しくバラバラだったそうだよ」
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●新連載<誤用に御用だ!(第3回)>「CRM」の誤用(青柳武彦)
●<Web Usability & Accessibility(第23回)>Yahoo! JAPAN--巨大化の悩みをどう解決していくか(濱田英雄・石田直子)
●<(第5回)>パイオニアが10年間続けてきた企業市民活動「身体で聴こう音楽会」
●<BETWEEN(編集後記)>

2003年2月号(2003年1月1日発売)
●ホームプロジェクター2003--ここまで来た画質とビジネス
家電店で急速にお客の関心を集めているのが、フロント型プロジェクターによる「ホームシアター」。“画質のオニ”たちが精鋭5社の画質を評価。各社の画質づくり、特徴が見えてきた。
・アメリカで新しいマーケットを開拓する新型プロジェクター(アレッサンドラ・アルムグレン)
・家電専門誌記者が見た繁盛店頭動向(堀越春一)
・“画質のオニ”麻倉怜士氏と村瀬孝矢氏による、精鋭5社ホームプロジェクターの画質評価解説(エプソン/三洋電機/シャープ/松下電器/ヤマハ)
・ハウス設計のプロとホームシアターづくりのプロが対談「非常に面白い時代になった」(黄 紹堅・神崎健太朗)
・シャープの一番のこだわりは黒の階調性--暗部を豊かに再現するDLP方式を採用
・エプソンはつないで、ポン!--マルチソースの簡単接続で、ようこそ“大画面生活”へ
●雷害は「人災」だ--果たせ、ケーブルテレビの責任!!
ケーブルテレビで雷害が急増しているが、本格的な対策に取り組む事業者は少ない。情報化社会の重要インフラを担うネットワーク事業者の責務である雷害対策の実行を提案する。
・雷害のリスクガバナンスは、ケーブルテレビ局に必須の課題(妹尾堅一郎)
・雷害対策の設備投資は経営課題として不可欠(池辺裕昭・高橋明男・岡林親志・坂井章人・西澤 滋)
・最新雷害対策製品・ソリューション解説(サンコーシヤ/日本高圧電気/白山製作所)
●海老沢勝二・NHK会長、テレビ50年新春インタビュー「放送は技術を活用した文化。我々には文化を創造し、後世に残し、文明のかけ橋となる務めがある」
2003年、テレビ放送50周年を迎えたNHKの会長として、「テレビ50年」への思いや、地上デジタル放送の開始など、大きな節目を迎えた放送の今後の展望を語っていただいた。
■一般記事
●<New Media FRONT>
・アメリカDTV、正念場の普及対策に動くか(隈部紀生)
・生き残りを賭けるCOMDEX--Microsoft主導の知的家電技術登場(蓮 憶人)
・三菱電機、世界初のインターネット配信型フルカラーデジタル看板を発売
・新宿のアルタビジョンが銀座三越に登場
・3回目のプライベートショー「IMAGICA Cinema2002」開催
・BSデジタル2周年「BSデジタル大賞2002」受賞作品発表
・放送のバリアフリーを目指して「リアルタイム字幕放送セミナー」開催
・BSフジ、双方向英語教育番組「もし模試TV for the TOEIC TEST」を開始
・日本SGI+日立+ブロケード3社によるオールインワン型SANシステム製品化
・会員1万人突破の「Slownet」--ブロードバンド時代だからこそスローライフ
●<デジタル・パブリッシング提案(第9回)>双方向性インターネット調査システム--インターネット「生き物調査」に見る可能性(中澤堅一郎)
●<使いたくなるケイタイ論(第2回)>激化するケイタイ「高画質化」競争が周辺ビジネスに及ぼす影響力(曽崎重之)
●世界で一番コンパクトなパナソニックの3チップDLP方式プロジェクター(島岡克明・松原洋二郎)
●<激変するメディアパワー(3回連続テーマ特集・第1回)>
・広告主Web研が、デジタル時代の広告メディア戦略「メディア構造改革宣言」を発表(真野英明・峯川 卓)
・「ターゲティング」への挑戦、「蓄積型サービス」への対応策--春から広告会社2社が共同実験
●「『VideoIT』の機は熟した。MAMの先には巨大なマーケットがあると確信」(菅原 仁)
●<Video ITソリューション(第5回)>映像のデータベース化・配信の自動化ソリューション--東京学芸大学の活用事例(姉歯 康)
●ウェスタンケーブルショーがBB通信技術中心のイベントへ大変身(藤本篤志・石原 篤)
●2003年のケーブルテレビ局デジタル化投資の焦点は、VoIP商用化とデジタルSTBの普及(安藤時彦)
●ケーブルテレビ局のVoIP参入、パートナー選択の9つの比較ポイント(宍戸一弥・市来裕教・中村高根・小林直行・小林賢一・藤原 洋)
●だから「BBケーブルTV」は成功する(楜澤 悟)
●<The Challengedとメディアサポート(第61回)>最高の技術を最重度の人の自立のために(石井純夫・麩澤 孝・竹中ナミ)
■連載
●<今月の表紙>片山幹雄・シャープ(株)モバイル液晶事業本部長--エレクトロニクスを超える“光”技術を生かせる
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●新連載<誤用に御用だ!(第2回)>「米国破産法第11章」の誤用(青柳武彦)
●<Web Usability & Accessibility(第22回)>中央省庁サイト総評--Webサイトの運営目的は何か、「伝わる情報」を念頭に入れよ(濱田英雄・石田直子)
●<貝谷嘉洋の視点(第4回)>旭化成の「ライフタクト」で未来生活送ってみませんか
●<BETWEEN(編集後記)>
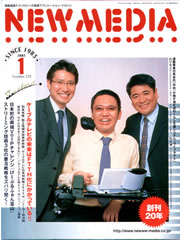
2003年1月号(2002年12月1日発売)
●ケーブルテレビの未来はFTTH化にかかっている!!
ケーブルインターネットを引き離すADSL、そして急成長するFTTH。“FTTHブーム”を絶好のチャンスにできるかどうかは、ケーブルテレビ局各社の設備投資戦略にかかっている。
・ケーブルテレビの長期戦略「FTTHに強気の姿勢で取り組むべき」(羽鳥光俊)
・<関連メーカー総決起座談会>「HFCのままではFTTHには対抗できない」(岡野 久・青山繁行・小林隆男・坂主好章)
・最新ケーブルテレビ用FTTHソリューション提案(NEC・NECケーブルメディア/シンクレイヤ/フジクラ)
●日本初の県域VoIPチャレンジ「けーぶるふぉん富山」--2003年2月から商用化、域外接続を目指す(中村正孝)
富山県ケーブルテレビ協議会は、日本で初の県域VoIPサービスのモニター募集を開始した。新聞広告、テレビCMなどでプロモーションも展開。サービスの計画や可能性を聞いた。
●ストリーミング技術3社の普及戦略をズバリ聞く!(姉歯 康・御代茂樹・河野万邦・古井洋司・古村秀幸)
WindowsMwdia Technology、Real Media、Quick Timeは、成熟期を迎えた。技術のベースが整ったところで、今後は普及戦略が重要になる。3社のキーマンに最新事情を聞いた。
・<安心のストリーミング提案>ソニー「MediaStage」はネット経由で映像エンコーディング、低コストで動画配信可能(川井啓亘)
・<安心のストリーミング提案>メディア、BB市場へ積極展開、日本SGIの技術資産が活かせる時代が到来した(和泉法夫)
■一般記事
●新コーナーがスタート--<New Media FRONT>富士通ゼネラルがPDPで世界初のエミー賞受賞/シャープと半導体エネルギー研究所が世界初「ガラス基板上にCPU」/ナノテク新素材「規則配列セラミックス多孔体」開発、燃料電池のメタノール透過が9割減に ほか
●<デジタル・パブリッシング提案(第8回)>顧客の視点に立ったクロスメディア企画制作(和泉広彦)
●CATV局とスカパーの個別交渉で進展(園田義忠)
●ケーブル事業者229社結集、「日本ケーブルキャスセンター」の目指すもの(塩冶憲司)
●世界最大級の映像アーカイブス、NHKアーカイブス
●「文化資産」が産業を誘引する時代を証明(衣川由希子)
●日立プラズマテレビ「Wooo」、成功のカギはテーマを決めた画づくり(麻倉怜士・青木浩司・長谷川 敬・尾関考介)
●長野県穂高町からの「コンテンツ立国」政策--ソニー出井会長らが語る(神田敏晶)
●Panasonic液晶プロジェクター「TH-AE300」、フィルムの映像美を再現(松原洋二郎)
●<シリーズEPSON EXCELLENCE(第22回)>「ELP-73」「ELP-53」、普段着でプロジェクターを使いたい人に向けて新発売(馬塲宏行・新井勝一)
●BS8社共同キャンペーン「ハイビジョン!スペシャル100」スタート(軍司達男)
●南極から世界初のハイビジョン生中継実施!(佐々木 元)
●組込用プロセッサも1GHz超の時代へ、PDA、STBの能力は拡大へ--Microprocessor Forum 2002レポート(蓮 憶人)
●<Video ITソリューション(第4回)>N対Nのインタラクティブなテレビ会議を実現する「GloBiz21」--コスモトレードアンドサービスの活用事例(姉歯 康)
●<使いたくなるケイタイ論(第1回)>カメラ付携帯とFOMAにみる「手軽さ」重視のユーザー心理(曽崎重之)
●世界的な先端企業がひしめくカナダの燃料電池産業最前線(竹本 隆)
●<The Challengedとメディアサポート(第60回)>
・就労支援組織「eふぉーらむ」はチャレンジドも参画の自治を目指す(北川正恭・竹中ナミ)
・「紹介予定派遣」で障害者の就労拡大(中和正彦)
●東京国際映画祭に「NCFムービー・ギャラリー」初登場(前澤哲爾)
■連載
●<今月の表紙>山岸秀之・旭化成(株)研究開発本部住環境システム・材料研究所課長・工学博士/柏原誠一・旭化成(株)研究開発本部住環境システム・材料研究所主幹研究員--目指すは音声で一発操作、しかも携帯性のある小型軽量
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●新連載<誤用に御用だ!(第1回)>「QoS」の誤用(青柳武彦)
●<Web Usability & Accessibility(第21回)>政府広報オンラインサイト--デザイン、構成とも平均以上だが、トップページの情報内容が不明瞭(濱田英雄・石田直子)
●<貝谷嘉洋の視点(第3回)>ダイエーの取り組みはちょっとすごい(後編)--駐車許可証制度は、行政もお手本にすべし
●<電通局長・恒太郎のNMadクリエイティブ(第15回・最終回)>小さきものは、皆うつくし(杉山恒太郎)
●<BETWEEN(編集後記)>