バックナンバー紹介
(2002年の号)
(2002年の号)
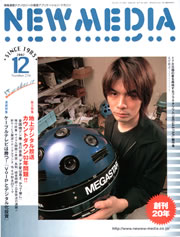
2002年12月号(2002年11月1日発売)
●<総力特集>地上デジタル放送カウントダウン'03年問題
50年という歳月をかけた全国の放送網を、たったの8年でデジタルに移行せよという政策が打ち出された。移行のための投資はもちろん、新ビジネスモデルへの模索が始まる。まさに地上デジタル放送移行の「'03年問題」。8分野、20テーマの話題で整理した。
・<要点解説>地上デジタル放送の基本技術と特徴
・全国地上デジタル放送推進協議会会長に聞く(北川 信)
・<「'03年問題」を8分野、20テーマの話題で整理>移行政策・サイマル問題/国民の意識/放送規格問題/技術課題/民放「系列」経営問題/広告放送/新サービス展望/地上デジタル音声放送(デジタルラジオ)/コンテンツ管理提案/ケーブルテレビ局の対応課題/BSデジタルの番組満足度/編集長の着眼(麻倉怜士・鈴木祐司・音 好宏・菅原 仁・編集部)
・これからのデジタル放送と音の世界--5.1チャンネルによる音楽創作の視点から(冨田 勲・村井清二)
・強靱で柔軟なデジタル放送局を目指せ!--アンリツ/ソニー/NECソリューションズ/パサタ/松下電器産業)
「有線系」のADSL、FTTH、そしてケーブルテレビのブロードバンド陣営は、ユーザー獲得のためにデジタル化投資の拡大を余儀なくされている。ケーブルテレビ・ビジネスの可能性について、VoIPやDBCなどの新サービス、財務分析、最新技術を中心にまとめた。
・DBC(Direct Broadcasting Cable)に勝機あり
・2006年から人口減が始まることをデジタル化投資に際して考慮せよ(澤田正彦)
・日本初のIP-CATV放送事業「BBケーブルTV」(橋本太郎)
・業界初の超高速DOCSISモデムなど、伊藤忠ケーブルシステムの最新ソリューション解説
・VoIPの技術・市場動向とNTTコムウェアの取り組み
■一般記事
●放送のバリアフリーを目指してデジタル化で進化する、NHKの「人にやさしい放送」
●<Video ITソリューション(第3回)>メタデータによる映像管理で効率配信する「Outliner」--(株)エバーグリーン・デジタル・コンテンツの活用事例(姉歯 康)
●トヨタ「G-BOOK」サービスの全容(友山茂樹)
●<麻倉怜士が最新液晶テレビの画質を評価
・業界最速の動画表示、Panasonic「液晶T“タウ”」
・新ベガエンジン搭載、SONY「液晶“ベガ”」
●<技術解説>統合デジタル高画質システム「ベガエンジン」(山本善寛)
●市民のシーズを政策に反映するeデモクラシーは地域間競争勝ち残りの切り札(金谷年展)
●メディア・アートという産業の勃興--「アルス・エレクトロニカ」レポート(神田敏晶)
●<NM INFO>村瀬孝矢が見た「CEATEC 2002」注目のディスプレイ ほか
●<デジタル・パブリッシング提案(第7回)>遠隔履修と授業の効率化に対応した「大学医学部電子シラバス」の構築(前田和也)
■連載
●<今月の表紙>大平貴之・プラネタリウム・クリエーター--「MEGASTAR」後継機づくりに着手
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<筋金入りケーブルテレビ経営(第142講・最終回)>“革命”でも変わらない人の営み--問われる、新規事業の創造力(佐野匡男)
●<貝谷嘉洋の視点(第2回)>ダイエーの取り組みはちょっとすごい(前編)--バリアフリーで企業利益アップ)
●<Web Usability & Accessibility(第20回)>内閣府サイト--「寄り合い」の組織形態がサイトの構成にも強く反映(濱田英雄・石田直子)
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第20回)>今月のキーワード「人材採用とエントリーシート」--読んでもわからない!? ならば視点を変えよ(土方了順)
●<BETWEEN(編集後記)>
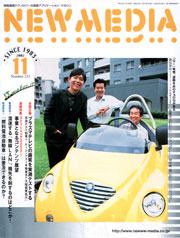
2002年11月号(2002年10月1日発売)
● プラズマテレビの画質を実測テストする
4社のプラズマテレビの画質を横澤美紀・東京情報大学教授指導のもと、実測テスト。普段ディスプレイ技術の専門家が見ることの多い数値データをわかりやすくグラフ化した。
・画質の実測テスト結果--三洋電機、日本ビクター、パイオニア、富士通ゼネラル
・実測テストのねらいと読み取り方(横澤美紀・村瀬孝矢)
・ホームシアター本格普及、大画面化ニーズの増加で、プラズマテレビの大幅需要(稲葉視朗)
●<3連続特集 ストリーミング2002(第2回)>事業となるコンテンツ展望--ブロードバンドによるストリーミング・コンテンツ配信事業化に王道はあるか(萩原和彦・五十川 匡・辻 知之・古株 均)
ストリーミングの動画コンテンツ配信事業を展望。動画コンテンツといえば、最強メディアのテレビ放送があるが、常時接続のブロードバンドはどんな事業をもたらすのか。
![]() ●無線「乱」勃発!!--混戦模様を打開せよ
●無線「乱」勃発!!--混戦模様を打開せよ
無線LANサービスが活発化してきた。多数の企業が商用化や実験に参加して、激しい覇権争いを繰り広げている。電波競合、基地局設置問題、最新活用事例をレポートする。
・主な無線LAN規格とサービス事業者
・<図解>実測データで見る無線LANの「電波競合」問題(瀬賀幸一)
・法解釈で混乱するJR駅構内「線路」問題(井上繁樹)
<無線LAN最新活用事例>
・無料で使える「フリースポット」で町おこし--名古屋市大須商店街
・学校で高速無線LANを導入--三鷹市
・ケーブルテレビ局が集合住宅で導入実験--北ケーブルネットワーク
この夏、燃料電池自動車が実用化に向けて大きく動き出した。トヨタ、ホンダが今年末の発売を相次いで発表。しかし、市場環境はまだ整っていない。普及の課題と可能性は?
<経済産業、国土交通の2副大臣に聞く>
・2004年までに前倒しで規制緩和、燃料電池特区への自治体の参加に期待(古屋圭司)
・先手で水素スタンドを積極的に整備、10年以内に1万カ所設置が目標(佐藤静雄)
■一般記事
●<The Challengedとメディアサポート(第59回)>チャレンジドの手でイーハトーブを!--「第8回チャレンジド・ジャパン・フォーラム 2002 in いわて」報告(中和正彦)
●スタートラインについた地上デジタル放送(和崎信哉)
●ナチュラルビジョンの世界--従来の3原色にとらわれず色を忠実に再現(横澤美紀・金子啓明・田中 博・河口洋一郎・大山永昭・中村直司)
●<編集長がズバリ問う BBストリーミングのターゲット(第10回)>--毎日放送(MBS)--94年から積み上げてきたインターネット経験が、ストリーミング「阪神タイガースLive!」を生む
●<シリーズEPSON EXCELLENCE(第21回)>価格19万8,000円「ELP-30」衝撃デビュー、エプソン販売社長が販売戦略を大いに語る(真道昌良)
●三洋電機のハイビジョンプラズマテレビ「VIZON(ヴィゾン)」(麻倉怜士・前田 健・河合晃弘・岡本敏一・吉田好行)
●「地上デジタル放送免許方針案」を総務省地上放送課長に聞く(安藤友裕)
●<Video ITソリューション(第2回)>ノン・オーサリングでマルチメディアコンテンツ作成「EZプレゼンテーター」--NTTコミュニケーションズ(株)の活用事例(姉歯 康)
●世界に誇る「1インチヘッド」採用で低コスト、高速、高画質のキヤノンオフィスカラープリンタ(野沢佳津夫・小野田繁義・滝沢勝己)
●<ファーストクラス・ケーブルテレビ局訪問(第5回)>(株)ZTV--「ソフトスイッチClass5」導入のグレートユーザーの現場を視る(Ted Griggs・Ken Bender・Jonathan Reid・日下部俊彦・吉田 要)
●攻勢の時だ!「J-COM Broadband Forum 2002 in Urayasu」開催(松崎秀樹・廣瀬禎彦・鈴木敏正・服部眞司)
●<デジタル・パブリッシング提案(第6回)>「PDF校正」で打てば響くチラシ作り(大野謙治)
●<NM REPORT>インターネットの前身、ARPANETは耐核戦争用ではなかった!(杉沼浩司)
●<NM WATCH>おもしろくなってきたプロジェクター業界、きっかけはホームシアター
●<NM TECH>--(株)ブロードネットマックス--Deep
HFCや従来のHFCを有効活用したFTTHネットワーク整備を提案(小谷浩之・小野 浩)
●<NM
INFO>日本テレパソロジー研究会に全国から集合 ほか
■連載
●<今月の表紙>渦尻栄治・チョロキューモーターズ(株)取締役、近藤洋之・チョロキューモーターズ(株)取締役・事業推進グループプロデューサ、田中修一郎・チョロキューモーターズ(株)取締役・企画開発グループプロデューサ--おもちゃ屋が造った電気自動車、売れ行き絶好調
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<貝谷嘉洋の視点(第1回)>ロボットか? 電動車いすか?--第29回国際福祉機器展のポイント)
●<Web Usability & Accessibility(第19回)>(財)地方自治情報センターサイト--フレームの安易な使用でサイトの使い勝手を阻害(濱田英雄・石田直子)
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第19回)>今月のキーワード「言語分析の実態」--言語分析は背景の文化の分析をも含む(土方了順)
●<電通局長・恒太郎のNMadクリエイティブ(第14回)>「経験メディア」と考えたい(杉山恒太郎)
●<筋金入りケーブルテレビ経営(第141講)>リアルで深い人間関係のために--新しい事業ゆえに、時代遅れも必要(佐野匡男)
●<BETWEEN(編集後記)>
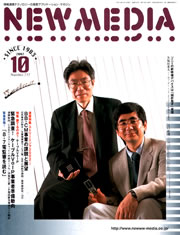
2002年10月号(2002年9月1日発売)
● <3連続特集 ストリーミング2002(第2回)>BB-CM事業の課題と展望--プロモ関係者必読(協力:姉歯 康・峯川 卓)
ブロードバンド上の動画CM−−「BB-CM」に、市場規模6兆円の広告業界はどう反応するのか。また、BB-CM事業を切り拓かんとする起業家たちが着眼する事業性はどこにあるのか。
・BB-CMを取り巻く業界の動き
・主要事業者7社のサービス一覧
・BB-CM制作の課題(杉本健二)
・<業界座談会>BB-CMの特性をテレビとの比較で考える(真野英明・大木眞熙・峯川 卓・日下部耐史・佐藤裕幸・菅谷俊二・中川 進・広屋修一・福元邦雄)
・商社の特性を活かしたテレビ型配信サービス「CMナビ・プロジェクト」
・テレビCMをWeb広告展開するアゼスト「e-CM」)
●ケーブルVoIPは勝てるのか?--2003年春から一斉商用化、東名阪74局大連携が実現へ
東名阪74ケーブルテレビ局による空前絶後の大連携構想が着々と進行。さらに拡大することが予想される。電力会社、ヤフー、NTT、KDDIなどと接戦を演じることができるのか?
・日本最強のケーブルアライアンス「TDNC+スターキャット+中部ケーブル」来春商用化へ(奥村博信)
・<ケーブルテレビデジタル化実態調査(第13回)>ケーブルテレビ102社が回答、ケーブルVoIP「風」の行方
・沖電気がIP電話普及推進センタを開設--これからはケーブル局、自治体などの公共セクターで伸びる(疋田定幸)
・すでに4,000世帯でVoIPサービスを展開している島根県大東町)
総務省は8月7日、「放送普及基本計画の変更」などを電監審に諮問。地上デジタルの免許方針案とアナアナ変換の対応が打ち出されたことで、地上デジタル移行計画が動き出す。
・視界は不良? 地上デジタル放送(天野零一郎)
・地上デジタル放送で広告は変わるか?(湯川朋彦)
■一般記事
●ワールドカップはBSデジタル普及の起爆剤となったのか(市川 勇)
●シンクレイヤからの挑戦状「ケーブルはメディア・ビッグバンの主役」(山口正裕)
●<編集長がズバリ問う BBストリーミングのターゲット(第9回)>(株)トレソーラ--3局のテレビ番組を500Kbps配信する「Chance!@トレソーラ」
●<Video ITソリューション(第1回)>100%字幕時代への強力な武器--スピーディ・低コストの字幕制作システム「NeON-III」(姉歯 康)
●infoComm Japanの中で最も注目を集めたNECビューテクノロジーの「SQUARE SHOT」(高木清英)
●映画『パルコフィクション』をVaricamで撮影--フィルムのような官能的映像に到達(矢口史靖・鈴木卓爾・安田裕子・座間隆司・田口勝行)
●<The Challengedとメディアサポート(第58回)>本格的に動き出した日本の基準の行方(中和正彦)
●<デジタル・パブリッシング提案(第5回)>印刷会社がペーパーレス提案--電子文書管理システムを独自開発(高下士良
●<NM WATCH>Yahoo!BB加入者向け「BBケーブルTV」サービス開始(橋本太郎)
●<NM INFO>「infoComm Japan 2002」最新14機種レポート ほか
■連載
●<今月の表紙>久保田重夫・ソニー(株)コーポレートリサーチフェロー・工学博士、江口直哉・ソニー(株)コアテクノロジー&ネットワークカンパニー・コアテクノロジー開発本部フォトニクス研究部統括部長・主幹研究員--「回折格子」原理によるソニーの新ディスプレイデバイス
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<筋金入りケーブルテレビ経営(第140講)>そろそろ時期到来か--ケーブルTVでのコミュニティーFM(佐野匡男)
●<Web Usability & Accessibility(第18回)>環境省サイト--長すぎる文章リンクが大きなマイナスポイントに(濱田英雄・石田直子)
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第18回)>今月のキーワード「時勢ボード」--新聞の新しい読み方で時勢を予測せよ(土方了順)
●<BETWEEN(編集後記)>
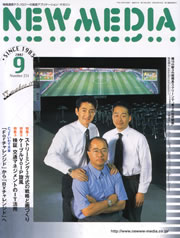
2002年9月号(2002年8月1日発売)
● <連続特集 ストリーミング2002(第1回)>ストリーミング3方式の戦略と画づくり展望(姉歯 康)
ストリーミングの技術を提供する3社−−リアルネットワークス、マイクロソフト、アップルコンピュータの事業戦略と、エンコード技法による画づくりについてレポートする。
・日本初! CM素材エンコードを実例で検証(村瀬孝矢)
・絶対に必要! ストリーミングCMの「エンコード基準」(石川治彦)
●<ケーブルアライアンスが実証実験・商用サービス開始>特集Cable VoIP旋風
日本の主要ケーブルテレビアライアンスが、8月から一気にVoIP実証実験や商用サービスを開始する。ケーブルVoIP旋風の実態を3号にわたる連続特集でレポートする第一弾。
・全国ケーブルアライアンスのVoIPプロジェクト状況
・世界初ZTVのDOCSIS1.1対応VoIPにSyndeoソフトスイッチを採用(吉田 要・内田庸行・日下部敏彦)
・津市は世界で最もユニークなブロードバンド先進地域(近藤康雄・杉本 弘・中村共喜)
・関西ケーブル18局とZAQの挑戦「日本のケーブルVoIPは関西から」(小西良往・畠山乃生彦・藤原 洋・大山 茂・大沢 潔)
●<TDM先進自治体の事例を検証>交通需要マネジメントを成功させる公共交通情報サービスは何か?
渋滞や大気汚染など地域の交通問題を解決する施策として、交通需要マネジメント(TDM)が注目されている。TDMの中でも特に情報通信を活用した施策の成功条件を探る。
・「ドアtoドア」が好評な公共交通を路線バスの半分のコストで運行中(酒井隆行)
・地図上の入力で簡単に2・3次元アニメ化できる交通流シミュレーションシステム)
障害者が誇りを持って生きられるIT社会を目指すチャレンジド・ジャパン・フォーラム(CJF)が、8月に岩手県で開催される。どんな会になるのか。増田知事など3人が語る。
■一般記事
●2002 FIFAワールドカップの生中継に生字幕(鬼丸眞人)
●エプソンのプロジェクター提案は「さらに」(本多 豊・竹村英二・鈴木新次郎・村山郁二・麻倉怜士・木村登志男)
●液晶プロジェクターの「三者サンヨー」活用事例(小林弘明・鈴木利治・石渡 登・塚本貴信・岩中俊博)
●HDCAM24pシネアルタで映画『ピンポン』撮影、「24pは私の最大の武器」(曽利文彦・早坂高志)
●infoComm 2002ラスベガス大会で見たいくつかの「兆候」(麻倉怜士・稲葉視朗)
●<ブロードバンド国家戦略の最新事情(第4回)>カナダ--機能的な組織を中心とした先進的な回線運用・管理に注目(青柳武彦)
●<編集長がズバリ問う BBストリーミングのターゲット(第8回)>読売テレビ--24時間ライブ配信 「ライブよりオンデマンド配信が相応しい」
●<特集 IP活用の監視・防災システム>普及への期待膨らむIP活用の監視システム(曽崎重之)
・IP通信とリアルタイム動画配信の活用で、機能的なシステムを構築
●<デジタル・パブリッシング提案(第4回)>ショッピングカートレンタルシステムと汎用アンケートシステム(柴崎敏紀)
●<NM WATCH>出だし苦戦「FOMA」の底上げねらう「Vライブ」プロジェクト
●<NM REPORT>電子投票、新見市についで白石市、中津市、広島市などが実施プロセスを進行)
●<NM WATCH>「ワールドカップ最大の謎」と言われたAVAYA鵜野社長が語る「成果と自信」
●<NM INFO>松下電器が地上デジタル放送対応テレビカメラ6機種発売 ほか
■連載
●<今月の表紙>佐佐將行・2002年FIFAワールドカップ日本組織委員会・情報通信専門委員会委員長代行、松信章一・元日本ビクター(株)ワールドカップ推進室次長、大場省介・ソニーPCL(株)クリエイト事業部映像ソフトセンター担当部長--スタジアム最高の席と同じ観戦視野
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<筋金入りケーブルテレビ経営(第139講)>セールスや契約の現場の状況は--有テレ法、訪販法では対応できない(佐野匡男)
●<Web Usability & Accessibility(第17回)>法務省サイト--全体的には平均点以上、されどサイト構成など工夫を(濱田英雄・石田直子)
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第17回)>今月のキーワード「終身雇用」--問題提示に弱腰な新聞報道(土方了順)
●<電通局長・恒太郎のNMadクリエイティブ(第13回)>カンヌフェスティバルの勝者たち(杉山恒太郎)
●<図読のすすめ(第16回・最終回)>「古川市農業・農村振興中期計画」を図読する(久恒啓一)
●<BETWEEN(編集後記)>
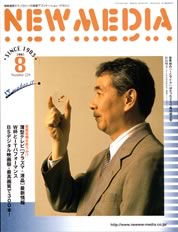
2002年8月号(2002年7月1日発売)
● <家電危機を救うか?!>薄型テレビ(プラズマ+液晶)最新情報
プラズマと液晶の薄型テレビが不振を極めていた家電業界の救世主となっている。湧き上がる薄型テレビブームは本物か。それを確かめるべく、画質面と販売店頭の実態から、その真贋に切り込んだ。さらに、業務用分野でのプラズマ活用の最新動向も聞いた。
・<「画質のオニ」の画質診断>各社が繰り出す画質革命の切り札を斬る!(麻倉怜士)
・<好調な売れ行きは本物だ!>「本当に売れているのか」の疑問は簡単に裏切られた(吉村 永)
・<3年後プラズマ市場1兆円超に照準>松下電器が2004年4月、業界最大の量産工場を操業(森田 研・猪原静夫・大竹桂一・麻倉怜士)
・<PDPのパイオニアが語る>PDP活用のカギは5つの「P」にあり(水谷純一)
●<ワールドカップとITパフォーマンス>短い準備期間のためか、目立つ新規ITサービスは少ない
ワールドカップの運営にとって、ITは欠かせないものになっている。1990年のイタリア大会では、公式記録をフロッピーベースで運用していた状況であった。隔世の感。大会のIT拠点となる「国際メディアセンター(IMC)」から、ITの活躍ぶりをレポートする。
●<BSデジタル映画祭>この夏、最高画質で300本!(土屋 円)
ワールドカップで「NHK、民放の2トップ」を成功させたBSデジタル放送が、次に挑むのは「BSデジタル映画祭」。今度は、スター・チャンネルも含めた3バックか? BSデジタル放送の普及拡大に向けて、守りを固めつつも積極果敢に攻めていく。
■一般記事
●<シリーズEPSON EXCELLENCE(第20回)>スペック競争終焉宣言「誰でもプロジェクターが買える時代をエプソンがつくる」(木村登志男)
●<ドキュメンタリー『子供が見たルーヴル美術館』を全編24p撮影>ソニーのHDCAM24pが「名画の空気」をとらえた(重延 浩・神永幸三)
●<日米韓ブロードバンド国家戦略の最新事情(第3回)>日本--公共財であるインフラ構築を民間に期待するe-Japan戦略(青柳武彦)
●<成長・進化する電脳宇宙>「河口洋一郎のCG世界」展開催(串山久美子)
●<セミナー「光ファイバーソリューション2002 in 神戸」>BBバックボーンの選択次第で企業、自治体の将来が決まる(藤原 洋・芝 勝徳・寺本雅夫)
●<合併自治体の地域情報化戦略>最先端立体映像で魅力ある地域情報を発信する山梨県八田村(齋藤公夫・外越久丈・窪田久夫・長沢 純)
●<ファーストクラス・ケーブルテレビ局訪問(第3回)>ケーブルテレビ富山--富山の8局連携ケーブルネットワークは、世界に一つしかない貴重なネットだ
●<ミート・ザ・プレス「ブロードバンドケーブル2002」開催>「勝てるのか?」の質問に「もちろん勝てる」が答え
●<The Challengedとメディアサポート(第56回)>情報アクセシビリティ最前線(第3回)--専用品とUD、両面から挑戦する日立製作所(中和正彦)
●<デジタル・パブリッシング提案(第3回)>テレビ番組表自動組版で販促力アップ(押久保智史)
●<NM REPORT>マイクロソフト・Coronaは720p、5.1chサラウンドをサポート(姉歯 康)
●<NM INFO>地域新交通システム向けソリューションの展示会出展が相次ぐ ほか
■連載
●<今月の表紙>田島利文・NHK放送技術研究所・撮像デバイスチーフ--超小型でプロ仕様に耐える音響特性
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第16回)>今月のキーワード「心をひきつける」--激しい論戦よりも相手に呼びかける論調を(土方了順)
●<Web Usability & Accessibility(第16回)>警察庁サイト--近寄りがたいWebデザイン・構成(濱田英雄・石田直子)
●<筋金入りケーブルテレビ経営(第138講)>ケーブルテレビと全国スポンサーの関係--マスマーケティングだけの時代は終わった(佐野匡男)
●<図読のすすめ(第15回)>町民ニーズを図読する(久恒啓一)
●<電通局長・恒太郎のNMadクリエイティブ(第12回)>Webは広告キャンペーンの司令塔(杉山恒太郎)
●<BETWEEN(編集後記)>>
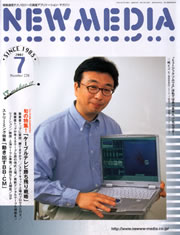
2002年7月号(2002年6月1日発売)
●ケーブルテレビ勝ち残り戦略
ADSL、FTTH、キャリアのVoIP−−。コンペチターの包囲網は狭まるばかりだ。ケーブルテレビに勝機はあるのか? 株式上場による資金調達と経営体制の革新は、その答えの一つである。「勝つ」ためのケーブル局経営、事業戦略、機器・ソリューションに迫った。
・<競争力を問う>事業者トップに質問、「勝てますか?」(石橋庸敏・樋口 淳・奥村見治・長谷川大二・吉村和文・中村正孝)
・<唯一の上場ケーブル局>スターキャット上場までのプロセスと調達資金の使い道
・今、ケーブル局の上場は得策か?
・<解説>最新デジタルケーブル機器&ソリューション(エヌ・ティ・ティ・コムウェア/愛知電子/伊藤忠ケーブルシステム/NECケーブルメディア/沖電気工業/共信テクノソニック/パイオニア/ブロードネットマックス/マスプロ電工)
・<伝送路監視技術>「考え行動するSTM」をOSSBNとCADIXが開発完了(嶋岡利明)
・<アジアのBB普及>世界の先端を行くグレートドラゴン(中国)と「四小龍」(猪股英紀)
・<NCTAレポート>米国のコンベンションビジネス、「テロと共に去りぬ」
・<日本型MSO>J-COM BroadbandがNCTAで受賞、「トリプルプレイ戦略」が高い評価(石橋庸敏・清水輝彦・松崎秀樹)
・キーは「ミドルマイル」−−世界初、日本発のブロードバンド・エクスチェンジ・サービス(藤原 洋・大山 茂・及川満広)
・<テレビショッピング>開局1年目で導入効果を実証したQVCジャパン(佐々木 迅・宮内康行)
●動き出すBB-CM
ブロードバンドで俄然注目を集めているのが、ネットワークでの動画CMだ。2005年には、2,000億円市場を突破するという予測も飛び出してきた。これまでのネット広告とは違うメディアの誕生だ。最新動向、技術特徴、そして気になる各社の事業展望を特集した。
・<「ADmission」提案のねらい>BB-CM浮沈のカギを握る著作隣接権処理(峯川 卓)
・<技術レポート>各方式の違いはココだ(姉歯 康)
・<解説>BB-CM各社の事業展望(アゼスト/オプティム/サイバーウィング/CMナビ・プロジェクト/パサタ/ブロードバンドADソリューション/シーエムジャパン)
■一般記事
●<2002FIFAワールドカップ>戦いぶりが即わかる、NHKBSデジタル・データ放送
●<映画『模倣犯』を監督>「HD24pは僕が本当にほしかったメディアなんだ」(森田芳光)
●<シリーズEPSON EXCELLENCE(第19回)>プロジェクターでインフォームドコンセントを実践する寺岡歯科医院
●<液晶プロジェクター>ついにセイコーエプソンが超えた「2kgの壁」(村瀬孝矢)
●<日米韓ブロードバンド国家戦略の最新事情(第2回)>韓国−−大成功した大胆なIT政策の転換(青柳武彦)
●<編集長がズバリ問う BBストリーミングのターゲット(第7回)>「儲かるのはアダルトサイト」ではBBコンテンツの将来は絶望だ−−アルケミア
●<NAB2002>米DTV普及策へ動く(隈部紀生・姉歯 康)
●<The Challengedとメディアサポート(第55回)>情報アクセシビリティ最前線(2) トップを走る日本IBMの軌跡(中和正彦)
●<電子自治体と情報セキュリティ>絶対に必要な意見交換とコンサル(森井昌克・藤谷護人・八木淳一・井上陽一・中本健司・浦山清治)
●<県民医療の向上>「いわて医療情報ネットワークシステム」始動(関山昌人・澤井高志・生田孝雄・吉田郁彦・森 広)
●<デジタル・パブリッシング提案(第2回)>メーカーの小売店販促ツール制作を支援する「刷込みじょうず」(和泉広彦)
●<NM INFO>NEBA定時総会で「プラズマ、液晶テレビが復調のカギ」 ほか
■連載
●<今月の表紙>三崎正之・松下電器産業(株)マルチメディア開発センター音響グループチームリーダー−−ユビキタス時代の音楽生活に提案する、感性イメージの選曲技術
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<筋金入りケーブルテレビ経営(第137講)>ケーブルテレビは勝てるのか−−コンテンツがすべての源(佐野匡男)
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第15回)>今月のキーワード「改革不況」−−「改革念仏」のままでは日本経済は崩壊する(土方了順)
●<Web Usability & Accessibility(第15回)>文部科学省サイト−−ナビシステムやページ構成などに難あり(濱田英雄・石田直子)
●<BETWEEN(編集後記)>
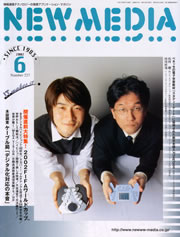
2002年6月号(2002年5月1日発売)
●<開催直前大特集!>2002 FIFAワールドカップ 世紀熱島! デジタル放送×IT
2002FIFAワールドカップは、放送ではデジタルハイビジョン放送とデータ放送が活躍し、ネットワークではブロードバンド環境でストリーミングによる情報サービスも予定されており、ITでも画期的な大会である。ワールドカップのデジタル最前線をレポートする。
・BSデジタルハイビジョンでワールドカップを
・SKY PerfecTV!は合計10ch、マルチアングルで全64試合を生中継
・異色解説者に聞く、おもしろテレビ観戦法(富樫洋一・羽中田 昌)
・「超キレイ」なハイビジョン録画を活用する
・ワールドカップの「い・ろ・は」(広瀬一郎)
・大会運営で大活躍するIT
・世界が驚くハイビジョン+超横長+超大画面「MEG VISION」登場
・ワールドカップ特選「名言・至言」(広瀬一郎)
●<本誌調査「第11・12回ケーブルテレビデジタル化実態調査」>ケーブル局デジタル化の本音
ケーブルテレビ局は現在どのようなサービスを提供し、また、メディア融合時代へ向けて準備をしているのか。本誌編集部の調査に対し、全国159局から回答を得た。第2部では、ケーブル局注目のピンポイント気象情報サービスの実態を調査し、戦略を探った。
・32%がBB動画配信商用化、70%がVoIPに期待
・ピンポイント気象情報はキラーコンテンツ
・250局が採用するウェザーニューズのピンポイント気象情報
■一般記事
●<シリーズ・地方民放の地上デジタル「戦略方程式」(第4回)>
・RKB(毎日放送)−−デジタル時代の「i」を意識した続々のトライアル
・TVA(テレビ愛知)−−ケータイ連動番組や海外買い付けなどオリジナルソフト拡充
●<編集長がズバリ問う BBストリーミングのターゲット(第6回)>主催ゲームの全打席を映像クリップで配信−−中日ドラゴンズ映像サービス協議会
●森田富士郎撮影監督が高く評価「世界に誇れるカメラだ」−−松下電器が「Varicam」の試写・評価イベント開催
●<日米韓ブロードバンド国家戦略の最新事情(第1回)>米国−−トウジン・ディンゲル法案をめぐって(青柳武彦)
●<韓国映画事情レポート>インターネット映画と投資組合(Yang, Woo Seok)
●東京−大阪−福岡間の光ファイバー網完成で、今夏から新ソリューション−−ネットワークソリューションプロバイダーのグローバルアクセス(寺本雅夫)
●<電子自治体と情報セキュリティの専門家が鼎談>自治体の情報セキュリティはいかにあるべきか(松崎秀樹・坂 明・井上陽一)
●<シリーズEPSON EXCELLENCE(第18回)>世界最軽量液晶プロジェクター「ELP-730」「ELP-720」(内野信也)
●年間13万人が受験−−ビジネス能力認定を専門に行う日本有数の団体、サーティファイ(国山広一)
●<The Challengedとメディアサポート(第54回)>岩手をチャレンジドのイーハトーブに−−「CJF2002・いわて大会」プレ大会(中和正彦)
●<デジタル・パブリッシング提案(第1回)>インターネットとはがきを組み合わせた新広告メディア「ぽすこみ」
●<NM REPORT>Mac OS Xでプロ市場へシフトか!?−−Macworld Expoレポート(姉歯 康)
●<NM WATCH>コダック・デジタルシネマ・システムが2003年いよいよ事業化、映画業界が変わる
●<NM INFO>プロジェクター教育活用研究会、2年間の活動終える ほか
■連載
●<今月の表紙>松村 聰・(株)ベネッセコーポレーション 教具開発室小学講座高学年セクション・セクションリーダー、田川欣哉・リーディング・エッジ・デザイン−−採用理由は「tagtypeは小学生でも簡単にできそう」
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<筋金入りケーブルテレビ経営(第136講)>結んで、開いて−−既存の縁と線を生かした事業を(佐野匡男)
●<電通局長・恒太郎のNMadクリエイティブ(第11回)>もはやバナーだけではネット広告は語れない(杉山恒太郎)
●<Web Usability & Accessibility(第14回)>JAWOCサイト−−イエローカード続出のサイト(濱田英雄・石田直子)
●<図読のすすめ(第14回)>ドラッカーの経営学を図読する(第2回)(久恒啓一)
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第14回)>今月のキーワード「3月危機」−−「3月」危機は免れたけれど(土方了順)
●<BETWEEN(編集後記)>
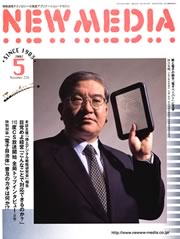
2002年5月号(2002年4月1日発売)
●<本誌主催・地方民放「地上デジタル戦略」合宿研究会レポート>こんなことで地上デジタルに対応できるか
・野村證券がBSデジタルでエリア別マーケティング
・放送局経営者のためのシステム提案(東芝/松下電器産業/ソニー/ヒビノドットコム/NECソリューションズ/大日本スクリーン製造/アビッドジャパン/日本SGI)
・<編集長がズバリ問う BBストリーミングのターゲット(第5回)>トレソーラ−−TBS+フジ+テレ朝のブロードバンド連合、今夏に実証実験を計画
2月14日・15日の2日間、地方民放「地上デジタル戦略」合宿研究会を弊誌主催で開催。「デジタル放送に向けた意識改革」を叫ばざるを得ない苦しい胸のうちから、ブロードバンド時代の放送事業が求めるべきビジネスプランまで、縦横に意見交換を繰り広げた。
●110度CS全局トップに聞く「これが我がチャンネルの見どころ、使いどころだ」(前編=プラットワン編)(王 東順・舛方勝宏・小林 樹・武田 彰・松崎淳嗣・塚田史郎・竹内宏二・片岡久實)
・<110度CSへの視点>トラポン代の値下げと受像機の普及がカギ(西村泰重)
ついに110度CS放送がスタートした。各委託放送事業者のトップにご登場願い、自社の番組は従来の地上波、BS、そして110度CSの他局の番組とはどこが決定的に違うのか、語っていただいた。今回は先発組のプラットワン陣営の8社(プラットワンを含む)を掲載。
●<特別対談>「電子自治体」普及のカギは何か!?(大久保利之・吉崎正弘)
地域行政のあり方まで変える電子自治体が注目を集めている。効果的な情報化で魅力的なまちづくりを行うことが、地域が生き残っていくための重要なカギとなる。地域情報化のスペシャリストが、電子自治体の課題と実現するためのポイントを語り合った。
■一般記事
●「ヨッ、三代目!」“砧のランドマーク”NHK技研新棟完成
●<NHK「番組技術展」>現場技術者の創意工夫が放送の底力を生み出す(三浦真吾)
●<座談会>膨張する電子政府のデータ管理とSAN(須藤 修・松島 努・永久 茂)
●さらば「http」「www」「co.jp」−−Webの成熟、リアルネームズの「インターネットキーワード」(田中里沙・新堀 進・中島將典・梶野清治)
●<ファーストクラス・ケーブルテレビ局訪問−−スーパーネットワークユー+浦安市編>「eマチづくり」に欠かせないブロードバンドと最強の電子自治体(松崎秀樹・田代壽郎・中村晴男・藤波陽四郎・石橋庸敏・廣瀬禎彦)
●「銀河デジタルネットワーク」プロジェクト>岩手県の9ケーブル局を連結、既存光ネットワークとも接続(和山修一・藤原伸彦・佐々木隆一・齊藤 豊・瀧澤 淳・山本光浩)
●<第3回デジタルアーカイブ・アウォード受賞>デジタルアーカイブのリーダーたち(中川惠司・古家時雄・高橋昭憲)
●<高画質画像ビジネス研究会>ブロードバンド時代だから可能になった高画質画像ビジネスの最前線
●<検証−−携帯電話トラブルはなぜ続発するのか(第2回)>警告!! 携帯メールの危険な兆候(曽崎重之)
●「今情報」を反映させた変動料金制で、ビジネスチャンス大幅拡大−−逆転の発想「ネコの目システム」
●<The Challengedとメディアサポート(第53回)>「チャレンジドを納税者に」が政治の舞台に−−女性議員プロジェクト発足(中和正彦)
●<NM WATCH>学校教育の情報化「ミレニアム・プロジェクト」、ハード整備に地域格差
●<NM WATCH>タカラ「チョロQ」が電気自動車に!? 「Q-CAR」に意外な可能性(中和正彦)
●<NM REPORT>混迷!! 12cm光ディスク、9社共同で「Blu-ray Disc」規格を発表(麻倉怜士)
●<NM INFO>通勤電車の中でインターネット!? JR東日本の次世代通勤電車「ACトレイン」ほか
■連載
●<今月の表紙>河合英明・凸版印刷(株)取締役、生産・技術・研究本部長兼新商品事業推進本部担当−−紙と電子の融合「電子ペーパー」に王手、カラー化の改良と量産体制で本格商用化へ
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<筋金入りケーブルテレビ経営(第135講)>中高年市場にケーブルを−−顧客、広告主、出演者、株主すべて地域住民(佐野匡男)
●<Web Usability & Accessibility(第13回)>財務省サイト−−簡潔・わかりやすさで平均点以上(濱田英雄・石田直子)
●<電通局長・恒太郎のNMadクリエイティブ(第10回)>「メディアミックス」から「メディアフュージョン」へ(杉山恒太郎)
●<図読のすすめ(第13回)>「ドラッカーのタイムマネジメント論」を図読する(久恒啓一)
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第13回)>今月のキーワード「ナレッジマイニング」−−組織風土、企業文化、そしてナレッジマイニング(土方了順)
●<BETWEEN(編集後記)>

●マクドナルドのIT戦略「エブリデイ・マック」
国内のハンバーガー市場で約65%という圧倒的シェアを誇っている日本マクドナルドは2002年2月、新会社「エブリデイ・マック」を立ち上げ、日本最大のeコマース・プラットフォーム事業を展開すると発表した。日本マクドナルドのIT戦略を探る。
・顧客満足をバーチャルの世界まで広げる独自のeビジネス
・ITを駆使したマックの次世代型店舗
●ホームシアター用液晶プロジェクター、エプソンからデビュー
「シアターのような大画面を家庭でも」という夢を今すぐかなえてくれるホームシアタープロジェクターが2モデル、エプソンから発売された。同社が得意とする液晶パネルの開発力とカラープリンタで磨き上げたカラーマネージメント技術を集中させた製品だ。
・大画面ホームシアターの“特等席”(降旗國臣)
・ホームシアターのプロが「厳しい眼」で“観”定(朝沼予史宏・麻倉怜士・藤原陽祐・吉田伊織)
●<地方民放デジタル戦略“本音”調査(第3弾)>地方民放テレビ53局の「ケータイ活用事情」
急増した携帯電話利用者に対して、地方民放テレビ局はどのようなサービスを提供し、新規ビジネスへの糸口をつかもうとしているのか。ケータイサービスを実施中の地方民放66局を対象に、“本音調査”を実施した。回答からは各局担当者の「迷い」が感じられる。
・モバイル系ビジネスの手応えは「△」
・ケータイ放送実験で見えてきた近未来型サービス
●PowerPointでWebサイト制作−−「インパティカ」を発展開発した「P4」をIMJ社が日本展開(太場次一・大久保圭二・神谷俊隆・小芝亜紀・宮崎龍彦
「パワポだからできる」「パワポにしかできない」−−。ソフトウエア「インパティカ」とその普及版パッケージ「P4」を使えば、HTMLが書けなくても、特殊なソフトを使いこなせなくても、パワーポイントで作成したコンテンツがそのままWebサイトになる。)
■一般記事
●全世界で15万台の実績−−DVCPROの最新機で地上デジタルへの移行を強力支援(山本克彦)
●<ソルトレークシティー・オリンピック>NHKデータ放送、これが挑戦だ(宮崎経生)
●<ハイビジョン放映と大型映像>タイガー・ウッズの神がかりショット、その瞬間、大画面が“揺れた”!(原 康二・杉浦俊太郎・宮田 隆・渡辺栄一)
●<シリーズ・地方民放の地上デジタル“戦略方程式”(第3回)>
・TSS(テレビ新広島)−−系列全体で営放システム標準化
・HAB(北陸朝日放送)−−平均年齢34歳の若さでブロードバンドを模索
・ABN(長野朝日放送)−−大成功「ふるさとCM大賞」応募全作品を常時動画配信
●<座談会>「今年のNABはここが見どころだ」
・放送の最新動向はNABにいかねばわからない(阿部正吉・山内信治・北出継哉・金丸幹夫・八巻 磐)
・放送局のストリーミング事業はコンテンツを二次利用していては失敗する
●<編集長がズバリ問う BBストリーミングのターゲット(第4回)>BBサービス研究組織「BBit Japan」−−コンテンツの全国配信をにらむ電力10社連合
●<覆面座談会>放送事業のハード・ソフト分離を謳うIT規制調査会「宮内レポート」の背景にあるもの
●「電子自治体の情報危機管理」に熱い視線−−関東と関西でデジタルアーカイブ現場研究会開催(壱岐 徹)
●<デジタルナーシングホーム>最先端ITを活用した介護専用型老人ホーム
●驚異の成長力・経営力の秘密−−同業他社が次々と消え去る中、NECインターチャネルはどうして生き残れたのか?
●<NM WATCH>データビッグバンへの危機管理対策に「SAN」導入を推進すべし
●<NM REPORT>世界初のカラー有機EL搭載ケータイがたった1カ月半で消えた理由(川田宏之)
●<NM TECH>3人の若手天才クリエーターが対話型ロボット「memoni」を開発
●<NM INFO>三菱電機研究開発成果発表会に200名超す記者、アナリストが参加 ほか>
■連載
●<今月の表紙>ルジェロ・ミケレット・京都大学大学院工学研究科材料科学専攻助手・理学博士−−光ファイバーとナノ技術で極小LED発光を確認
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<Web Usability & Accessibility(第12回)>農林水産省サイト−−デザインやナビ機能に一層の努力を(濱田英雄・石田直子)
●<図読のすすめ(第12回)>「地下鉄大江戸線効果 暮らしのバリア取り除く」を図読する(久恒啓一)
●<電通局長・恒太郎のNMadクリエイティブ(第9回)>ブロードバンドでインターネットはマス化に走るのか?(杉山恒太郎)
●<筋金入りケーブルテレビ経営(第134講)>最先端が最良でもない−−描いてほしい、ケーブル事業の将来像(佐野匡男)
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第12回)>今月のキーワード「小説の言語」−−小説の表現と構造から相手を引き込む話法を学べ(土方了順)
●<BETWEEN(編集後記)>
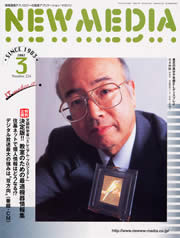
2002年3月号(2002年2月1日発売)
●教室にふさわしい「プロジェクター、デジタルカメラ、電子ボード」選択のための情報集−−文部科学省「ミレニアム・プロジェクト」に対応した特別企画(下山真二・山田英子・小島淳子・金森克浩・田邊則彦・村瀬孝矢・吉村 永)
文部科学省が推進する「ミレニアム・プロジェクト」により、全国約50万の教室にプロジェクターなどの表示装置が1台装備される。教育現場で、本当に使いやすいモノとは何か。5名の先生方がプロジェクターとデジタルカメラを実際に体験、評価した。
・教室で使って便利なプロジェクター機能解説
・学校の先生などによるプロジェクター体験評価と製品情報
・プリンタ、ドキュメントカメラ製品情報
・デジカメを使って学校でできること
・学校でデジカメをより便利に、賢く使うためのQ&A
・授業で使いやすいデジカメとは
・学校の先生などによるデジカメ体験評価と製品情報
・電子ボードの種類
・教室にふさわしい電子ボード製品情報
・<三洋電機>「応援します。わかりやすく、楽しく学ぶために」
・<日立製作所>教室での“使いやすさ”を徹底追求したプロジェクター
・<プラスビジョン>授業で大活躍するインタラクティブボードおもしろ活用事例
・<三菱電機>授業への集中力を高めるプロジェクター
・<コマツ>プロジェクターを無線LANで共有化し、生徒主導の研究発表会
・<オーエス>文教市場No.1シェアのスクリーンメーカー、充実のサポート体制
・「エプソンならでは」学校教育のお手伝い−−児童、生徒の「調べる、まとめる、 発表する」をトータルサポート
●住基ネットで個人情報はどうなる!?−−11ケタの住民票コードでコンピュータ一元管理
国民全員に番号を割り当て、個人情報をコンピュータで一元管理する「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」が8月に稼働する。しかし個人情報の大量漏洩の心配や国民総背番号制に道を開くことから、反対の声も大きい。住基ネットの問題点を探った。
・<創刊224号記念対談>住基ネットシステムと個人情報の保護(山田 宏・伊藤穰一)
・<解説レポート>住基ネットで個人情報はどうなる!?(臺 宏士)
●デジタル放送最大の強みは“双方向”番組・CM
米国同時多発テロ事件などの影響で個人消費が低迷する中、BSデジタルテレビの2001年11月の国内出荷台数は前年同月比112.6%と健闘した((社)電子情報技術産業協会調べ)。ハードの価格低下ととともに、「使うテレビ」への興味がこの数字を後押ししている。
・NHK・BS-i・BSフジ・WOWOWが放送史初のクイズ番組−−同時+生+双方向とチャンネル切り替え参加を実現
・毎回1万人の参加、リターン8,500、視聴リピート7割以上−−BS-iの「TIME OVER」放送開始1年
・テレビの広告媒体価値を変えた視聴者直送CM−−BSデジタルCMの仕掛人3人が語る(小川由紀夫・前田理恵・小川 泰)
■一般記事
●京都発、デジタルアーカイブ技術のデファクトスタンダード「VFZ」−−セラーテム社の新画像フォーマット(長尾 真・新藤次郎・柴田 満・清水宏一)
●<ファーストクラス・ケーブルテレビ局訪問−−ケーブルテレビ山形編>「バーチャルシティやまがた」プロジェクトを推進する、最先端の第4世代ケーブル局(吉村和文・廣瀬禎彦・渡辺 聡・草刈 忍・深町俊幸・中山裕平・大村敦子)
●<シリーズ「地方民放の地上デジタル“戦略方程式”」(第2回)>
・<SBS(静岡放送)>サブチャンネルの割当をぜひとも
・<RNB(南海放送)>ケータイへの情報提供で探る新規デジタル事業
●<編集長がズバリ問う BBストリーミングのターゲット(第3回)>凸版印刷「@irBitway」−−独自の“決済機能”を提供、PDAへのコンテンツ配信ポータル(野沢宏一郎・大石英司・淡野 正)
●<第34回ウエスタンショーレポート>テロで参加は激減したが、デジタルケーブルへの熱い挑戦が続いている(山口正裕)
●ケーブルテレビ局がコールセンターを自社運営する理由−−ZTVなどの先進局
●<NTTコムウェア>VoIP活用により低コストでコンタクトセンターを構築
●<フォトレポート>ケーブルコミュニケーション長良川が「CCN」に大変身
●<NM REPORT>麻倉怜士が見たCES2002(麻倉怜士)
●<NM INFO>博報堂、TBS、NTTドコモ、NTTデータがケータイ動画CMの配信実験実施 ほか
■連載
●<今月の表紙>茨木伸樹・(株)東芝 ディスプレイ・部品材料社液晶開発センター所長・工学博士−−東芝の有機ELは「高分子有機膜」を採用
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<電通局長・恒太郎のNMadクリエイティブ(第8回)>From creating for media to creating media.(杉山恒太郎)
●<筋金入りケーブルテレビ経営(第133講)>ケーブル業界の魅力訴求を強力に−−決まっている事業の方向(佐野匡男)
●<Web Usability & Accessibility(第11回)>日本道路公団サイト−−ナビ機能など利用時を考えた工夫を(濱田英雄・石田直子)
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第11回)>今月のキーワード「小泉首相年頭会見」−−構造改革の如何に関わらず、小泉政権安泰の気配(土方了順)
●<図読のすすめ(第11回)>「イベントで街づくり 成功のカギは市民参加」(『週刊東洋経済』記事)を図読する(久恒啓一)
●<BETWEEN(編集後記)>
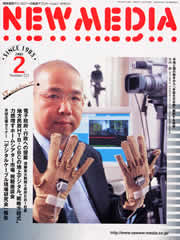
2002年2月号(2002年1月1日発売)
●<創刊223号記念特別対談>電子政府・行政の実現へ一つの提案(須藤 修・長井正利)
政府が提唱する電子政府。2003年までに電子情報を紙情報と同じように扱う行政を実現し、人材面でもアメリカを上回る基盤を持った確固たる電子政府にするというプランが描かれている。そのカギとなるのが、iDC(インターネット・データセンター)をどう活用するかだ。
・電子自治体を推進する50人が現場でアーカイブの実際を視た−−デジタルアーカイブ現場研究会「電子自治体と情報危機管理」関東編(月尾嘉男・高澤信行・清水宏一)
●地上デジタル放送戦略
11月20日、地上デジタル放送のスケジュール見直しが発表になった。アナログ周波数変更対策、通称「アナアナ変換」が予想以上にてこずることが判明したからだ。そもそも地上デジタル放送に関して、「非常に議論が少ない」。スケジュールも放送技術規格も、あまりにも知られていない。
・地上デジタルの開始スケジュールはどうなる!?−−地上デジタルの成否を握る「アナアナ変換」
・<シリーズ「地方民放の地上デジタル“戦略方程式”」(第1回)>HTB=北海道テレビ放送(斎藤忠貞・樋泉 実)/CBC=中部日本放送(水野弘之)
●ホームシアター市場“力感”浮上の理由と体力強化プラン−−7社イチ押し製品を視聴してプロたちが語る(秋山雅和・鈴木新次郎・村山郁二・大橋伸太郎・神崎健太朗・麻倉怜士・村瀬孝矢)
ホームシアター用プロジェクターを視聴して座談、というスタイルは今回で2回目。初回の2001年6月号から約半年。実に激しい変化が見える。市場にも新たな流れが出てきた。その最新動向をホームシアターのプロたちに視聴していただき、今後の強化方向まで語っていただいた。
■一般記事
●教育はNHK永遠のテーマ−−学校のインターネット教材としても活躍(遠藤絢一)
●NECインターチャネルの脅威の経営力−−デジタルコンテンツ界のスーパーエンジン(黒川 湛・桔梗 純・池田昌史)
●<編集長がズバリ問う BBストリーミングのターゲット(第2回)>インプレスTV−−ネットワークによるコンテンツビジネスの“ショールーム”を目指す(萩原和彦)
●「Streaming Media Japan 2001」セミナー報告−−民放キー5局ブロードバンド事業担当者が本音を語る(平松英俊・大原通郎・佐藤信彦・福田 泉・渡辺 豪)
●もう一度見たい場面をケータイでクリップ−−ティージィー情報ネットワークの「P-CLI」はネット映像視聴の新スタイル(河野 勧・堀口宏幸)
●ロードバンドの各種映像配信サービスで大活躍−−沖電気工業のMPEG4対応サーバ「OKI MediaServer」
●動き出したアップルQuickTimeのMPEG-4戦略(姉歯 康)
●期待と不安が交錯、ケーブルテレビは最後に生き残れるか?!−−日本ケーブルテレビ連盟九州支部「平成13年度トップセミナー」開催
●日本初、世界最大級規模のコミュニティ型VoIPサ−ビスに熱い視線−−デジタルケーブル現場研究会「和田山町のVoIPを視る」セミナー報告
●サーバ管理者よ、安心して眠れ!−−ランスが独自開発したケーブル局専用「Lx‐CATV Server」(鈴木 昭)
●アルジャジーラは「9・11」を知っていた!?−−「戦争のメディア」湾岸戦争からアフガニスタンへ(徳久 勲)
●松下電器がデジタルシネマに本格進出−−“映画フィルムカメラの画質を再現”した「Varicam」(田中誠一・田口勝行・石井英範)
●「色純度の高いシャキッとした映像。これはキヤノンの自信作に違いない」−−キヤノンのプロジェクター新製品「LV-X1」「LV-7345」を体験評価(村瀬孝矢)
●東京モーターショーの大型映像演出、フルカラーLED大画面が急増(原 啓起・清水英治)
●コンピュータとアートを融合させた男、ピーター・コーウェル(中島 興)
●<The Challengedとメディアサポート(第51回)>情報アクセシビリティ最前線(1) ユニバーサルデザインでNECを変える!?(中和正彦)
●<NM WATCH>ep、代理店制度で会員加入促進、2002年春事業開始までの道筋見える
●<NM INFO>松下精工が燃料電池用高効率空気ブロワを開発 ほか
■連載
●<今月の表紙>竹内 勝・(株)日立製作所 中央研究所マルチメディアシステム研究部主任研究員−−頭の動きから手話の文法情報を分析
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>
●<図読のすすめ(第10回)>『経済財政白書』の財政分析を図読する(久恒啓一)
●<Web Usability & Accessibility(第10回)>宮内庁サイトを考察(濱田英雄・石田直子)
●<筋金入りケーブルテレビ経営(第132講)>人間の目は近くを長く見られない−−競合の時代、横並びは命取り(佐野匡男)
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第10回)>今月のキーワード「社説にみる2002年予測」−−キーワード群の変遷から社会の変化が読み取れる(土方了順)
●<BETWEEN(編集後記)>
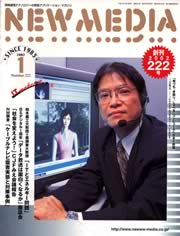
●BSデジタル1周年 普及の意思
BSデジタル放送について新聞などで、「番組が面白くない」「受信機が高すぎる」という正論?らしき声が広がっている。そこで、巻き返しを図る流通とメーカーの「普及の考えと決意」と、「まだ不十分」なデータ放送のパワーアップについて聞いた。 ・「番組が面白くない」への回答だ!--BSデジタル8社が共同キャンペーン ・「そんなに苦戦しているのですか?」-- 流通、メーカーに聞く市場の手応え(NEBA・全商連・三洋電機・シャープ・ソニー・東芝・日本ビクター・パイオニア・日立製作所・松下電器) ・データ放送を面白くする手はあるか(高城 剛・竹内宏彰・堤 俊行・舟橋洋介・水野弘之
●<本誌独自調査>ケーブルテレビで増加する雷害の実態と最新対策事例
「雷の被害が増えて困っている」というケーブルテレビ事業者の声がよく聞かれるようになった。そこで、雷の多い地域のケーブル局を対象に、雷害の実態と対策について調査、取材した。ケーブル局向け雷対策製品も紹介する。
●<創刊222号記念特別対談>エネルギー問題の解決に向け、今ITにできることは何か?(柏木孝夫・廣瀬通孝)
日本のエネルギー安全保障やCO2排出量の抑制が至上課題となる中、IT関連の電力消費量は増え続けている。だが一方で、省エネ技術の鍵を握っているのもITである。新エネルギー研究とシステム工学の第一人者が、ITがエネルギー問題の解決に果たす役割について語り合った。
●<The Challengedとメディアサポート(第50回)>「21世紀、日本は地域から変わる」か--「第7回CJF 2001国際会議 in みえ」報告(中和正彦)
「第7回チャレンジド・ジャパン・フォーラム(CJF)2001国際会議 in みえ」が三重県で開催された。CJFは、自らの課題に挑戦する前向きな障害者=チャレンジドが自立できるIT社会を目指す。今回は地方の、そして個人の自己変革が日本を変えるというメッセージが強く感じられた。
■一般記事
●「地上デジタル放送商戦に臨む松下電器「鶴翼の陣」--新体制で強力サポート
●<図説 燃料電池開発企業相関図(後編)>燃料電池自動車開発状況(1999〜2001年)
●<NM INFO>地上デジタルHDTV+携帯端末向け同時生放送実験実施 ほか
●<デジタル放送と視聴率調査(後編)>どうする、視聴率の計算処理方法--デジタルがもたらした多局化の混迷(藤平芳紀)
●<編集長がズバリ問う BBストリーミングのターゲット(第1回)>ソニー・ミュージックエンタテインメント--常時接続で得られる「参加性」、スピード感が生命線
●ビジネスへの視界が開けたブロードバンド・ストリーミング--エイベックス・ネットワーク+ビーバット+ヒビノドットコム(前田治昌・高田仁一郎・日比野晃久・大関 靖)
●<シリーズEPSON EXCELLENCE(第17回)>セイコーエプソンのプロジェクターシェアNo.1の座、その秘密と今後の展開
●「規格」を意識した斬新な開発・提案が専業メーカー、ケーブル局双方のビジネスチャンスを生む--CADIXのケーブルIPトータルソリューション(杉本 弘・吉田 要・中山貴康・柳迫 誠・嶋岡利明)
●IT産業と環境を考える
・使用済みIT製品は有害廃棄物だ--『IT汚染』(岩波新書)が問いかける視点(吉田文和)
・2002年度中のパソコンリサイクル開始は時期尚早--家電リサイクル法施行から半年、見えてきた課題(岡嶋昇一)
●<インクジェットプリンタ革命(第4回)>製版・印刷工程は一挙にフルデジタル化、IJPによるリモートプルーフの確立 ・完全に認知されたIJPによるプルーフ(箱崎 紘)
・ジャパン・グラフィック・アーツショー2001(JGAS2001)出展15社インタビュー
・プルーフィングの世界をガラリと変えたエプソンのインクジェットプリンタ--大丸印刷が進めるフルデジタル化の最前線(中島弘稀)
●<NM REPORT>「瓢箪から駒」でホクホク市場の着メロ・ビジネス(清水計宏)
■連載
●<今月の表紙>三吉秀夫・シャープ(株)技術本部・横須賀研究センター主任研究員--むずかしく言えば「マルチモーダル・インターフェース開発」
●<編集長メッセージ「新志脳巧商」>創刊222号、熱き厚さに感謝
●<図読のすすめ(第9回)>平松守彦・大分県知事の構想を図読する(久恒啓一)
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第9回)>言語分析の基準--情報を真に読み込むには客観的な評価基準が必要だ(土方了順)
●<Web Usability & Accessibility(第9回)>国税庁サイトを考察(濱田英雄・石田直子)
●<筋金入りケーブルテレビ経営(第131講)>経験したことはよくわかる--けなすのは簡単で、無責任(佐野匡男)
●<NM WORD 決断と行動の言語分析!(第8回)>今月のキーワード「リストラ」--外的要因に押され、リストラが再燃する(土方了順)
●<BETWEEN(編集後記)>